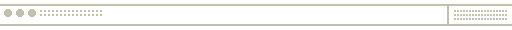
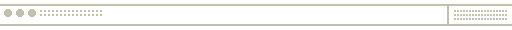
これは、光文社文庫「本格推理(15)」に掲載された、募集要項に添えた文章の原稿です。原稿ですので、誤字・脱字等が多々あります。その点は御容赦ください。
[空前絶後の本格推理小説を求む!]
二階堂黎人
1、『新・本格推理』創刊について
皆さん、こんにちは。私は小説家の二階堂黎人です。本格推理小説を読むのが何より大好きで、ついに自分で本格推理小説を書いてしまった――名探偵・二階堂蘭子シリーズなどを――作家だと言えば、自己紹介になるでしょうか。
実はこの度、私が鮎川哲也先生の跡を継いで――鮎川先生の監修の元――『本格推理』の新編集長をやらせていただくことになりました。本格推理小説の驍将にして名アンソロジストの鮎川先生の後任ですから、たいへんに緊張し、また、大いに責任を感じているところです。ですが、私なりに精一杯、この大任を果たしていく所存ですので、どうかよろしくお願いたします。
つきましては、次回より『本格推理』は『新・本格推理』と名前を変え、再出発することになりました。来年、二〇〇〇年度の秋までを新規募集期間とし、再来年――二十一世紀を迎える二〇〇一年度の春に、この『新・本格推理』の第一巻目を上梓したいと考えています。今までどおりに――いいえ、これまで以上に奮って、多数の作品をどしどし御応募ください。
それから、別巻の『本格推理マガジン』の方も、『新・本格推理マガジン』として生まれ変わります。こちらは、あの芦辺拓氏が編集長を務めますので、合わせて御愛読をお願いします。
さて、『本格推理』はこれまでに十五巻を数えますが、そこから多数の新人を排出しました。延べにして百人以上、毎回三百編を優に超える応募作があり、その後、プロになった作家も何人もいます。
北森鴻氏や村瀬継弥氏は、さらに鮎川哲也賞を経て大活躍をしている最中ですし、津島誠司氏、柄刀一氏、光原百合氏(吉野桜子改め)なども単行本デビューを遂げました。紫希岬真緒氏、八木健威氏、天宮蠍人氏などを代表とする、非常に有力な常連投稿家を獲得したのも幸いでした。新人発掘の場を提供したものとしては、これらは素晴らしい実績だと思います。
『新・本格推理』でも、ますます、次代を担う新たな本格推理小説作家の登場を期待しています。優れた本格の書き手を、ここから続々と生み出していきたい――それが、私たちスタッフの希望であり、願いでもあるのです。
新編集長に就任した私が、『新・本格推理』の募集に際して最初に述べておきたいことは、「空前絶後の本格推理小説を求む!」ということです。もう一つ付け加えると、「奇想天外で、前人未到の本格推理小説を求む!」ということです。
私たちは、新人の――アマチュアならではの――新鮮な発想と斬新なアイデアを求めています。ですから、どうぞ自由闊達に、広い視野の元、思いっきり奇抜なトリックで、奇想に満ちたプロットで、誰も考えなかったような厳密なロジックで、驚異に溢れたストーリーで、類い希な本格推理小説を書いてください。そして、私たちを大いに驚かせてください。驚きこそが、ミステリーの命です。醍醐味です。意外な犯人に対する驚き、実際にはあり得ないような状況に対する驚き、想像すらしなかった巧妙なトリックに対する驚き、常識をくつがえす殺人動機、意表を突いた展開――そうした様々な驚きを、本格推理に寄せる情熱と共に、ぜひ私たちに提供してください。
江戸川乱歩はその昔、己の作品の力で、この日本に英米のような理知的な本格推理小説を根付かせたいと考えました。『二銭銅貨』や『一枚の切符』を書き、その原稿を博文館の森下雨村編集長の元へ送りつけたのはそのためです。横溝正史は、戦争が終わると、今度こそ本格推理小説を自由に書ける時代が来たと歓喜し、あの『本陣殺人事件』に着手しました。また、高木彬光も、新時代の欲求に突き動かされて『刺青殺人事件』を一気呵成に書き上げたのです。鮎川哲也先生も、誰に読ませるというのではなく――出版の宛てもないのに――本格推理小説の持つ魅力に魂を揺さぶられて、『ペトロフ事件』や『黒いトランク』を書きました。
新本格推理作家の多くも同様です。綾辻行人氏も有栖川有栖氏も芦辺拓氏も、そして、この私も、本格推理小説が堪らないほど読みたく、しかし、本格推理小説が巷にないのなら――そんな不遇の時代が昔、この日本にあったのです――自分で書いてしまうしかないと、『十角館の殺人』や『月光ゲーム』や『殺人喜劇の13人』や『吸血の家』に手を染めたのです。それは、けっして誰かに頼まれたからはありません。本格推理小説が心の底から好きだという純粋な情動から心身を突き動かされ、筆を走らせる要因となったのです。
乱歩はかつて、随筆「一人の芭蕉の問題」で、芭蕉のような革新的な天才ミステリー作家を文壇は求めている、世にいでよ!と、声高にうたいあげました。ですが、私はもっと貪欲です。私は一人ではなく、大勢の《レオナルド・ダ・ヴィンチ》を求めているのです。『新・本格推理』からたくさんの革新的な作家が生まれ、それぞれの独創性を顕示し、本格推理の可能性を際限なく拡大していってもらいたいと願うのです。
その独創性は、物語の面でも、プロット構築の面でも、トリック案出の面でも何でもかまいません。前代未聞で驚天動地の作品を、従来の固定観念にとらわれない前衛的な作品を、夢と浪漫に溢れた作品を、流行に拘泥しない徹底的な内容の作品を、誇り高い作品を――私たちは切望しています。
現在はミステリー・ブームだと言われています。なるほど、毎月刊行されるミステリー本の数は相当なものになります。新本格推理は若い読者の圧倒的な支持を受け、書き手も増え、執筆側の層はかなり厚くなりました。また、今や、中間小説や娯楽小説のほとんどがミステリーという名の元に売られています。直木賞などの受賞作にミステリーと呼ばれる作品が増えているのがその明かしです。
しかし、そのミステリー・ブームも、残念ながら本質的なものではありません。かなり表面的なものなのです。ミステリー出版全体の刊行点数は増大しましたが、一冊ずつの発行部数はそれほど増えているわけではありません。何万部、何十万部と売れる作品もわずかです。しかも、本格推理小説の場合には、やはりそこに独特の様式性や内容理解が求められるため、コアなファンは多くても、その読者数にはまだまだ限りがあります。いや、それどころか、本物のミステリーというものがどんなものか、それすら理解されていないというのが現状でしょう。
したがって、本格推理ファンが一人でも増えてくれるよう、私たち作家は、日々面白い小説を書く努力をせねばなりません。と同時に、《本格推理小説》とは何なのか、その独自性とはどのようなものか、その実体と特質に関する啓蒙をもっと行なうべきです。そのためには、ベテラン作家の熟練した手練れと共に、新人やアマチュアの型にはまらない柔軟な発想や活力が必要なのです。だからこそ、この『新・本格推理』が設けられたわけです。
私たち『新・本格推理』のスタッフが求めているのは、平凡なミステリーや単なる普通のエンターテイメントではなく、非凡で、清新な、熱意の漲る、それこそ黄金色に輝く、これぞ本格推理小説という強烈な作品です。ぜひその点を充分に踏まえた上で――ただし、楽しんで書くことを忘れず――読んでわくわくするような魅惑的な作品を投じてください。
なお、応募規定枚数ですが、今までの四百字詰め原稿用紙五十枚から、百枚に拡大しました。
本格推理小説の場合、状況説明、登場人物紹介、トリックの手配、伏線や手がかりの挿入など、実に多くの手続きを必要とします。その上、そこに何かの要素――情感でも蘊蓄でも怪奇性でも何でもかまわないが――を盛り込もうと欲張ったら、これは普通の小説以上に、物理的にも精神的にも大変な作業です。したがって、なかなか短い枚数では書ききれないことが多いものです。そこで私たちは、新たに百枚という肥沃な土地を用意したわけです。
応募者の皆さんは、この新たな土地の上で、想像力の翼を思いっきり広げてください。自由に力強く飛び回って、この未開の地を豊穣な驚異の世界に書き換えてください。そして、ミステリー史に燦然と輝くような、ミステリー界に新風を巻き起こすような――まさに奇想が天を動かし、地に鳴動を走らせるような――そんな画期的な推理小説を『新・本格推理』に投じてください。心からお待ちしています。
2、推理小説とは何か
ところで、《本格推理小説》とは何ぞやという問題について、少し触れておきましょう。今さらそんな問題を論じる必要はないと思う方もいるでしょうが、応募作品の中に、時折、本格以外の小説が混じっていて困ることがあるのです。それは、鮎川哲也先生が前にも何度か、『本格推理』の中で注意されたとおりです。
私たち本格ファンからすると残念なことに、本格推理小説が何なんのかを知らない人間が、地球人類の中にはまだ若干名残っています。また、こうした問題を論じることは、体系を論理付けることですから、創作に携わる者にともっても有益な作業となりましょう。
では実際に、皆さんは、本格推理小説がどのようなものだと思いますか。エドガー・アラン・ポーが発明した小説ジャンル? 江戸川乱歩や横溝正史が書いた小説のようなもの? エラリー・クイーンやアガサ・クリスティーやディクスン・カーが書いたようなもの? 犯人が最後に暴露される小説? 犯罪が描かれている小説? 密室殺人のような奇抜なトリックが作中にある小説?
そうです。いろいろな受け止め方や考え方があるでしょう。
しかし、その個々の内容に言及する前に、やはり一般的認識として、いくつかの用語について統一的な見解を求める必要があるかと思います。そこで、以下に、私の考えを披露しておきます。
ただし、これらの定義は、あくまでも個人的なもので、この文章全体の理解のために提示するものです。また、このように分類すれば、混乱を招かないであろうという提言でもあります。それに対して、異論や反論は大いにあるでしょう。それはそれで大いに有意義だと思います。
御存じのとおり、今私たちが問題にしている《いわゆる犯罪事件や謎があって、それが最終的に解き明かされる物語に対するジャンル》の呼称には、様々なものがあります。
《探偵小説》《推理小説》《本格推理小説》《ミステリー(ミステリ)》《本格ミステリー(ミステリ)》。
日本語では以上のようなものだし、英語でも次のようなものがあります。
《Detective Story》《Detective Fiction》《Detective
Novel》《Mystery Story》
さて、これらははたして、同一の物語内容をさす言葉なのでしょうか。それとも、どこかが微妙に違っているのでしょうか。
ここで、日本語における用語の歴史的変遷について、先に御説明しましょう。
《探偵小説》 第二次大戦前。探偵小説としての自我の誕生期。
↓
《推理小説》 戦後。探偵小説の多様化。探偵の「てい」の字の当用漢字もれによる改名。
↓
《ミステリー》 近年。推理小説のいっそうの多様化と、エンターテイメント小説の吸収及び融合化。
日本では戦前、ミステリーは《探偵小説》と呼ばれていました。大戦後、探偵の「偵」の字が当用漢字から落とされたことと、《探偵小説》というだけでは枠にくくれない作品が出てきたために、カテゴリー全体に新しい名称が必要になり、木々高太郎らが提唱した《推理小説》という言葉が定着しました。その後、さらに多様化した作品が生まれたり翻訳されたりした結果、《推理小説》という名称でも、すべてのジャンルを表現しきれなくなったのです。そこで近年では、《ミステリー》という便利な(ある意味で曖昧な)名称が多く使われるようになったのです。
これはマンガにたとえると解りやすいのですが、戦前から昭和三十年代くらいにかけてはユーモアを含むことを前提に《漫画》と呼ばれ、手塚治虫式ストーリー・マンガの台頭で《マンガ》に変化し、《劇画》や《アニメ》と融合して、最近はよく《コミック》という表記が用いられています。
つまり、現時点で《ミステリー》と言う時には、推理小説のみならず、ハードボイルド、犯罪小説(クライム・ノベル)、スリラー、サスペンス、スパイ小説、一部の冒険小説、一部のホラー小説などを含む、カテゴリーとしての総称と考えるのが一番妥当ではないでしょうか。
そうした現状を踏まえ、《ミステリー》はこのように定義できます。
《ミステリー》とは、小説という虚構の物語の中の、《純文学》 《主流文学》《歴史小説》《時代小説》《SF》《冒険小説》《恐怖小説》などと並び立つ、文学上の一範疇である。そしてかつ、世の中に有形無形で存在するあらゆる《謎》を、自己の物語中に含んだ小説ジャンルの総称である。
ここで言う《謎》とは、「誰が殺人者なのか」というような疑惑から生ずる謎から、密室殺人のような人工的な謎、幸福な生活を送っていたはずの人妻が何故突然失踪したかというような人間心理の謎など、どんな形でもかまいません。極端な話、物語の中に何か一つだけでも謎が含まれれば、広義に解釈して、これを《ミステリー》と呼んで良いかと思います。
ただしその謎は、基本的に、結末で合理的に解決されるものでなければなりません。ここが非常に重要な点です。
また、超常現象などに関するミステリーは、これには含まれません。ストーン・ヘンジの謎とか、ナスカ絵の謎のような歴史上の疑問や、あるいは、UFOや宇宙人の謎といったような神秘的で超自然的な謎は、また別の小説範疇(SFやホラー)や怪奇的なノン・フィクションに任せるべきです。
したがって、私たちが今注目している《ミステリー》というのは、主として犯罪に関する謎が扱われることになります。
次に、この《ミステリー》の内包する性格について考えてみましょう。
《ミステリー》とは、《謎》の存在する小説の総称で、主として、《推理型の小説》と《捜査型の小説》を合わせたものである。
これが私の見解です。いきなり二つの用語が出てきたので、それについて定義しますと、
《推理型の小説》とは、ミステリーのうち、謎を推理という思索的行為によって解決する物語である。《探偵小説》や《推理小説》や《本格ミステリー》がこれに該当する。
《捜査型の小説》とは、ミステリーのうち、謎を捜査という体験的行動によって解決する物語である。《私立探偵小説》や《警察小説》や《犯罪小説》などがこれに該当する。
ということになります。
最大の違いは、謎の探求の仕方です。《推理型の小説》の場合には、文字どおり探偵もしくはその他の人物の推理によって(頭を使って)謎の解明をみるわけで、推論を組み立てるために、必然的に物語中には、ちりばめられた手がかりや証拠が必要となります。推理小説の物語中には、よく「読者への挑戦」が挿入されますが、それは手がかりを過不足なく、公平に読者へも分け与えたという、作者からの明確な意志表示なのです。
しかし、《捜査型の小説》の場合には、必ずしも手がかりは必要としません。物語の推移や探偵の行動によって(ようするに、相手をぶん殴って白状させるとか)、順次、結論や結末にたどりつけば良いのです。謎の解決は、たいていの場合、小説の最後に作者から一方的に提示されることになります。
ですから、《推理型の小説》は、物語の発端から後ろ向きに謎が探求されるわけですが、《捜査型の小説》は前向きに謎が探求されるという違いもあります。
したがって、この二つの小説区分は、《ミステリー》という同じカテゴリーの中に含まれていても、根本的には、性質や目的がまったく違う種類のものなのです。これは、ミステリーを論じる時には非常に重要な事柄なのですが、残念ながら、まだ一般的にはあまり明確に認知されていないようです。
そこで、この二種類のミステリーに関して、創作法の違いを見てみましょう。
【推理型の小説】
① トリックやプロットを考える(結論)。
② トリックやプロットに状況や舞台をあてはめる。
③ 状況に人物を当てはめる。
④ 状況と人物にふさわしい物語を考える。
⑤ 全体のプロットを再構成する(発端)。
(全体のプロットを、ほぼ最初に立てる必要がある)
【捜査型の小説】
① 全体の物語やプロットを考える(発端)。
② 人物設定を考える。
③ 状況や物語をあてはめる。
④ トリックを付加することもある。
⑤ 解決を考える(結論)。
(プロットは、物語の進行に合わせてできあがる)
という訳です。紙面の都合で、このあたりを今回は深く説明する余裕はありませんが、実作に照らし合わせて、よく考察してみてください。たぶん、実際の執筆作業の際に体現できるでしょう。
3 《本格推理》の定義
《ミステリー》という小説を定義したところで、いよいよ、《本格推理小説》とは何かという命題にかかります。
過去において、実に多くの論客が、それぞれの独特な言い回しで、本格推理小説に関する定義を述べてきました。たとえば、そのいくつかを拾ってみるとこうなります。
【江戸川乱歩】
探偵小説とは難解な秘密が多かれ少なかれ論理的に徐々に解かれて行く経路の面白さを主眼とする文学である。(鬼の言葉 昭和十一年)
探偵小説とは、主として犯罪に関する難解な秘密が、論理的に、徐々に解かれて行く経路の面白さを主眼とする文学である。(幻影城 昭和二十六年)
【甲賀三郎】
探偵小説とは、まず犯罪――主として殺人――が起こり、その犯人を操作する人物――必ずしも職業探偵に限らない――が、主人公として活躍する物語である。(ぷろふいる 昭和十年)
【ドロシイ・セイヤーズ】
探偵小説とは、犯罪とその捜査をとりあつかった小説のうち、謎の設定とその開設が、もっぱら論理的操作によってのみ行われるものをさしていう。(探偵・ミステリ・恐怖小説集 一九二八年)
【レジ・メサック】
探偵小説はなによりもまず、不可思議な事件の正確な状況を、合理的な方法で理路整然と一歩一歩、発見してゆく過程を描いた物語である。(『探偵小説』と科学思想の影響 一九二九年)
【H・ダグラス・トムスン】
探偵小説とは、ずばり言って謎解きである。手持ちのデータをもとに、論理的につめていって解答にいたるプロセスを骨子としている。
【ジョン・ディクスン・カー】
推理小説とは、犯罪者と探偵との闘争であり、犯罪者はアリバイ作り、新奇な殺害方法の案出など、巧妙な策略の力で罪を免れ、逮捕はおろか、疑われさえもしないのだが、探偵は読者に事前に知らされている証拠の収集によって、犯罪者の正体をあばくのを中心的なテーマとする物語である。(地上最大のゲーム 一九四七年)
【木々高太郎】
推理小説とは、推理と思索を基調とした小説で、探偵小説もこれを含む。(推理小説叢書 昭和二十一年)
【高木彬光】
推理小説とは、ある一つの事件に対する、解釈の論理と心理とを、主題とした小説である。(探偵作家クラブ会報 昭和二十四年)
【大坪砂男】
推理小説とは、未知の世界を推理手法で探求する精神の物質化したものである。(探偵作家クラブ会報20号)
【松浦正人(引用者・綾辻行人)】
(本格)推理小説の指標は、謎とその『論理』的解明(ここでいう『論理』とは、数学的証明のみを意味しない)があり、これらと、小説内の様々な要素とあいまって、それが現実(常識)世界と一致するかは別として、見事に一つの閉ざされた空間を形成していることだろう……。(水車館の殺人のあとがき 一九八八年)
【島田荘司】
本格ミステリーとは、幻想的な謎と、高度な論理性の二つを有する(形式の)小説である。(本格ミステリー宣言 一九八九年)
どうでしょうか。本格推理小説なるものがどういうものか、これらの定義から解りましたか。いずれも大差はないと思われるかもしれませんし、もしかすると、余計解らなくなったかもしれませんね。
結論を言えば、これらの定義はどれも正しいし、しかし、どれも充分ではありません。そもそも本格推理小説の定義というものは、その書き手及び読み手が独自に考量するものだからです。絶対無比の定義など、この世には存在しないのです。あなたがこうだと思えば、それが正しい本格推理小説の定義に成り得るのです。
しかし、その一方で、最大公約数的な考え方は存在すると言って良いでしょう。それはたとえば、大勢の人間が、「エラリー・クイーンの作品こそはまさに本格推理だ」と思う根拠であるわけです。綾辻行人氏の館シリーズを読んで、「これぞ、本格の神髄だ!」と歓喜する理由なのです。
ここに並べた各人の定義の中にも、いくつかキーワードと思しきものが見受けられます。《犯罪》《謎》《論理》《証拠》など。もしかすると、これらがその最大公約数なのではないでしょうか。つまり、この最大公約数が含まれるかどうかで、他のミステリーと本格推理小説が区別されると言って良いでしょう。
なお、私自身は次のように定義しています。
《本格推理》とは、手がかりと伏線、証拠を基に論理的に解決される謎解き及び犯人当て小説である。
どうやら、私の定義も先人の考えと大差がないようです。
つまり、本格推理小説を書き上げるために必要な最低限のものは、次の四つということになります。
① 謎の提示。
② 謎を解くための手がかり(や伏線)の提示。
③ 手がかりに基づく論理的な推理。
④ 真相の提示。
これが、推理小説の骨格なのです。物語は、この骨格の上に様々な肉や皮膚や衣装を付けて完成されるわけです。
なお、《推理小説》と《本格推理小説》と《本格ミステリー》とはどう違うのでしょうか。単に呼び方が異なるだけでしょうか。
これも私見ですが、今述べたような《本格推理》の定義が満足されている場合には、《推理小説》も《本格推理小説》もまったく同じものです。単に《本格》という言葉は、内容の特化性を強調したものにすぎません。逆に言えば、《本格》と言えるものしか《推理小説》と呼ぶ資格はないというのが、私の個人的な考えです。
《本格ミステリー》もまったく同じことで、《推理小説》を現代風に言い換えた言葉にすぎません。ただ、時として、《推理小説》に何かプラスαをしたという意味合いを持つこともあるでしょう。αの部分は余剰や過剰であり、情感、蘊蓄、何らかの趣向(たとえは、ホラー小説との融合とか)、メタ性、アンチ性などが、あえて付加されているのだとの、発言者の意思表示ととれます。
3、《フェアプレイ》について
江戸川乱歩は、探偵小説の面白さは《出発点における不可思議性、中道におけるサスペンス、結末の意外性》にあると語っています。評論家の津井手郁輝は、その論を踏まえた上で、《探偵小説の面白さは、謎が解かれる方法と過程と結果にまたがる〝解き方〟にあるといってよい》と述べています。
私もやはり重視したいのは、《伏線や手がかり》といった証拠とその処理の仕方です。そうした証拠に基づいて解決される物語こそ、本格推理小説であると言えます。ただ単に拳銃を突きつけて犯人に自白を強要したり、ぶん殴って真相を聞き出したり、のんべんだらりと歩き回っていたりした結果、犯人の告白が書かれた手紙を偶然手に入れるような単純なものは、けっして本格推理と呼ぶ資格はありません。
良質の推理小説は、エラリー・クイーンの国名シリーズのように、物的証拠から演繹的に推理を重ね、唯一無比の結論に達するものなのです。または、クリスティーやカーの小説のように、それ以外にはあり得ない厳密な状況証拠に基づき、単独の解決が導き出されるものもそこに加えて良い良いでしょう。
証拠や手がかりが何故それほどまでに重要かと言えば、それは、探偵や読者が行なう推理や推論の根幹となるものだからです。それだからこそ、《推理小説》を、様々あるミステリー小説のうち、「謎を推理という思索的行為によって解決する物語」と定義することができるわけです。
ですので、探偵が事件に対する推論をどんなに数多く口にしても、それが証拠や手がかりに基づかない場合は、それは単なる空想、単なる妄想にしかすぎません。それではけっして立派な推理小説とは言えないのです。
ここでも極端なことを述べますが、推理小説における結末の意外性は、実は、文中に作者が巧妙にひそませておいた手がかりや伏線から生まれるのです。要するに、結末での推理を読んだ時に、「何てことだ! こんな前の方に証拠があったのか!」とか、「ああ、こんなに明確に手がかりが書いてあったのに! どうして僕は気づかなかったんだ!」という、自分のおろかさ加減に起因する驚きなのです(推理小説には、恐怖とそこからの解放という要素があって、これも結末の謎解きにおけるカタルシスに寄与しています)。
ところで、よく本格推理小説では、《フェアプレイ》精神について語られます。これももちろん、証拠の重視という観点から導き出されたジャンル特有のルールです。証拠を証拠とならしめるために、誰が本当のことを言っているか、誰の言葉が質実なのか、作者は読者に対して常に明確にしておかねばなりません。
【ヴァン・ダインの探偵小説作法二十則から】
① 謎を解明するに当たっては、読者にも作中の探偵と平等の機会が与えられなければならない。
② 作中の犯人が探偵に対して適当に行なう策略やごまかしのほかには、故意に読者を惑わすような記述があってはならない。
【リチャード・ハルの探偵小説とその十則から】
① 探偵小説作家は、一つの事柄に関して違いに矛盾する二つの陳述を成してはならない。
② 決め手となる事実を、最終頁まで隠しておいてはならない。
③ 読者に対してなんらかの手がかりを与えなければならない。
【探偵クラブ入会の誓い】
盟主 貴殿は、読者に対して、決め手となる手がかりを隠蔽せぬことを厳かに誓うか。
志願者 はい、誓います。
具体例を一つ上げると、推理小説作家は、物語中の《地の文》で絶対に嘘を書いてはいけません。《地の文》というのは、会話や、ある登場人物の思考描写以外の普通の説明的文章のことです。
たとえば、作者が物語の冒頭で、Aという人物は犯人ではないと明言しながら、結末でもしもこの人物を犯人にしたら、読者はどう思うでしょう。「騙された」とか「インチキだ」と憤慨するに違いありません。この時の「騙された」という気持ちは、ミステリーの本来持つ壮快なカタルシスではなく、単なる詐欺にあったような不快なものです。もしも、Aという人物がBという人物になりすまして物語中に顔を出すならば、実はAであったということが最後に納得できるよう、行動や性質、その他の複数の証拠で充分にそれを示唆しておかなくてはなりません。それが、フェアプレイというものなのです。
ディクスン・カーの生んだ名探偵フェル博士の言葉に、『そういった事件が奇妙なように思われるのは、ある一つの事実がしかるべき前後の状況から切り離されてもちだされるからだ』という言葉があります。極論を言えば、推理小説上の犯罪の謎は、真相を知らない犯人以外の人間から見た不完全な――虫食い状態の――物語ということができましょう。その欠落部分を、人間の思考作業である推理や推論で埋めていくのです。それが、探偵や読者に課せられた楽しくも厳しい宿題であるわけです。
したがって、推理小説の謎を語る際には、《視点》ということが非常に重要になります。当然のことながら、犯人側から事件を書いたら謎は存在しないわけですから(倒叙ものは、これを逆手にとった方法ですが)、誰から見たら謎に感じられたか、誰と誰から見たら不思議であったのか、そういった視点を明確に、叙述がふらついてはなりません。そのことを作者はちゃんと把握して、筆致を制御しながらプロットを展開する必要があります。
なお、フェアプレイに直結する問題として、本格推理の中に占める比重の高いトリックの問題があります。紙面の関係で、トリックの役割や扱い方などに関しては、いずれまた詳細に語ることとしますが、これだけはお願いしておきます。
「トリックはできるかぎり前例がなく、独創的なものであってほしい」ということです。これほど数多くの推理小説が世の中に生まれてきたわけですから、完全に新規で、原型となるものを考案するのは難しいかもしれません。ですが、なるべくそれに挑戦してみてほしいのです。前例のないものを生み出そうという意欲、独創的なものを発明しようという熱意――それが、本格推理小説をさらなる高みへと前進させるのですから。
そして、完全な独創は無理でも、一つのトリックに対するバリエーションは豊富に存在します。《死体移動》のトリックが自動車を対照に発明されたとして、それを船や飛行機、ロケットに応用することは可能です。新考案されたトリックは発明者の偉業として尊重されますが、一度でも使われたら、今度は常套手段として万人が使う権利を有するとも私は考えます。この時、前任者の使用した状況や設定をそっくり踏襲すれば、それは単なる盗用にすぎません。しかし、新たな状況や新たな設定、別の方法に変換させれば、それはまったく新しい応用として認知されると考えられます。
トリックに前例があるかないかは、たしかにすべてを点検するわけにはいかないでしょう。しかしながら、古典的名作をできる限り読み進めることで、そのあたりの知識や経験は身に付き、おおよその見極めがつくはずです。また、読者の方も、そこに書かれた作品を読めば、作者の志は何となく解るものです。つまり、読者を馬鹿にしないためにも、読者から馬鹿にされないためにも、推理作家の創作意識は高潔で、自尊的であってほしいものです。
ついでに簡単にですが、あまり良くない推理小説の例も示しておきましょう。応募作では、このようなものは遠慮してください。
富士山の側に一件のコテージが建っている。リビングの窓からは富士山がよく見えている。一晩あけ、宿泊客がその窓のカーテンをあけると、何と富士山が目の前から消えている。消失事件だ! 消失事件だ! と、宿泊客が即座に大騒ぎを始める。
その答えは、コテージの土台には大型モーターが仕掛けられ、建物全体が回転するようにできていた。夜中の内に、建物は一八〇度回転していたのである。
仕掛けそのものは、場合によっては許容できます。しかし、その道行きに問題があります。登場人物や作者が、これを不思議な消失事件だと思うならば、少なくとも、宿泊客が、家の中のすべての窓から外を見てみるとか、外に出て周囲を点検し、それでも、富士山がどこにも見えないということを、作者は読者に対して提示し――信じさせ――なくてはなりません。そうでないと、けっして本格推理小説の謎とは言えないのです。その上で、何らかの仕掛けがあって(それも、最後には手がかりによって看破されること)、富士山が消えたように見えるというのなら合格です。
これは、奇術師の作法である《あらため》と同じことです。奇術師は、右手を開いて観衆に掌に何もないことを示します。次に、左手も開いて、こちらにも種のないことを示します(本当は、種があるのかもしれませんが、巧妙に隠します)。それから、手の中からトランプを次々に出したり、鳩を取り出したりして、まるで魔法のように見せかけるのです。つまり、こうした事前の《あらため》がないと、ちっとも不思議に思えず、驚くことができないのです。
前述のコテージの場合も、常識人なら誰だって、そんなことが起きれば、すぐさま家の周囲を確認するでしょう。こうした当たり前の行動に関しては、言い訳のために認識論も錯覚も持ち出すことは不可です。
プレハブ式の体育倉庫がある。二つの窓は、中から半月錠がしまっていて、ドアには、元から南京錠のかかった留め金がある。南京錠の鍵は、信頼のおける第三者がずっと保管していたにもかかわらず、何故か、体育倉庫の中には死体が転がっていた。
答えは、留め金をドライバーの先などで無理矢理はがし、ドアをあけて死体を体育倉庫に運び込んだ後で、瞬間接着剤でこの留め金を元通りに貼り付けた。
何故、この答えが悪いかと言うと、現在の警察の鑑識活動からすれば、こんなことをした痕跡はただちに見つかってしまうからです。錠前が全部きちんとしまっている。全部の錠前には、誰も変な細工をしたようには見えない。こうした検証が完全にすんだところから、現代の本格推理は始まるのです。その困難を覆すのが、トリックなのです。このことも、先の《あらため》と同じです。可能性を残したところから、本格推理の謎を始めてはいけません。
Aという人物が殺されたが、Bという人物にはアリバイがある。Aのいる所には、デーブ鉄道のお昼ちょうど発の列車に乗っていかなければならないが、その列車に乗ったのでは、Aの死んだ時間までにBはそこへたどり着けない。
答えは、よく時刻表を調べたら、別のトーフ鉄道の特急に乗り、途中からタクシーで行けば、AはBを殺すことが可能であった。
はるか昔のトラベル・ミステリーなら、これでも一つの答えになったでしょうが、今はもうだめです。こうした時刻表の隙間を突くだけの作品は、あまりにありふれてしまいました。複数の鉄道、様々な自動車のルート、飛行機やヘリコプターの活用など、これも一通りの手立てが検討されて、それがすべて否定された後に、本格推理の謎が生じるわけです。それを、誰も考えなかったようなトリックを使い、偽のアリバイをまんまと作り上げるからこそ、読者は感動してくれるのです。
4、推理小説を書くために
《本格推理》の定義など、やや難しいことを述べたかもしれませんが、小説を書く上では、「こうすると良い」という提言はありますが、「こうしなければならない」という狭量な制約はありません。昔は、低俗極まる一部の似非知識人が、「ミステリーは人間が書けてなければならない」とか、「動機が重視されなければならない」とか、「現実的でなければならない」とか、「名探偵が出てきてはいけない」とか、「トリックは不自然だから不必要である」とか、まったく具にもつかないことを平気で言い、作家に強制したりしました。しかし、新本格推理の勃興によって、今はそうした誤解は拭い去られ、足枷は完全に取り払われています。ですから、皆さんは、自由に楽しく、そして野心的に、思う存分、自分の信じるところの本格推理小説を書いてください。
もちろん、前項で述べたように、推理小説の形態としての様式美や、ジャンルとしての特化性は尊重されるべきでしょう。どこまでそれに徹することができるか、究極の状態まで突き詰めることも大歓迎です。しかし、これもけっして強制ではありません。もしも、書き手が、本格のコードや器を叩き壊すことでもっと素晴らしいものが書けると思ったなら、派手に破壊して、定義からもさっさと逸脱すべきです。私はそれを否定しません。
当然、応募作においても、本格推理小説としてのスタイルや文体に制限は設けません。シャーロック・ホームズもののような古典的なスタイルでも良いし、ヴァン・ダインやクイーンやカーのようなオーソドックスな探偵スタイルでもかまいません。文体をハードボイルド形式にしても良いし、横溝正史の『三つ首塔』のようなサスペンス・スタイルにしても良いのです。何も、必ず密室殺人が出てくる必要もありませんし、名探偵が登場する必要だってありません。そういう表面的な形態には、私はこだわりません。ただ絶対に、本格の精神――センス・オブ・ミステリー――だけは忘れないでください。文章や設定から本格推理の発露が感じられない場合には、その作品を『新・本格推理』に採用することはありません。それだけははっきりと、事前にお断わりしておきます。
最後に、新編集長たる私のこの長い挨拶を、ディクスン・カーの最高の言葉で結びたいと思います。本格推理小説の作家を目指すものなら、それが全員の共通した願いだと思うからです。
「私の野心は今もなお真に傑出した推理小説を書くことであるが、いまだに達成したとは正直、思わない。作家がこう述べるとき、その本音は他のすべての推理小説がつまらないものに見えるような傑作をものにしたいということである。無論、それは不可能だ。しかし、いつまでも試みつづけることはできる」
(完)
 戻る |
 表紙 |
