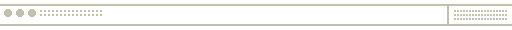
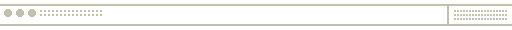
以下の作品は、個人で楽しむ他は、禁複製です。
『高木彬光先生、ありがとうございます!』
高木彬光氏には様々なシリーズ探偵ものがあるが、その中でも一番好きなのが神津恭介ものである。もともと天才探偵が活躍する探偵小説を読むのが大好きなので、快刀乱麻、神のごとき名推理を披露する神津恭介氏の登場にはワクワクする。
好きな作品のベスト3は、『人形はなぜ殺される』『刺青殺人事件』『成吉思汗の秘密』となる。『呪縛の家』や『死を開く扉』、短編の「妖婦の宿」もいい。ようするに、これまた自分の趣味で、密室ものが好きなのだ。と書くと、『人形はなぜ殺される』はアリバイものでは?という人もいるだろう。ところが、箱の中から首が消える奇術ネタは、完全に密室トリックなんですね。どちらにしろ、マネキン人形を列車に轢断させるアリバイ・トリックや犯人の意外性を含め、『人形はなぜ殺される』は、日本の本格推理小説史上のベスト3に入る傑作だと思っている。一生に一度で良いから、私もこのような傑作(物語・トリック・プロットの投守走の三拍子揃ったもの)を書いてみたいものだ。
逆に、あまり感心していない作品は『死神の座』である、高木彬光氏が社会派に移行する時期に書かれたものなので、探偵小説としては完全に気が抜けている。長いけれども密度が薄いという低評価である。
確か、神津恭介ものの長編は十八編あったはずだ。しかし、高木彬光氏の長く濃いキャリアから考えれば、この数は非常に少なすぎる。もっともっと、神津恭介の活躍する小説があってしかるべきだ。これも結局は、社会派の功罪の『罪』の影響であって、我々ミステリー・ファンとしては悲しむべきことだ。
神津恭介もので扱われたトリックに関して、二つほど不満がある。一つは、私が自著『名探偵の肖像』のエッセイでも触れた『魔弾の射手』の足跡トリックの問題(正確にはミスディレクションの不備)、もう一つは、短編「わが一高時代の犯罪」の消失トリックである。高い塔やビルの屋上から人が消えたら、当然、紐やロープを使っての外部脱出が考えられるわけで、それは探偵たちによって事前に検討されねばならない。その可能性が一度否定された後に、何らかのトリックによって目的が達成されるならば良いが、ただ単に紐やロープが脱出の道具として使われたと解明されるのでは芸がない。読者の知能を侮っている。
処女作の『刺青殺人事件』が傑作であることに異論はまったくない。ただ、最初に読んだ時、冒頭が少し長く(密室殺人が起きるまで)、まだるっこく感じられた。その点は、この作品の現行版が後で加筆されたものであると知って納得ができた。描写は丹念にはなったのだろうが、初出にあったような若々しい勢いが失せてしまったに違いない。
また、私は、例の浴室の密室殺人現場における作者の説明にも納得できなかった。浴室から胴体が運び出されていると書いてあったが、私には、浴室へ頭や手足を投げ込んだようにしか思えなかったからだ。これは、単純に質量の問題である。私には、手足などの部位の合計よりも、胴体の方が大きく感じられたのである。高木彬光氏にしても、そうした不満を述べる者がいることを承知して、その対応のために《心理の密室》というロジックを付加したものだろう。
なお、私事になるが、『悪霊の館』という作品は、神津恭介シリーズがなかったら生まれなかったものだ。ファンの皆さんは御承知のとおり、『人形はなぜ殺される』の中で、作者(=松下研三)は、未発表事件『甲冑殺人事件』に触れている。これが、『人形はなぜ殺される』事件に匹敵する大事件だというのだから、ファンとしてはたまらない。当然、読んでみたくなる。私も長い間、この未発表事件はどんな物語だろうかと空想をたくましくし、また、一刻も早く読めることを望んでいた。そうした空想の中から生まれたのが、『悪霊の館』なのである。『甲冑殺人事件』はとうとう書かれなかったが、私としては、高木彬光氏に大いなる感謝を捧げたい。
『ローダンよ、永遠に!』
何故、人間は夜空を見上げたくなるのか。何故、星の輝きに魅せられてしまうのか。何故、ロケットを造って宇宙へ旅立とうとするのか――皆さんは、こうした謎に答えることができるだろうか。また、これらの質問は、次のように変換することもできる。すなわち、宇宙には、我々以外の宇宙人がはたして存在するのだろうか。
実を言えば、どの質問の答えもまったく同じものである。
宇宙には、我々以外の宇宙人はいない。
これが、真実なのである――いいや、もう少し正確に言うと、宇宙には他にも生命を有する惑星は多々あるのだが、我々地球人が、今この瞬間では、一番文明的に進んでいる存在なのだ。ということはつまり、《この広大無辺の宇宙をすべて自分の物にできるぞレース》の最前部にいるのが、我々人類という種であるということなのだ。UFO目撃例などというあやふやなものを別にすれば、未だに地球外文明の痕跡は発見されていないけれども、それも道理なのである。
だから、我々は急いで、宇宙開発や宇宙進出を果たさなくてはならない。そうすれば、いつの日か、必ずや人類が宇宙全体を手中に収めることができるだろう。そしてそれは、一刻を争う過酷な競争でもあるのだ。もしもこのレースで、私たちが少しでも停滞することがあれば、後から成長してきた別の宇宙人たちによって、簡単に追い抜かれてしまうだろう。そうなれば、あの膨大な数の星の世界を彼らに奪われてしまい、我々はこの地球という牢獄に閉じこめられてしまう。それだけは、何としても避けなくてはならない。
私たち人間が星空や宇宙に強く心惹かれるのは、このレースに勝たねばならないという、人類としての本能的な衝動――生存本能や征服欲――なのである。
とは言え、この二十世紀末という現実時間に生きる我々には、まだ恒星間飛行を可能にする科学技術がない。ではどうするかと言えば、科学技術が成熟するまでは、ひたすら精神面を鍛えておくべきなのだ。そのためのシュミレーションとして、『宇宙英雄ペリー・ローダン』シリーズを読むことが最適なのである。我々が宇宙へ進出した時、そこで遭遇する未知や危機にどう対処するべきか、困難をどう切り抜けていくべきか、ローダンが最善の道を指し示してくれる。
――さて、こんな真面目な話はさておき、『ローダン』シリーズという小説である。ドイツ人というのは、時折途轍もないことをしでかす人種だが、SFの分野でも突拍子もないことを始めた。一話一冊完結の週間小説誌として刊行されるリレー型SF小説で、一九六一年より始まり、未だに向こうでも大人気を博している。
日本では、向こうの二冊分を一冊としての文庫版。現在は年十巻という早いペースで刊行されて二百五十巻を数えたが、とうてい追いつくことはできない。それでも、一九七一年の邦訳第一巻刊行から二十八年。早川書房もよくぞここまで出し続けたが、それに付き合ってきた私たち読者も立派だ。主人公たちの不死性に見合うように、これからも未来永劫、この偉業が続いてほしい(ついでに言えば、複数翻訳者制になったのだから、年に三十六巻と、『アトラン』シリーズを十二巻ずつ出してください)
シリーズを最初から振り返ってみると、最初の三巻はさほど面白くなかった。ところが、第四巻以降、太陽系外に舞台が広がり、地球外生命体が出てきた途端、物語は俄然沸騰して、壮快・痛快の極みとなる。トカゲ型のトプシダーは意外に弱かったけれど、ローダンらに不死を与えることになる超生命体の《それ》の不可思議性を含め、スプリンガーを代表とする没落のアルコン帝国の残党など、実に様々な怪物や宇宙人が出てきて、血湧き肉踊る冒険と活劇が主人公と我々読者の前に次々と立ちふさがる。
シリーズ全体で言うならば、非ヒューマノイドが敵である方が話は面白い。ヒューマノイド型宇宙人が敵である場合は――アンドロメダやカピン・サイクルなどがそうだが――個人的にはもう一つ感動が少ない。
たとえば、アンドロメダ・サイクルだが、《島の王》が強権支配、統制する一大銀河という設定は、最初は規模雄大で非常に魅惑的に思った。天の川銀河人類よりも圧倒的な科学力を持つ《島の王》たちと配下のテフローダーらの結束力の前には、ローダンらの勝機はまったくなさそうだった。ホラー惑星という複層構造の星、この人工的な罠の突飛な着想には目を見張ったし、そこからの脱出業には手に汗握るスリルがあった。しかし、話が進むにつれ、《島の王》の正体が単に不死者である数名のヒューマノイドであるという矮小的真相には、いささかがっかりした。神のような、もっと想像を絶する高次の生命体や機構の存在を期待していたからだ。
カピン・サイクルも同じだ。分裂した地球人同士の政治的戦争というどうでもいい話から始まり、新エンジンを使ってせっかく他の島宇宙であるグルエルフィン銀河まではるばる飛んでいったにもかかわらず、カピンの通常の外観が人間とほとんど変わらず(というか、人間自体が、カピンに似せて創られたものだったわけだが)、しかも、精神作用も人間と変わらないので、最後までまったく盛り上がらなかった。
だが、非ヒューマノイドが敵となるサイクル――アルコンのロボット摂政、ドルーフ、ポスビ、ブルー族、けだもの――などは、どれも圧巻、また圧巻である。ドルーフの異世界も不気味だったし、怪物シュレックヴルムやメンタリティの異なるポスビの圧倒的強さにも痺れた。ことに、けだもの・サイクルは、シリーズを通じての白眉で、実に壮絶な物語だったと言える。M―87星雲の中心部の摩訶不思議な情景には目が眩む思いがしたし、結末の怒濤のような展開にも息が詰まった。オールドマンを含めた総当たり的な決戦は数ある戦闘の中でも一番壮烈で、まさに、太陽系帝国絶滅の危機というに相応しい盛り上がりを見せた。
今、『ローダン』シリーズはようやくカピン・サイクルが終わり、新たな冒険――大群サイクル――に入ったところだ。今回の敵は非ヒューマノイドのようなので、私は大いに期待している。
それにしても、『ローダン』シリーズには実にいろいろな見所がある。大星間帝国を背景に縦横無尽に駆けめぐる人類や宇宙人たち。異種生物との壮絶な戦いや異世界での冒険や探検。タイム・トラベルや次元移動、ロボットや超能力、超科学兵器その他の超SF的アイデア――それらが次々と繰り出し、奔流のごとく読者を包む。
だいたい、シリーズ作品というものは、バローズの『火星』シリーズやハミルトンの『キャプテン・フューチャー』シリーズをはじめ、まず主人公の独自性の上に成り立ち、その上で、シリーズが進むにつれて増えてくる脇役たちのキャラクター的な面白みに支えられているものだ。ところが、『ローダン』シリーズではこの側面がかなり希薄である。確かに、グッキーという名脇役がいるが、それ以外はどうだろう。ことに主人公のローダンにはまったく人間的魅力がなく(似たようなケースに、カッスラーの『ダーク・ピッド』シリーズがある。これも、主人公は無色透明である)、むしろ脇役のブリーやアトランの方がずっと光彩を放っている。
何故、ローダンが平凡かと言えば、それは、容貌、性格、行動規範及び思考様式が、人類の代表者としての側面から、非常にニュートラルに設定されているからだろう。《瞬間切り替えスイッチ》などといって、いろいろ個性を与えようとはしているが、結局、ローダンはローダンという個人ではなく、人類という種の象徴なのだ。
そのように認められた時、『ローダン』シリーズ全体の真の姿が浮き彫りになる。これはローダンという個人とローダンの取り巻きが活躍する話ではなく、人類という種全体が、宇宙という広大無辺な舞台を手に入れるために粒々辛苦する物語なのである。
シリーズの創設者の一人、K・H・シェールは、グッキーというある意味であざといキャラクターの導入を嫌ったという。また、もう一人の作者、クラーク・ダールトンは、逆にこのアイデアを推し進めたという。どちらの考えも理解できるし、どちらも正しかろう。人類の物語という本来の意義からすればシェールが正論だし、シリーズを商品と見て人気を勝ち得るためにはダールトンの政策が正しい。今現在の評価としては、その辺のバランスは非常によく取れているということで落ち着こう。
ローダンの面白みの一つであるチーム・ワークの勝利も、この辺の設定から起因している。ローダンやアトランらの司令官グループ。グッキーやマーシャルらのエスパー・グループ。カルプやワリンジャーらの科学者グループ。カソムやレミーら兵士グループ。ある者たちは永遠の生命を持ち、ある者たちは有限の生命を持つ。だが、かれらは己の使命に準拠し、人類の幸福だけを願って宇宙へ飛び立つのだ。
話は少し変わるが、私は、最近のSF小説はあまり好きではない。物語作りが粗雑になり、その貧弱さを糊塗するためにガシェットに頼って表面を繕っている。あるいは、やたらにディテールに凝って饒舌なだけだったりする。一番悪いのは凡庸なハードSFと盲目的なハードSF信仰で、本来SFのSを形成するのは科学アイデアの小説的な料理の仕方であったはずなのに、今や単なる科学事実の引き写しに奔走するはめになっている。科学技術の整合性などは末節的な話で、SFにとって何より大事なのはセンス・オブ・ワンダーの追求だと思うのだが、どうやら完全に目的と手段を取り違えている(それは、リアリズムしか取り柄のない一部のミステリーとよく似ている)。結局、それが可能性の文学であるSFをどんどん袋小路においやり、日本におけるSF小説の人気の下降に繋がっているように思えるのだ。
今のままの有様では、SF小説が新規の読者を獲得・拡大することはとうてい不可能であり、いつまでも『スター・ウォーズ』などのSF映画に負け続けるだろう。たとえ、現時点から見た科学事実に誤認があろうとも、大半のハードSFよりも、ウエルズの『月世界最初の人間』の方がずっと普遍的で面白い。かつて、福島正美が『SFは決して単なる科学啓蒙書ではない』と述べたが、この言葉をもう一度噛みしめてみるべきだ。
では、『ローダン』シリーズを一個のSFとして評価するとどうだろう。SFが本質的にSFらしいのは読者に未来のビジョンや希望を与えることができる小説であることだが、その点においてはまったく過不足ない。宇宙航行技術、タイム・トラベル方法、兵器類、異星人や異世界の有様など実に多彩な科学的アイデアが、後から後から噴出する。しかも、これがまったくの荒唐無稽ばかりかというとそうでもない。意外にも、事実的科学技術に関する面をしっかりと押さえていたりする。各宇宙船の人間工学的成り立ちはもちろんだが、たいそう感心したのが、けだものサイクルの途中で超重力惑星へ行く話であった。ここではクレメントの『重力への挑戦』に出てくるのとよく似た惑星と、超重力下での危険な冒険が詳細に、迫真的に描かれている。これなど、科学事実と科学的空想力のみごとな融合と言えるだろう。だから、ハードSFが好きな者にだって充分に鑑賞に堪えるはずなのだ。
そして、『ローダン』シリーズの数々の魅力の中でも、最大のものが、このシリーズが絶対に終わらない物語であるということだろう。普通の小説ならば、どんなものにも必ず終わりがある。おとぎ話でも、伝説でも、神話でも、テレビ・ドラマでも映画でも、テレビ・ゲームでも、それらがどれほど面白かろうと、どれほど長かろうと、必ず必然的な、あるいは物理的な結末を迎える。話が結末に至ったとか、作者が死んだとかで、悲しくも終わってしまうのだ。
ところが、『ローダン』シリーズは、今のところまったく終わりが見えない。親本であるドイツ版は未だに毎週刊行されているわけだから、それより刊行ペースの遅い日本語版は、当然のことながら中途にある。早川書房がこれを刊行し続けてくれる限り、本国版よりも長く存続することになる。つまり、我々読者は、実質的に永遠に終わらない物語を、この『ローダン』シリーズによって手に入れたことになるのだ。何という贅沢であろう。何という愉悦であろう。何という幸福であろう。これこそ、小説読みの見果てぬ夢の実現ではないか!
最後にもう一度言おう。我々人類は、この素晴らしき『ローダン』シリーズをマニュアルにして、一刻も早い宇宙進出、宇宙制覇を成し遂げなくてはならない。それが、我々人類という生物の種に原始の時より規定された{ルビ
さだめ}運命{/ルビ}なのだから。
『挨拶にかえて』
【非オリエント急行の殺人】
「どうですかな、ムッシュー・ポモロ。二万ドルで私の護衛をしてくださらないかな。それも現金ですぞ」
「何ですって、二万ドル? そんなにたくさん!」
「そうです」
「解りました。あなたをお守りしましょう。ミスター・ラチェット・レンチ。この灰色の脳細胞を持つポモロがあなたの味方となれば、誰もあなたに危害を加えられるはずはありません」
「おお、ありがとう!」
こうして、オリエント急行は、何事もなくカレーに到着した。
【水晶の万里の頂上】
「それで淫羅井、君は、中国の万里の頂上が古代において何に使われたと言うんだ。中国の歴史を振り返れば、あれは、中国の皇帝が夷狄から領土を守るために作った城壁だということははっきりしているじゃないか」
「ワオーン。石井くん、君の目は、どうやら僕の思っている以上の節穴だね。その節穴に、竹の子が生えてきそうだ」
私はいささかムッとして、淫羅井に言った。
「それでは、君のたぐいまれな頭脳で、あの人類史上最大の建造物の使い方を教えてくれ」
「解りきったことさ。あれは水路だよ。てっぺんの部分を、水がずっと流れるのさ」
「水路!」私はクラクラと眩暈がした。「あんなに長い、何万キロもある水路だって!」
「そうさ。こんなのは簡単な推理だ」
「じゃあ、そんなに長い水路を作って、昔の中国人は何をしたんだ」
「まだ解らないのか。いやになるな」
「頼む、教えてくれ、淫羅井」
「スプラッシュ・マウンテンだよ」
【殺人者はキツネ】
「それから、妻は、流しの上のキャビネットの上から自分でグラスを取りました。それに、私はグレープフルーツのジュースをなみなみと一杯注いだのです」
「では、フォックスさん、あなたはそのグラスを水道で洗いましたか。もしくは、あなたの奥さんは、それを水道で洗いましたか」
「何ですって、グイーンさん!」
全員の目に激しいショックが走った。
「だって、そうでしょう、フォックスさん。私はさっき、あなたが自分で取りだしたグラスを洗ったかどうか確認しました。したがって今度は、奥さんも取りだしたグラスを洗ったかどうか、私は確認する必要があります。それが演繹的で、論理的というものです」
「つ、妻は洗いませんでした」
エルリーは後ろにいる警官を振り返った。
「デメキン署長、これで事件は解決ですね。彼女が後から取り出したコップの中に、最初から毒が入っていたのですよ。どうして十六年前の公判で、その点が問題にならなかったのか、たいへん不思議ですね」
【倒錯の葡萄】
私は一仕事終えて葡萄を食べていた。種なし葡萄だ。そこに、私の友人である刑事のジョー・ダンキンが入ってきた。
「スカダー、君を逮捕する!」
「おいおい、急に何を言うんだ!」
「君がギャングの黒人と組んで、ミックルとルルガをスポーツジムの地下で殺害したことを、俺は知っているだ」
「チクショウ!」私は驚いて立ち上がった。「どうして、ばれたんだ湄」
ダンキンは腰から手錠と、もう一つ別の物を取りだした。
「何故ならだ、お前が自分で事件のことを書いたこの九冊目の本を読んだからさ」
【切り裂き魔Ⅱ】
乗杉輪太郎は図書館にでかけた。司書をしている鈴木穂波に呼ばれたからだ。
「君の要請ならば、僕はいつでも駆けつける。それで、今回は何が起こったんだい」
穂波は一冊の単行本を差しだした。グロテスクな表紙の絵を見ただけで、それが推理小説だと解る。
「また切り裂き魔が出たの。この本のあちらこちらが、虫食い算のようにカッターで切られているのよ」
輪太郎はその本を受け取った。頁をめくっみると、穂波の言うとおりの惨事だった。
「電話を借りていいかい?」
輪太郎はピポパとボタンを押した。
「松浦君か? 乗杉輪太郎だ。話がある。すぐに図書館まで来たまえ」
松浦雅人は、うなだれた顔で出頭した。
輪太郎は彼の前に、その本を突きだした。
「これをやったのは君だね」
「そうです、僕です。でも乗杉先生なら、僕の思いつめた気持ちを理解してくださいますよね」
「ああ、解っている」
「この本は至る所に、古今東西の推理小説について、ネタバレに近いことが書いてあるんです。ひどい本ですよ。だから、僕は未読の読者のために、危ない所を切り捨てたんです」
「それは僕も同感だ」と、輪太郎は頷いた。「穂波さん、こんな本は図書館に置かない方がいい。二階堂黎人の『地獄の奇術師』なんて本はね」
【匿名原稿か?】
「よく、解りました。ダンナーさん。これで、すべて解りました」
私はトーマスから賛辞を受け、フッと虚無的に笑った。笑ったことに意味はないが、私立探偵とはそういうものだ。後は、探偵料を受け取ればいい。
「いえ、私は納得できないわ!」
キャサリン・チャタートンが突然叫んだ。
私は彼女の顔を見つめた。
「だって、そうでしょう。もしも、この『ハムラビは目には目を』という原稿が本になって出版された時、著者だとされているウエット・リンドンがそれを読んで、これは自分が書いたものではないと、公に訴え出たらどうなると言うのよ!」
 戻る |
 表紙 |
