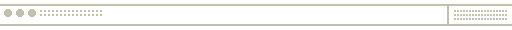
小説
ここには、未発表の小説などが置いてあります。個人で楽しむ他は禁転載です。
[短編]
『素人カースケの華麗な日々』
二階堂黎人
(これは、未発表小説です。なお、登場人物にモデル等はありません。また、特定の意図もありません。あくまでもギャグとして書いたものです。その点、お含みおきの上、お読みください。)
《五月七日金曜日 カースケとミユキが、新宿でデートをする》
1
ミユキこと{ルビ しまむらみゆき}島村美由紀{/ルビ}は、恋人のカースケこと{ルビ
おおちかわすけ}大地河介{/ルビ}と、西武新宿駅の改札口の外側で待ち合わせしていた。
腕時計を見ると、約束の午後三時まであと二分ある。これまでのデートでミユキが遅刻したことはあっても、カースケが遅れてきたことは一度もない。いろいろな面においてオタクっぽい性格がある彼は――そのせいかどうかは解らないが――時間には非常に几帳面である。
案の定、視線を上げた途端に、改札口の向こうにカースケの姿が見えた。着いたばかりの電車から飛び出し、前にいる人々をかき分けるようにして走ってくる。痩せ形で背が高いので、手足がやたらに長く感じる。
「――ごめん、ごめん、ミユキ。遅れたかな」
軽く肩で息をしながら、改札を通り抜けたばかりのカースケが謝った。長い前髪の間から、大きくて愛嬌のある目が覗く。
「ううん。ちょうど三時よ。私も五分前に来たところ」
ミユキは軽く首を振り、ニッコリと微笑んだ。
「そうか、良かった」
カースケも同じように微笑み返す。
ミユキは十八歳で、渋谷にある美容学校の生徒である。カースケは二十歳で、神田にある文系大学の二年生だ。したがって、平日でも時間が合えば、こうしてよくデートをする。また、ゴールデン・ウィークの間は、ミユキが家族と一緒に北海道へ行ってきたので、二人が会うのは久しぶりなのだった。
「ところで、カースケさん。最初にどこへ行くの。夕食までまだずいぶん時間があるわよ。ペペの八階にある本屋さん? それとも、紀伊国屋書店?」
カースケはたいへんな読書家だったから、デートの度に本屋に入りたがる。ミユキは前は雑誌などを見る程度であったが、彼の影響によって、最近はけっこう小説も読むようになった。
「いいや、最初に《ミステリー喫茶》へ行こうと思うんだよ。大学のOBの一人が、地下街のサブナードのすぐ側で、一週間前に新しく店を開いたんだって。それで、顔を出してみようかと思うんだ」
「OBって、やっぱり《ミステリー研究会》の先輩?」
「うん。幻の会長さんの一年後輩でね、影の副会長さんて呼ばれていた人だ」
幻の会長にはミユキも会っている。原宿にある《{ルビ
ブラウン}舞羅運{/ルビ}》という高級《読書ラン》で、《読むリエ》をしている人である。少し前のことだが、二人はその店で、たっぷりと本を堪能してきた。
「影の副会長?」
「そう。ひどく引っ込み思案な人でね、いつも一人っきりで本を読んでいたらしい。だから、いるんだかいないんだか解らず、影みたいに存在感がないということで、そういう渾名が付いたんだそうだ」
「へえ。でも、そんな人が、接客業を始めて大丈夫なの?」
「《ミステリー喫茶》なんて、《マンガ喫茶》と同じで、本さえ揃えておけば平気なんだろう。飲み物を出したら、後はお客が勝手に時間まで読書しているだけだもの」
「そう言えばそうね」
ミユキは納得して頷く。
「じゃあ、行こう」
二人は手を握って歩きだした。地下道へ繋がる一番近い階段に向かい、ファッショナブルな商店が並ぶサブナードへ入る。途中にも、新装開店したばかりの《マンガ喫茶》があり、立て看板が出ていた。
「ねえ、カースケさん。何だかこの頃、喫茶店と言えば《マンガ喫茶》ばかりよね」
「そうだね。ずいぶん増えたね。五百円程度でワン・ドリンク付いて、好きなマンガが読めるんだから、僕らみたいな若者にはありがたいシステムさ。ただし、そうして人にマンガを読ませてお金を取っている以上、営利的な観点から言えば、著作権上の問題も発生しているみたいだ。カラオケだって、著作権者にお金を払っているわけだし」
「私、まだ《ミステリー喫茶》には入ったことがないわ」
「システムは《マンガ喫茶》と同じだよ。《ミステリー喫茶》の方もだいぶ流行ってきたらしいよ。銀座の三越デパートのあたりにも、いっぺんに三軒の店ができたって、昨日の夕方のニュースで言っていたから」
「新宿は?」
「僕の知っているかぎりでは、西口には四軒あるな。南口と東口には、これから行く店を入れて六軒かな」
「まあ、ずいぶんあるのね」
「そりゃそうだよ。今や、ミステリーは、小説の中心的存在に成長して、エンターテイメントと同義語になりつつある。特に新本格推理は大人気で、知性と稚気がある若者たちのトレンドだ。インターネットを見てごらんよ。その系統のホームページがわんさかあるから。キーワードを作家の綾辻行人や京極夏彦にして検索を実行してごらん。何千というヒットがあるよ」
「そうね」
「もしかしたらその内、《マンガ喫茶》はみんな《ミステリー喫茶》になってしまうかもしれないな」
カースケは嬉しそうな声で、期待感たっぷりに言う。ミユキはそんなことはあるまいと思ったが、黙って頷いておいた。
「ところで、カースケさん。これから行くお店の名前は?」
「《マボロシ倶楽部》。場所は伊勢丹デパートの横だよ」
二人はサブナードを抜け、営団地下鉄駅などがある地下道へ入った。紀伊国屋書店や丸井デパートの横を通ると、ほどなく、その《ミステリー喫茶》の看板が見えた。
狭い入り口である。木製のドアにはトカゲの文様の盾と、フェンシングの剣が打ち付けられていて、少しおどろおどろしい雰囲気が醸し出されていた。カースケがドアを押し開けると、チャリンと鈴の音がする。そして、古書特有のやや黴びた匂いが、冷たい空気と共にミユキの鼻孔をくすぐった。
「……いらっしゃいませ……」
か細い声が、すぐ左手のカウンターの中から聞こえた。そして、横手から白いシャツと黒いチョッキを着た、ひどく痩せこけた男性が顔を出した。目は落ちくぼみ、頬はこけていて、まるで骸骨が洋服を着ているような風情である。
ミユキはちょっとびっくりして、カースケの後ろに隠れる。
「……お二人でございますかあ……」
男は濁った目と、覇気のない声で言う。
カースケも、少し気圧されたように、
「あ、どうも、こんにちは。あのう、筋川さんはいらっしゃいますか」
「……私が、筋川ですがあ。店長ですよお……」
「し、失礼しました。僕は《ミステリー研究会》の後輩で、大地河介、カースケと言います。幻の会長さんにこちらを教えていただき、今日は本を読ませていただこうと思いまして、やって来ました」
「……そうですかあ。ありがとうございます。ごゆるりとどうぞう。お一人様五百円でワン・ドリンク付きです。制限時間は一時間ですが、後輩ならば、時間無制限でいいですよう……」
「それはありがとうございます」
カースケは二人分の代金を払い、コーヒーを頼んで、奥へ進んだ。
店内は意外に広く、四人がけのテーブルが十二台あった。三方の壁がすべて造り付けの書棚になっていて、ぎっしりと小説が詰まっている。若い男女の客が十人ほどいて、皆、一心不乱に本を読んでいる。ざっと見たところ、講談社ノベルスを読んでいる者が多いようだ。
二人が本棚を眺めながら席に着くと、店長が良い香りのするコーヒーとおしぼりを持ってきた。
「……左の壁が絶版本、奥の壁が文庫本、右の壁が単行本やノベルスです。お好きな本を選んで読んでくださあい……」
「はい。解りました」カースケが頷く。「新刊もあるんですか」
「ありますよう……」そう返事をした店長は、顔をゆっくりと二人に近づけ、小声で囁く。「……実はですねえ、今月十日に発売になる新しい講談社ノベルスが、たった今、入荷したところなんですよお……どうしますかあ。読みますかあ……」
「それは凄い!」と、カースケが目を光らせる。「有栖川有栖の『ペルシャ猫の謎』や、法月綸太郎の『法月綸太郎の新冒険』が、もう読めると言うんですか!」
「……それに、今月は、高田崇史の『QED 六歌仙の暗号』とか、物集高音の『血食』といった新人の作品も、あるんですよお。どれにしますかあ……」
「す、すみません。それ、全部見せていただくわけにはいきませんか!」
カースケは興奮して頼んだ。
「……いいですよお……ちょっと待ってください……」
店長はぼんやりとした声で言い、奥へ引っ込んだ。少しすると、銀の盆に、今月発売になる講談社ノベルスを六冊積み上げて持ってきた。
「……さあ、どうぞお……」
カースケは目を丸くしてそれらを受け取ると、高ぶった声で尋ねた。
「でも、店長。どうして、まだ書店に並んでいない本がここにあるんです!?」
すると、店長は低く、不気味な声で含み笑った。
「……ふふふふふ……ふふふふふ……ふふふふふ……」
「教えてください!」
「……ふふふふふ……それはですねえ……ふふふふふ……」
「お願いですから!」
「……ふふふふふ……この業界には、見本刷りをこっそり手に入れる、秘密の裏ルートがあるんですよお……」
「本当ですか!」
「……まあねえ……でも、他人には内緒にしてくださいねえ。私も、だてに、《ミステリー研究会》の副部長をしていたわけではありません。先輩、後輩には、出版業界に就職をした人がたくさんいますからねえ。そうした人の{ルビ
つて}伝{/ルビ}をたどれば、新刊を少しだけ早く手に入れることなど、わりと簡単なんですよお……ただし、取次に知れると問題が起きますからねえ、君たちも、秘密は守ってくださいよお……」
「ええ、もちろんです。ありがとうございます!」
カースケは体全体で喜びを表わし、店長に感謝した。
さっそく二人は、その新刊を読み始める。カースケは悩んだ末に『法月綸太郎の新冒険』に手を出した。帯の『全編これぞ本格!』という威勢の良い惹句が気に入ったからだ。ミユキの方は、赤川次郎の『三姉妹探偵団』を選んだ。
二時間近く、二人は本を読んでいた。途中で、店長がサービスのオレンジ・ジュースを持ってきてくれた。
「――あら、もう六時を過ぎているわ」だいぶしてから、ミユキが腕時計を見て言った。「時間が経つのって早いわね」
カースケも本を閉じて、自分の腕時計を確認した。
「本当だ。そう言えば、お腹が空いてきたな。食事に行こうか」
「何か奢ってくれるの、カースケさん?」
「それが、あまりお金がないから、ラーメンでもいいかな」
カースケが情けなさそうな顔をする。
「仕方ないわね」と、ミユキが苦笑する。「カースケさんが金欠なのはいつものことだから、それで許してあげる」
と、二人が幸福そうな顔を見合わせた時だった。いつの間にか、店長が二人の横に立っていて、
「……あのう……」
と、消え入るような声をかけてきたのである。
「あ、びっくりした!」と、カースケは椅子の上で飛び上がりそうになった。「な、何ですか。店長さん?」
「……失礼ですけどお、カースケ君は、お金に困っているんですかあ……」
「え、ええ……」
と、カースケが何と言って良いか窮していると、横からミユキが口を挟んだ。
「はい。店長さん。そうなんです。カースケさんは苦学生なんです。アルバイトをしながら大学へ行っているので、いつもお金が足りない状態なんです。だから、私たちって貧乏なんですわ」
店長はぼんやりと頷くと、
「……解りましたあ。じゃあ、良かったら、私が夕食を御馳走しましょう。近くに、おいしいステーキを食べさせるレストランがあるんですよお……」
カースケはミユキを睨む真似をしてから、
「それは嬉しいですけど、でも、店長にそこまで甘えてしまうわけにはいきません」
「……いいえ。遠慮には及びません。ただし、こちらも、お二人にお願いしたいことがあるんですう。その話を聞いていただくために、食事に誘っているわけですからあ……」
「願い――と言いますと?」
「……お二人は、流行ミステリー作家の{ルビ
ぞんざいしごろう}存財四五郎{/ルビ}を知ってますかあ……」
「存財ですか」と、カースケは戸惑いながら、「ええ。もちろん知ってますよ。文芸雑誌に連載を七本も八本も持っていて、年に単行本を十数冊出している売れっ子作家ですよね。まあ、内容の方は、テレビの二時間ミステリー・ドラマと大差ないと言うか、その原作にしかならないような物ばかりみたいですけど」
「……そうですう。その存財先生ですう……」
「それが何か」
「……実はですねえ、私の弟が、存財先生の所で、チーフ・アシスタントをしているんですよお。ところが、最近、二人のアシスタントが急にやめてしまったんで、パートでもいいから、代わりの人材を捜しているんですう。良かったら、そこを手伝ってくれませんかねえ。アルバイト料の方もけっこう出ますよお。一時間五千円以上はくれると思いますからあ……」
「本当ですか――でも、僕、小説家のアシスタントなんてしたことがありませんよ」
「……大丈夫ですよお。アシスタントのアシスタントですからね。ただし、少しはミステリーの知識がないと困るので、君のように、《ミステリー研究会》か何かに入っている人を捜していたんですう。とりあえず、明日と明後日、土曜と日曜が今やっている仕事の山場なんで、この二日間だけでも手伝ってもらえませんかねえ……」
カースケは、頭の中で素早くアルバイト料を見積もった。
「――解りました。やらせていただきます」
「……そうですかあ。ありがとう。では、明日の朝、この住所の所へ行ってください。話は私がつけておきますう。準備も何もいりませんからあ……」
店長は、存財四五郎の住所と電話番号を書いたメモをカースケに渡した。それから、二人に、近くにあるレストランの場所を教えてくれた。そこは、目の前で肉を焼いてくれるような本格的なステーキ・レストランであった。カースケたちは遠慮なく、腹一杯になるまで食事を堪能した。
2
「――やっぱり、持つべきものは、大学の先輩だなあ」
と、新宿からの帰り道、西武新宿線の小平駅から自分のアパートへ向かう道すがら、カースケは膨れたお腹を撫でながら言った。優しい夜風が、何とも言えず気持ちが良い。
肩を寄せ合って歩くミユキは、
「何だか、得しちゃったわね」と、頷き、「小説家のアシスタントって、何をするのかしら。マンガのアシスタントなら、私の友達にやっている人がいるわよ。鉛筆で書いた線に消しゴムをかけて消したり、コマと呼ばれる枠線をロットリング・ペンで引いたり、スクリーン・トーンを貼ったり、髪の毛の黒い所なんかのベタ塗りをするんですって」
「まあ、行ってみれば解るさ」
と、カースケは楽天的に言う。それから、
「ミユキ。今夜は僕のうちに泊まってくかい」
と、期待を込めて尋ねる。
「もちろん」と、ミユキは微笑み、もっと彼の二の腕にしがみつく。「今日はサチコの家に泊まるって、親に嘘をついてきちゃったから大丈夫よ」
サチコというのは、彼女の親友の、{ルビ
いいやまさちこ}飯山幸子{/ルビ}のことだ。
「あ、しまった!」
と、突然、カースケが素っ頓狂な声を上げる。
「どうしたの?」
「今日は金曜日だろう。十一時から、テレビで《燃えるミステリーの達人》をやるんだよ。早く家へ帰らなくちゃ。どうしても見たいんだ!」
カースケは、街路灯の明かりで腕時計の針を確認する。十一時まで、あと五分しかない。
「《燃えるミステリーの達人》って?」
ミユキは、彼の顔を見上げて尋ねる。彼女は小柄なので、頭の先が、彼の首のあたりまでしか来ない。
「あれ、知らないの。四月から始まった番組でね、すごく面白いんだよ。けっこう視聴率も良いそうだしね。ミステリー作家二人が、スタジオで対決する生番組なんだ――あ、そんなことを言っている暇はない。始まっちゃう。アパートまで走るよ、いいね!」
言うが早いか、カースケはもう駆けだしていた。
「あ、待ってよ! カースケさん!」
ミユキもあわててその後を追う。
二人が、アパートの一室に飛び込んだのが、午後十一時ちょうどだった。カースケは肩で息をしながら、真っ先にテレビのスイッチを入れた。
「良かったあ! 間に合った!」
ちょうどコマーシャルが終わり、番組のオープニングが流れた。そして、プロレスのアナウンサーみたいに大袈裟なしゃべり方をするナンジャモンジャ{ルビ
いいずか}飯塚{/ルビ}という名前の司会者が、番組の概要を説明し、今日対決する二人のミステリー作家を紹介したのである。
「赤コーナー! ハードボイルド作家の{ルビ
ぎんやまりきむね}銀山力宗{/ルビ}先生! 九十八キログラム!」
名前を呼ばれたのは、短髪に髭を生やした中年の男性だった。ボディビルで体を鍛えているのか、真っ白いTシャツの下で、分厚い胸やごつい腕がはち切れそうになっている。
「青コーナー! 本格推理作家の{ルビ りゅうぜんじこうすけ}竜禅寺幸典{/ルビ} 六十二キログラム!」
こちらは、どこか陰のある顔をした、ちょっと病的な感じがする、憂い顔の若い男性だった。中肉中背で、黒いスーツを着ていた。
「おお! これはたいした対決だぞ!」
正座をして、食い入るようにブラウン管を見つめるカースケが大声を上げ、拍手する。部屋は六畳一間と狭く、ベッドとテレビと衣装ケース、そして、本棚でぎっしり埋まっている。座るにも、畳の上に積み上げてある本や雑誌をどかさねばならない。
ミユキはそんな彼の態度に半分あきれながら、小さな台所にあるガス台に火を点ける。薬缶に水を入れて、その上にのせた。
「ミユキ。この二人の作家を知っているかい?」
「竜禅寺っていう人は、名前を聞いたことがあるわ。銀山っていう人は知らない」
ミユキは、カースケの横に座りながら言う。それに答えるように、司会の飯塚が、二人の作家の最近の仕事を紹介する。
「――銀山先生の最新作は、珍文社から先週刊行されたばかりの、『腕ずくでかかってこい!』ですね。これは、どういう内容ですか」
するとすかさず、
「題名の通りだ!」と、銀山は太い葉巻きを口にくわえながら吠える。「心に傷を持つ一匹狼の酔いどれ私立探偵が、千葉の港町を牛耳るホンコン・マフィアに戦いを挑むというすげえ話しさ! くやしかったら、読んでみろってんだい!」
「別にくやしくはありませんが、売れ行きはいかがですか」
「絶好調さ。もう三刷りだ。ちなみに、俺も絶好調だあ!」
銀山は、両腕に力瘤を作ってみせた。
「そうですか。では、試合の方を頑張ってください」
と、飯塚は言い、今度は、椅子にじっと座って足元を見つめている竜禅寺に対して、インタビューを開始した。
「竜禅寺先生の新刊を紹介していただけますか」
若い小説家は遠い目をして、青白い顔を少し上げると、
「私の新刊は、先月奇譚社から出た、ノベルスの『螺旋の館の悲劇』です……潮騒の音が聞こえる」
と、小声で返事をした。
「――そっかあ!」と、ミユキが手を打った。「この前、カースケさんが読んでいて、面白かったと言ってた本の作者ね」
「そう。新本格推理の期待の星だよ。去年、『瓦礫の館の悲劇』でデビューした人さ。何でも自殺願望があったんだけど、遺書代わりに書いた小説を出版社へ送ったところ、採用されて本になったんだそうだ。それで、彼はまだ生きているんだって、この前、どこかの雑誌のインタビューで答えていたな」
カースケは浮き浮きした声で答えた。
司会の飯塚は、マイクをもっと竜禅寺に近づけて質問する。
「『螺旋の館の悲劇』ですか。面白そうな題名ですね。どんな内容ですか」
「……そう……螺旋型をした館で、恐ろしい悲劇が起きるんです」
「なるほど。それは複雑で、淫靡で、耽美で、奇怪極まりない物語ですね。ぜひ、私も読ませていただきましょう――ところで、今日の対決の意気込みなどをお聞かせください」
「儚い命ですが、全力を尽くしましょう……私など、腕力では銀山先生に勝てそうにないので、知力で勝負したいと思います」
「そうですか、頑張ってください」
ミユキはカースケに尋ねた。
「どんな対決をするの?」
「いろいろな小説の素材や資料が、スタジオ中央にある大テーブルの上に用意される。その素材を使って、それぞれの作家が、制限時間内に短編小説を書き上げるんだよ。そして、その小説を審査員に読ませて、勝敗を決めるんだ」
「まあ、たいへんそうね」
「ああ。時間が短いからたいへんだよ。それに、毎週、課題となる素材が違うんだ」
「今日は何?」
「まあ、見ててごらん――」
「――さて、本日の課題が明らかになります!」
と、司会の飯塚が声を張り上げ、後ろにある大きな電光掲示板を指さした。幾何学模様が様々に変化し、奇妙な電子音と共に、それが一つの単語となった。
「今日の課題は――《毒物》――でえす!」
飯塚の宣言。
巻き起こる盛大な叫声と拍手。スタジオのどこかに観衆がいるか、単に音を被せているかのどちらかである。
「お二人の作家の方には、《毒物》を題材として、これから三十分の間に、原稿用紙二十枚以下の短編を書いてもらいまーす!」
またもや、盛大な叫声と拍手。
「これを御覧ください!」
飯塚は、今度は中央の大テーブルを指さす。スポットライトがそこを照らし、様々な品物を浮き上がらせる。ラジオやCDウォークマンのようなオーディオ品。トースターやコーヒー・メーカーのような家電品。山になった男女の洋服。メガネや腕時計、首飾りなどの装飾品。文房具から本、ノート・パソコンから猫のエサまで――とにかく、ありとあらゆる物がある。まるでリサイクル・ショップの店先のようだった。
「お二人の作家の方には、ここにある品物を最低一つは小説中に取り込んでもらい、お話を作っていただきます。そして、今日は必ず、《毒物》を題材にしてもらわなければなりません。《毒物》の種類は――」と、飯塚がテーブルの前の方にある金庫をあけると、「――そうです。青酸カリです。それから、砒素もあります。この二つの毒物なら、どのように料理してもらってもかまいません!」
彼は、中からドクロ・マークの描かれた小瓶を二つ取り出した。
観衆はまた、拍手と叫声と口笛の音を立てた。
「さて、それでは、できあがった短編小説を読んで、優劣を判断してくださる審査員の先生方を紹介いたしまーす!」
飯塚は、画面に向かって左の方へ腕を差し出した。カメラがすかさずそちらを映す。銀色のモールで飾られたドアがあり、そこから、三人のタキシードを着て正装した男性が出てきた。飯塚が、ステージ中央にやってくる一人一人を、大声で紹介する。
「最初の方は、ミステリー評論歴五十年という{ルビ
たてかわまさみち}館川正道{/ルビ}先生です。次の方は、冒険小説応援団一筋十五年という{ルビ
わだやまけん}和田山剣{/ルビ}先生。そして、最後の方は、ミステリー業界の御意見番、{ルビ
ごうとくかんのすけ}豪徳完之介{/ルビ}先生でえええす!」
「まあ!」と、ミユキがテレビを指さし、驚きの声を上げた。「ねえ、カースケさん。あの人、この前、《{ルビ
ぶらうん}舞羅運{/ルビ}》という《読書ラン》へ来た、あの高慢チキな評論家じゃないの!」
「うん。そうだよ。あの豪徳氏だな」
カースケは顔をしかめる。ゴキブリを見たような表情だ。
「へえ、あの人、こんな番組にも出ているんだ」と、ミユキは憤慨半分、感心半分で言う。「だけど、あんなデタラメな考えしか持っていない評論家に批評されるなんて、対決する二人の作家も可哀想ね」
「ははは。そうだね」と、カースケは意味ありげに言い、「でも実はね、この対決の判定は、あの三人の批評家が誉めた方が負けっていう見方もあるんだよ」
「え?」
「解らないかな。つまり、僕らの《ミステリー研究会》では、あの三人は、普段からトンチンカンな批評ばかりしている悪い評論家の代表と見なしているのさ。普段、つまらない印象書評を書きなぐっていたり、小説を読みもしないで推薦文を書いたり、解説と言ってもあらすじばかりのダメ評論家ばかりだからね。先生、先生と持ち上げられて、審査員席に座るだけで充分に虚栄心を満足させられているんだろう。
それで、彼らが選んだ方の小説が本当は駄目な小説であり、敗者なのだと、僕たち仲間内では判断することにしているんだ。つまり、反面教師なんだね。得票の少なかった方が、僕ら的には優勝なのさ」
「ひっどーい」
と言ったが、ミユキの顔は嬉しそうである。そして、お湯が沸いたので、彼女はインスタント・コーヒーを淹れるために立ち上がった。
テレビの中では、派手なファンファーレが鳴り、いよいよ試合が始まった。ハードボイルド作家の銀山は力強い動作で、いきなり、テーブルの上にある品物を両手にかかえ、それを、自分の書き物机の方へ運び出した。
司会の飯塚が甲高い声で、その模様をレポートする。
「おおっと! 銀山先生は力ずくであります。品物を吟味せず、手当たりしだいに自分の領地へ持っていってしまいます。銀山先生! そんな簡単な選択でいいんですかあ!」
「いいんだよ!」と、銀山は吐いて捨てるように言う。「これが俺のやり方なんだ。小説を書くってのはな、スポーツなんだよ。汗がもたらすインスピレーションなんだ。筋肉がピクピク動いて話を盛り上げるんだ。だから、どんな題材だって、後から適当に当てはめりゃあいいんだ! お前はよけいなことを言うな!」
「は、はい。申し訳ありません! ところで、先生は、ワープロはお使いにならないのですか」
「当たり前だ! あんな物を使って、冒険小説や男の物語が書けるか! 軟弱な! お前、それでも体育会系人間か!」
「いいえ。すみません。私は高校の時、地理クラブに入っておりまして、文系なものですから――ところで、毒物は、青酸カリを使いますか、砒素を使いますか」
「馬鹿野郎。ハードボイルドな俺が使うのは、はなからハジキに決まってるだろう! 拳銃だよ、拳銃!」
「申し訳ありません。今日の課題は毒物でありまして、拳銃はスタジオには持ってきてないんです」
「だったら、凶器は俺の拳だ。見ろ! この火山岩のようにゴツゴツしたゲンコツを――解ったよ。さっさと毒薬の小瓶を寄越せ。それを思いっきり、被害者のおでこにぶつけて殺してやる!」
「はい、コーヒー」と、ミユキがカースケにカップを渡した。「ねえ、カースケさんは、どっちが勝つと思う?」
「さあ、解らないな。ベテラン対新人だけど、書いているジャンルが違うから、結果は予想できないよ」
カースケは、画面から目を離さずに答える。
「でも、ハードボイルドが好きな評論家が多いみたいよ」
「そうだね。彼らはみんな、作品の批評よりも、作家や体制にこびることに熱心な者ばかりだな――」
テレビ・カメラが切り替わり、素材選びをする竜禅寺を映す。若い作家は腕組みして斜に構え、じっくりとテーブルの上にある物品を吟味している。その内に、二つか三つの品物を選び出し、ゆっくりと、それを自分の書き物机の方へ運んだ。そこには、彼の執筆道具である富士通のオアシスというワープロ・マシンと、すでに選択してあった砒素の小瓶がのっていた。
司会の顔がアップになり、
「――竜禅寺先生は、ベネチア・グラスの花瓶と、ミッキーマウスの目覚まし時計と、丸い缶に入った越後の水飴をお選びになりましたあ!」
と、紹介した。そして、椅子に座った作家にマイクを向けると、
「竜禅寺先生。作品の題名などは、もうお決まりになりましたか」
と、尋ねた。
気怠い態度でワープロの電源を入れた竜禅寺は、物憂げに振り返った。慎重な答えが返ってくる。
「いいえ。仮題だけです。作品番号ヘ長調の二番。本当の題名は、作品を書き上げた時に付けます。それが、僕の常のスタイルなのですよ」
「銀山先生に勝てるとお思いですか」
「……さあ、解りません。しかし、全力は尽くします。それが、全国にいる僕のファンの方々へお約束できる最小限のことです……愛しているよ、君たち……」
竜禅寺はカメラに向かって流し目をくれた。
「――あ、見て。銀山先生はもう書き始めているわ!」
と、ミユキが興奮して言う。
「ああ、たいした早さだね」
と、カースケも感心して頷く。
実際、四百字詰め原稿用紙に、モンブランの万年筆で文字を書き込んでいく銀山の早さは、目にも止まらぬものがあった。一枚を書き上げるのに、一分もかからない。その代わり、字はミミズがのたくったようで、とても判読できるものではなかった。
テレビ・カメラは、小説を書くのに熱中する二人の作家を交互に映す。その合間に、司会の飯塚が、解説者と共に、二人の書く小説の内容を吟味し始めた。
「――今週も、ミステリー対決の解説は、《服部ミステリー学院》の院長であらせられる{ルビ
はっとりくんぞう}服部勲蔵{/ルビ}さんに頼みました。どうぞ、よろしくお願いします」
「よろしく」
「銀山先生は、ものすごい執筆速度ですね」
「ええ。彼の場合、書くのも早いですけど、推敲もいっさいしない主義なんですね。もう全身全霊で書きなぐるわけです。できあがった原稿は、彼専属の編集者がいて、あの速記のような他人には解りにくい文字を判読して、普通の読める文字に置き換えます。したがって、短編を書き上げるのは竜禅寺先生よりも先になるでしょうが、その必要時間を加味しなくてはなりません。たぶん、制限時間ギリギリになるでしょう」
「そうですか。一方、竜禅寺先生ですが、ずいぶんゆっくりとお書きですね。親指シフト・キーボードで、あんなに遅く書く人は初めて見ました」
「彼は、一言一句を大切にする人なんですよ。昔の純文学作家のようなスタイルですね。何だか、後ろ姿が芥川龍之介に似ていると思いませんか」
「私は太宰治に似ていると思います」
「それに、ピアニストがコンチェルトを弾くかのように優雅な手つきですね」
「――おおっと! 銀山先生が、今、コーヒー・メーカーを原稿用紙の横に置き、それを見つめながら書いています。コーヒー・メーカーを、どういう風に物語の中で活用するつもりでしょう」
「私ならば、コーヒーに今週の課題である砒素を入れますから、コーヒー・メーカーでコーヒーを作る場面を主人公に演じさせます。しかし、銀山先生のことですから、女主人公が、あのコーヒー・メーカーで、憎い元恋人の男性の頭を殴るんじゃないでしょうか」
「なるほど。そんな気がしますね。ちょっと、銀山先生に訊いてみましょう――銀山先生。そのコーヒー・メーカーは何にお使いですか」
「馬鹿野郎! 書き上げた原稿の上にのせているんだよ。文鎮代わりだ! 余計なことを言うんじゃねえ!」
「そうですか。失礼しました――いやあ、服部先生。また、我々、間違っちゃったみたいですよ!」
カースケは長い前髪をかき上げ、ゲラゲラ笑うと、
「この服部先生。いつも予想がはずれるんだよな。きっと、わざと視聴者受けを狙っているんだろうな」
「わざとなの? 本当に勘違いしているんじゃない。あんなんで、よく《ミステリー学院》の院長が務まるわね」
と、ミユキも愉快がる。
そして、いよいよ制限時間となり、執筆終了を告げる派手なファンファーレが鳴った。
「タイム・アップでえええす!」と、飯塚が絶叫する。「銀山先生、竜禅寺先生、お疲れ様でしたあああ!」
観衆が湧き上がる。手を止めた二人の作家の顔がアップになる。どちらも額に汗して、疲労感が浮かんでいる。
「さあ、それでは、お二人の書かれた短編小説を、評論家の方々に審査してい読んでいただきます。その間、しばらくお時間をちょうだいします。コマーシャルを十五分間お楽しみください」
「そんなにコマーシャルが長いの?」
と、ミユキが口を尖らせる。
「仕方ないさ」と、カースケは肩をすくめた。「評論家が実際に二つの短編を読んで、優劣を決めるんだから」
「あ、だったら、ちょっとチャンネルを変えてもいい?」
「何かあるのかい」
「ええ。この時間は、時々、テレビ・ショッピングを見ているのよ」
「何だ、通販か」
カースケがあきれように言うと、
「けっこう面白いのよ。《ワクワク・テレビ・ショッピング》っていう番組なの」
そう言ったミユキはリモコンを取り上げ、別の局のボタンを押した。
すると、こちらの番組ではちょうど、アメリカ製のエクササイズ・マシンを視聴者に向けて宣伝しているところであった。男性の局アナの他、{ルビ
たからがわあきら}宝川晶{/ルビ}という映画俳優、チェリー・オングという女優が司会者となって、商品の特徴が紹介される度に、わざとらしい驚きの声を上げるのである。
「――どうですか。このエクササイズ・マシン。日本の狭い住宅事情にはまったく合わないバカでかい大きさ! そして、外でマラソンをした方がよほど爽やかで経済的! いい年こいた大人がブランコでも漕いでいるような滑稽な動作! 何もかもが革新的です!」
局アナが身振り手振りでその健康器具をアピールすると、目を皿のように大きくしたチェリー・オングが、
「まあ、すばらしいざんすわね。こんなみごとなエクササイズ・マシンは見たことがありませんわ。一人でも組み立てられるんですの?」
「ええ。そこが、このマシンの素晴らしい特徴です。一人でも組み立てられるんですが、部品一つ一つがとても重いので、それを繋ぎ合わせることが、筋肉を鍛える行為にもなるんです。しかも、組み上がるまでは、どんなに頑張っても三時間かかります。つまり、知らず知らずの間に、三時間も体を動かしてしまうんですね」
「ということは、片づける時間を入れると、六時間も運動をしてしまうわけなのか」
と、かつてハンサムで鳴らした宝川晶が目を丸くして言う。
「そういうことでえす!」
「おお!」
と、こちらの番組でも、観客席にいる人々――ほとんど、暇を持て余している中年の主婦たち――がわざとらしい歓声と拍手を巻き起こした。
マシンの値段と、申し込み用の電話番号が告げられ、次の商品に移った。司会者が、新しい登場人物をまず紹介する。
「――それでは、本日のメイン・イベントです。今度の品物をお持ちくださったのは、オール・ジャパン・テレビ通販株式会社の社長、{ルビ
とかしきただし}渡嘉敷正{/ルビ}さんでえーす」
「こんにちは。こんなに安くて恐縮です」
顔を見せたのは、固太りの不動産ブローカーのような中年男性だった。胡散臭い雰囲気が漂うが、表情はあくまでもにこやかである。
「どれほどお安いんですか」
「その前に、商品をお見せしましょう」
「今日は何ですか」
「ジャーン!」と、渡嘉敷社長が、ジェラルミンのスーツケースを取り出し、テーブルの上に置く。「これでなのです!」
「スーツケースですか。ずいぶん立派な物ですね」
「違います。恐縮です。この中に、本日の特売品が入っているんです」
「そうですか。私も、きっとそうではないかと思いました」
「あけましょう。中身を御覧になれば、皆さん、今日は本当に驚かれると思いますよ」
渡嘉敷社長はわざわざ鍵を取り出し、スーツケースの錠前をあけた。そして、蓋をゆっくりと開き、中身が観客やテレビの視聴者に見えるように、ぐるりと回した。
中に入っていたのは、二冊の分厚い本であった。
「おお!」と、感動の声を上げた司会者は、顔をグッとこの本に近づけ、「渡嘉敷社長。これは何の本ですか。ぜひ、内容を詳しく紹介してください」
「解りましたあ! この二冊の本は、本格ミステリー界の重鎮、島田荘司氏の最新作、カッパノベルスの『涙流れるままに』上下巻です! しかも、実はこの本、来月、六月二十五日にならないと書店には並ばないものなのです。それを、今日は私どもが特別に入手し、まったく恐縮なんですが、限定五十セットということで、ここにわざわざ持ってきましたあ!」
「何と!」「おお!」「すごい!」「まあ!」「嘘でしょう!」
と、司会者陣や観客が揃って驚愕の声を立てた。
「だって」と、チェリー・オングが悲鳴のような声を出す。「今日はまだ五月の七日ですのよ。それって、本当は、六月の二十五日までは売れないのではありませんの!?」
「そうです。ですから、今日、テレビを御覧の皆さんは幸運なんです。一月以上も早く、この夏最高の話題作が読めるんですから!」
「信じられないわ! 夢みたい!」
「待ってください、渡嘉敷社長」と、宝川晶が横から口を挟んだ。「そんな本を、ここで売っていいんですか」
「ええ。だから、恐縮なんです。巷の本屋さんには悪いんですが、私どもが独自のルートで入手してしまって、しかも、直販ができるので、こんなに早く売ってしまうわけなんですねえ!」
「どうやって手に入れたのですか。ここだけの話、こっそり教えてください。渡嘉敷社長」
「――そうですね。じゃあ、ちょっとだけ、秘密をお話しましょう。作者の島田荘司氏は、最近は、アメリカのロサンジェルスに住んでいるんです。ですから、向こうで試しに印刷して――ああ、だめだめ! もうこれ以上は言えません。これ以上秘密を漏らすと、我々は日本で商売ができなくなりますから!」
「だけど」と、チェリー・オングが心配そうに言う。「そんな特別な本ならば、お値段の方が、お高いんじゃございませんこと?」
渡嘉敷社長はすまなそうな顔をし、
「それがですねえ、恐縮なんですが、もちろん、定価ではお売りできないんですよ」
「定価はおいくら?」
「この頁数ですから、一冊千円は軽く超えると思いますが、来月発売なんで、まだ決まっていません」
「じゃあ、一冊一万円とか、二万円とか……」
チェリー・オングはがっかりしたように言う。
宝田晶はしたり顔で、
「そうだとしても、島田荘司氏の新作がこんなに早く読めるなら、みんな買うでしょうね。私だってほしい。いや、今日は、私は絶対に買って帰りますよ!」
賛同の拍手が客席から湧き起こる。
「で、おいくらなんでしょうか。渡嘉敷社長?」
と、司会者が熱心に尋ねた。
「それでは、いよいよお値段を申し上げましょう」と、渡嘉敷社長はもったいぶって言う。「本日は、特別値段で――二冊セットが――何と、本当に恐縮なんですが――税込み、サービス料込み、送料別途で――」
「で――?」
「――で、たったの二千円ポッキリでええええす!」
「ええ!?」「嘘!?」「まさか!?」「キャーッ!?」
と、チェリー・オングや宝川晶、そして、観客席のオバチャンたちがこぞって絶叫、悲鳴を上げる。
司会者は後ろにのけぞりながら、
「二千円! 島田荘司氏の新作が二冊で二千円! たったそれだけなんですかあ!?」
「ええ」と、渡嘉敷社長はまんざらでもない顔で言う。「しかも、実はそれだけではありませんよ」
「と言いますと?」
「たいへん恐縮なんですが、まだおまけがあるんです!」
「え、本当ですか!?」
「嘘!?」
と、チェリー・オングも驚く。
「本当です」と、ニヤリとした渡嘉敷社長が、別のスーツ・ケースを取り出した。「島田荘司氏の推理小説といったら、物語の面白さは抜群だし、トリックは大がかりだし、しかも、サスペンスに優れ、殺人場面は恐怖に満ちているということで有名です――そこで、これを読む読者は心臓がドキドキし、血管の中で血は逆流し、頭は興奮でパンクしそうになります。ですから、中には卒倒をしたり、心臓麻痺になったり、気持ちが悪くなる読者もいることでしょう!」
すると、宝川晶が頷き、
「ええ。私も心臓にペース・メーカーを埋めているので、島田荘司氏の小説を読む時には注意しています」
「ですから!」と、渡嘉敷社長はスーツ・ケースの中身をテレビ・カメラの方へ向けた。「我々は、そんな読者の健康を考え、島田荘司氏の新作二冊の他に、脈拍、血圧、心拍数が同時に計れるヘルス・メーターを付録としてお付けすることにしましたあ!」
「ええええ!?」
と、司会者陣は揃ってびっくり顔を見せる。観客席も大いに湧き上がる。
「やった!」「すごい!」「たまや!」「かぎや!」「人殺し!」
渡嘉敷社長は、島田荘司のノベルス二冊の横に、ノート・パソコンぐらいの大きさのヘルス・メーターを置いた。なかなか立派な品物である。単体でも、軽く一万や二万や三万円はするだろう。
「このヘルス・メーターのセンサーを体に付けていれば、安心して、『涙流れるままに』を読むことができます。いくら夢中になりすぎても、体調が悪化すれば、ちゃんと警告音が鳴りますからね。大丈夫なのです!」
「でも、ヘルス・メーターってお高いんでしょう。そうなると、本のお値段の方はどうなるのですか」
チェリー・オングが心配そうに尋ねると、渡嘉敷社長は軽く笑い、
「もちろん、このヘルス・メーターも、本代二千円ポッキリの中に入っているんですよお!」
「まあ! そんな!」
「しかも、もっと恐縮なんですが、今回はさらに特別中の特別のプレゼントを、私どもの会社の方から御用意いたしました!」
「何ですか!?」
司会者が大声で尋ねる。
「今回この『涙流れるままに』をお申し込みいただきますと、漏れなく、もう一セット、まったく同じ本が付いてくるんでえええす!」
「ひええええ!」
と叫声を、司会者陣と客席の観衆が同時に上げた。
「たった、二千円で、本が二セットと、高級ヘルス・メーターが買えるって言うんですか!?」
司会者は大騒ぎで尋ねる。
「ええ、そうです!」と、渡嘉敷社長は自信たっぷりに答える。「本は、読むための物と、保存用と、二冊ほしいですよね。今回、私たちは、この御要望にお応えしました。もしも一冊を、コーヒーをこぼすなどして汚したり、電車の中に忘れてきても安心です。もう一セット同じ本があるわけですから」
「この大盤振る舞い、信じられません!」
と、司会者は客席を見回して叫んだ。
「――それに」と、渡嘉敷社長はウインクしながら言った。「これだけ分厚い本ですと、読むだけではなく、他にもいろいろ使い途があります。枕にできるし、漬け物石代わりにもなりますし、花壇のレンガ代わりにもなります。また、立てても倒れませんから、他の本を間に挟んでブックエンドとして利用もできます」
「それは素晴らしい! これは買わなくては損です! 絶対のお買い得商品です! ワクワク・テレビ・ショッピング始まって以来の快挙ですねえ!」
司会者は目の色を変えて訴えた。
渡嘉敷社長は、カセット・テープを頭の上で振り回し、
「さらに、二十四時間以内にお申し込みいただいた場合には、この本の読み方を詳細に解説した日本語ビデオまでお付けします!」
と、会場の興奮をさらに煽った。
そこで画面がテロップに切り替わり、女性アナウンサーの声で、販売に関する案内が流れた。
「《商品番号893》、島田荘司氏の『涙流れるままに』、限定五十セット。お申し込みは、フリー・ダイヤル0012―××△―●□◇88。面白くなかった場合には、翌日までなら商品引き替えで代金をお返しします。なお、お届けまでには一週間から十日ほどかかります。お支払いは現金か、図書券で――」
その途端だった。
「うわあ!」と、カースケが切羽詰まったような叫び声を上げ、飛び上がると、「電話、電話! ミユキ、電話を捜してくれ!」
と大騒ぎして、部屋の中をグルグルと回りだしたのである。
「何よ、カースケさん!」
びっくりして、ミユキが言うと、
「買うんだよ、この本! 島田荘司の久々の新刊だぜ! 早く申し込まなくてちゃ! 売れ切れちゃうよ!」
ミユキは雑誌の山に埋もれていた電話の子機を見つけ、彼に手渡した。
「ありがとう!」
カースケは、たいへんな勢いで電話番号をプッシュした。幸い、電話は繋がり、彼は購入希望の用件を早口にまくしたてた!
「――やった! やった! 買えたぞ! 限定五十セットしかないのに、僕の手に入ったんだ! 奇跡だ! ミラクルだ! 天のお恵みだ! ああ、神様、仏様、閻魔様、お礼を申し上げます!」
「良かったわね、カースケさん」
「信じられない! だけど、ミユキ。通販って、いつもこんな素晴らしい物を売っているのかい!?」
「時々、私も欲しくなる物があるわ」
カースケはやっと座って、気持ちを落ち着けるようにコーヒーを一口すすってから、
「おお、ミユキ。僕はまだ興奮が冷めないよ。これって、夢じゃないかな。島田荘司の新刊上下巻が、たった二千円だぜ、それも、通常の刊行より一ヵ月も早く読めるんだ。それだけじゃない。あんなに立派なヘルス・メーターが付いてくるんだから」
「島田荘司さんのミステリーって、結末で必ず驚かされるじゃない。だから、心臓麻痺で死ぬ読者とかが、たまにはいるのかもね。それで、出版社側が{ルビ
PL}製造物責任{/}法対策で、読者の健康管理にも目を配りだしたのかしら」
「ああ、そう言えば、京極夏彦の分厚い本てさ、読み通すのに体力勝負だもんな。この前の新刊が出た時、駅前の本屋で、買った人に漏れなくドリンク剤をおまけに付けていたよ」
「本を読むのも命懸けね」
「そうとも言える。とにかく、僕は今、猛烈に幸せだあ! 早く来い来い、カッパの最新刊!」
「ところで、カースケさん。その本のお金はあるの? 代引きで申し込んだんでしょう?」
「それなら、明日のアルバイトで稼ぐから大丈夫だよ。品物が来るまで、二、三日かかるそうだから」
「――あ、カースケさん。そろそろ、《炎のミステリーの達人》の結果が出るんじゃないの?」
と、ミユキが時間に気づいて言う。
「おっと、そうだった。チャンネル変更!」
カースケはあわててリモコンをつかんだ。
ちょうど、銀山先生の作品の最後が朗読されているところだった。
俺は坂を下りていった。右足を出した。左足を出した。右手を振った。左手を振った。女が坂の下にいた。こっちを見上げていた。美しい目だった。黒目が二つあった。鼻が一つあった。口も一つだった。髪は赤茶に染めてあった。俺はまっすぐ歩き続けた。彼女の方へ近づいた。女は身じろぎもしなかった。俺はタバコを取りだした。歩きながら口にくわえた。ライターで火を点けた。坂が終わった。あとは水平な道だった。女の目の中に男の姿があった。俺の見知らぬ男だった。
「――なるほど」と、カースケは腕組みし、感心して言う。「実に簡潔な文章だ。男の哀愁が漂っている。女の悲しみが坂道に投影されているんだな。さすがは銀山先生だ。実にみごとにハードボイルドしている。これでは、竜禅寺先生も負けるかもしれない」
「そうなの?」
よく解らず、ミユキが訊き返す。
「そうさ。そういうもんなんだよ。銀山先生も、だてに流行作家じゃないなあ」
そして、ようやく審査員の協議が終わり、結果が出ることになった。
「――さあ、本日の勝敗が決します」
と、ちょうど司会者がもったいぶって言ったところだった。彼は封筒に入った勝敗表を取り出し、「本日の勝者は――銀山力宗先生! 題名は『北風ピューピュー寒いぜ』でしたああああ!」
と、宣告したのである。
「うへえ」と、カースケは天を仰ぎ、手で目を覆った。「やっぱりだ。残念だなあ。竜禅寺先生を応援していたのに」
「だけど、負けた方が本当の勝ちだって言ったじゃない」
ミユキは怪訝そうな声で言う。
「そりゃそうなんだけど、番組上は、勝った人の方に商品が行くからね。ファンとしては残念なわけさ」
「変なの――」
ミユキは、付き合っていられないという顔をした。
司会者の飯塚は、勝者の銀山と敗者の竜禅寺へのインタビューを終え、審査員である三人の評論家たちに、審査内容を尋ねた。最初は、この道五十年というベテランの館川正道だった。
「――それで、どうして『北風ピューピュー寒いぜ』をお選びになりましたか、館川先生?」
「決まっているじゃないか。今や、小説界は広義のミステリーの時代なんだよ。広義のミステリーと言えば、冒険小説やハードボイルドと相場が決まっているんだ。本格推理なんか古くさくってだめさ。もう乱歩や正史の時代じゃない。つまりだ。問題は中身ではなくて、外側がいかに重要かということなんだよ。ようするに、流行さ。だから、こんな勝負は、読む前から私的には勝敗が決まっていたのだ!」
「なるほど。そうしますと、最初から、銀山先生に投票しようと思って、このスタジオに来られたわけですね」
「当たり前じゃないか。だいたいだな、私は老眼が進んで、あんまり細かい字が読めないんだ。難しい感じだらけの原稿は勘弁してほしいね。そんなのは、面倒で見ていられるかね」
「申し訳ございません。次は拡大鏡を御用意いたします――次に、冒険小説応援団一筋十五年の和田山剣先生にお訊きします。何を勝敗の根拠にされたのですか」
「私はミステリー評論家だけど、頭が悪いものですから、ミステリーっていうものが何だか良く解らないんですよ。ミステリーの定義とか言われても、何が何だか不明ですしね。そういう意味では、この二編の短編小説は、どちらも本当にミステリーなんですか。そこの点からして、私には解らない。だから、ミステリーかミステリーでないか、来週のこの時間まで、私の宿題にさせてください。暇だったら、もう少し勉強してきますから」
「あまりに素晴らしい戦いだったので、和田山先生は未だに混乱されているようです――最後は、ミステリー業界の御意見番、豪徳先生にお願いしましょう」
「ふん。どっちがいいかなんか、その時の気分だよ。勘で選ぶんだ、勘でな。この豪徳の研ぎ澄まされた勘が、すべてを決める。俺様がこっちと言えば、こっちだし、あっちだと言えば、あっちなんだ。業界で一番偉い俺がそう言うんだから間違いない。そうに決まっているんだ!」
「解りました。明快なお答えで、胸がスカッとしました――それでは、盛り上がりに盛り上がった《燃えるミステリーの達人》ですが、そろそろお時間が来たようです。また来週まで、御機嫌よう、さようなら――」
「――ああ、面白かった」と、カースケは言い、背伸びをした。「な、ミユキ。けっこう手に汗握る番組だろう。規定時間に短編小説を書き上げなくてはいけないなんて、スリルがあるよな」
「本当ね。私も、来週から見るわ。だけど、あの豪徳っていう評論家、どうしてああいつも威張っているのかしら。バッカみたい!」
「まあ、評論家なんていう人種は、ミステリーに限らず、同じような印象を受ける時があるね。批評的行為を繰り返している内に、自分自身に何某かの権威があるって勘違いしちゃう人もいるんだろう。もちろん、地道にその分野の研究活動をしている人もいるけれど、声高に叫ぶ輩ばかり目立つというような実状があるんじゃないかな。そういう下劣な人間を、無批判で使う側にも問題がないとは言えないな」
「そうね」
「ところでさ――」
「なあに?」
「――もう、寝る?」
《五月八日土曜日 カースケが、小説家のアシスタントをする》
1
翌朝、九時にミユキと駅で別れたカースケは、流行ミステリー作家の存財四五郎の所へアルバイトに行くことにした。存財の家は国分寺市にあるので、原付バイクで行ける距離だった。
存財の家は、閑静な住宅地にあり、白壁で囲まれた一際大きな――まるでラブホテルのような――家だった。呼び鈴を押して案内を請うたカースケは、さっそくアシスタント・ルームへ通された。
「――さあ、ここが我々の仕事場だよ」
と、一番若いアシスタントの{ルビ せた}背田{/ルビ}が言った。十数畳ある洋間の中に入ると、机が向かい合わせに六個あり、そこに、男性が一人と女性が一人座っていた。机の上には資料らしき本や雑誌、書類が山積みになり、自在首のライトの下には、ラップトップ型のワープロや書きかけの原稿、雑多な筆記用具などがある。また、向かい側の壁は天井まで書棚になっていて、ぎっしり図鑑や百科事典などが詰まっている。
「こ、こんにちは」
カースケが少し緊張して言うと、キーボードを打っていた二人が顔を上げ、やや無表情に会釈を返した。
「やあ」
「どうも」
背田を含めた三人は、年の頃は三十歳くらいだった。
「アシスタントの{ルビ ももやま}桃山{/ルビ}君と、{ルビ
てぐさ}手草{/ルビ}さんです。それから、チーフの{ルビ
すじかわ}筋川{/ルビ}さんは、今、別室で存財先生と打ち合わせ中なんです。カースケ君は、一番端の机に座って作業をしてください」
と、背田が案内した。
「で、何をすればいいんでしょうか」
席についたカースケは、隣の背田に尋ねる。
「最初は、原稿にスクリーン・トーンを貼ってもらう。それが一番簡単だからね」
「スクリーン・トーン?」
「スクリーン・トーンを知らないの?」
「いいえ、知ってます。あの、マンガで、効果を出すために薄い網の模様なんかを貼るやつですよね。裏に薄く糊が付いていて――」
「そう。あれの小説用があるから、それを台紙から切り取って、原稿の適当な場所に貼るんだ」
「なるほど、解りました……」
実を言えば、カースケはよく解らなかったのだが、適当に答えた。
「じゃあ、この原稿の、会話と会話の間のあいている所に、男用と、女用のスクリーン・トーンを貼ってくれたまえ。トーンやカッターは、引き出しの中に入っているから」
背田が渡したのは、このような原稿だった。
………………………………………………………………………………
「何だって! 谷保天満宮の境内で殺人があったって言うのか」
「ええ、そうなのよ。首を絞められていたらしいわ」
多喜子は、悲鳴を上げるように、言った。
「それは、いつのことなんだ?」
「たしか、昨日の夜中って、警察は言っていたわ、義彦さん」
「何ていうことだ! 僕にはアリバイがない!」
「そんな!」
「およよ」
と、多喜子は、[]髪を振り乱して、泣き崩れた。
義彦は、彼女を、抱き起こし、
「しっかりするんだ!」
シ―(9)
「だけど……」
………………………………………………………………………………
カースケはそれを読んでから、背田に、遠慮がちに尋ねた。
「すみません。どことどこにトーンを貼ればいいんでしょう。あいている所、全部ですか」
自分のワープロのキーを叩き始めていた背田は、ちょっと面倒臭そうに顔を向けた。
「いいや、そうじゃない。一行だけの空白部分に、横の会話に合わせて、[と、彼は、言った。]か[と、彼女は、言った。]のどちらかのトーンを切って貼るんだよ。二行以上あいている所には、チーフが背景文章とかを書き込むからね」
「は、はい」
と、カースケが頷くと、
「――ああ、悪い、悪い、トーンの見本帳を渡してなかったね」
と、背田は自分の目の前にある書類の山から、青いプラスチック・ファイルを取り出した。そして、それをカースケに渡すと、
「ファイルの中にある見本のトーンには、全部、[ア―(1)]とか[イ―(5)]とか、番号が振ってある。だから、原稿の中にそうした記号が青鉛筆で指定してあったら、そのとおりのトーンを貼るんだよ」
「じゃあ、この原稿のこの部分には[シ―(9)]とありますから――では、[と、彼は、叫んだ。]というトーンを貼ればいいんですね」
「そのとおり。君は飲み込みが早いぞ、カースケ君。じゃあ、しっかりやってくれたまえ」
「はい」
カースケは、見本帳を確認しながら、引き出しの中から必要なスクリーン・トーンを取り出した。一枚目には、[と、彼は、言った。]ばかりが何十となく印刷されてある。カースケはものさしを使いながら、カッターの刃を表面にそっと当てて、最初の[と、彼は、言った。]を一つだけ切り取った。
「――原稿は汚さないでくれよ」
などと背田が注意するので、余計に緊張して、手に力が入る。
カースケは、最初の空白行に、何とか[と、彼は、言った。]を貼った。曲がらずにうまく貼ることができたので、ホッと安堵する。
「カースケ君。丁寧なのも良いが、あまりゆっくりやっている暇はないぞ。みんなから、どんどん原稿が回るからね。今日中に、住営社の『小説めばる』の原稿、五十枚を仕上げなくちゃならないんだから」
「は、はい」
カースケは少し焦って、次のスクリーン・トーンを取り出す。今度は女性の会話だから、[と、彼女は、言った。]を貼らなくてならない。その後は、[シ―(9)]の[と、彼は、叫んだ。]だ。
何とかできあがった原稿は、このようになった。
………………………………………………………………………………
「何だって! 谷保天満宮の境内で殺人があったって言うのか」
と、彼は、言った。
「ええ、そうなのよ。首を絞められていたらしいわ」
多喜子は、悲鳴を上げるように、言った。
「それは、いつのことなんだ?」
と、彼は、言った。
「たしか、昨日の夜中って、警察は言っていたわ、義彦さん」
と、彼女は、言った。
「何ていうことだ! 僕にはアリバイがない!」
「そんな!」
「およよ」
と、多喜子は、[ ]髪を振り乱して、泣き崩れた。
義彦は、彼女を、抱き起こし、
「しっかりするんだ!」
シと、彼は、叫んだ。
「だけど……」
………………………………………………………………………………
カースケが具合を確かめるために読み返していると、背田が、文章の後ろから二行目を指さし、
「[シと、彼は、叫んだ。]という所に、青鉛筆の[シ]が残っているだろう。これは、ホワイトで消してくれ」
「ホワイトって、この修正インクのことですか」
カースケは、急いで机の上見て尋ねる。
「そう。それを使って、白く塗りつぶすんだ。そうすれば、コピーを取る時には、余分な汚れが消えるからね。また、白髪ではない、普通の髪の毛の色の描写とか、喪服の色などの所も空欄になっているから、そこには《黒》って書き込むんだ。これを、僕らの専門用語で《ベタ塗り》って言うんだよ」
「解りました」
頷いたカースケは、指定されたとおりにした。そして、修正インクが乾くのを待ちながら、この文書をもう一度読み返した。流行作家の生原稿を見るのは初めてだから、ちょっと感動した。
「――それにしても、やたらに句読点が多い文章ですね。それにいちいち、[と、誰々が、言った。]なんて書かなくても、会話を読めば誰の発言か解るのに――」
そう言った途端、他の三人のアシスタントは怖い顔になって、キッとカースケを睨んだ。
「大地君!」と、背田が低い声で、しかし、怖い声で言った。「そんなことを、ここで言ってはいけない。存財先生のお耳に入ったらどうするんだ! 先生がお怒りになるじゃないか!」
「え、ええ!?」
カースケはびっくりして、焦った。
すると、前に座っている女性の手草がやや身を乗り出し、声を低めて、意地悪く言った。
「カースケさん。あなたって、馬鹿ね。存財先生は、今を時めく流行作家なのよ。文章をちゃんと吟味したり推敲しながら書いていたら、月産千枚なんて書けるわけがないじゃないの。こうやって、流れ作業で書くから、どんどん量産できるのよ。そのためには、解りやすいシステムを取り入れる必要があるの。会話だって、作業する私たちが原稿の全体を通して読むことができないから、誰の発言かすぐに解るよう、こういうふうに全部逐一、指摘がなされているわけなのよ」
「そうだよ、カースケ君」と、背田も言う。「玄関横の応接室には、毎日五人もの編集者が原稿を取りに来ているんだ。その人たちに、約束どおり原稿を渡さなくてはならない。そのためには、小説の質をある程度は落とすしかないんだよ。それを我々は、必要悪と呼んでいるんだ」
「でも、それでは、物語が面白くないんじゃないですか」
「そんなことはないさ。先生の作品はあんなにたくさん出版されているんだ。売れに売れているしね。マニア向けの新本格とか、やたらに長い冒険小説と違って、一つの長編は必ず原稿用紙四百枚程度。登場人物は名探偵役の熱川警部と伊東刑事を含め、全部類型的に創造する。舞台となる場所は温泉や崖のある観光名所がいい。そうすれば、テレビに売りやすいからね。それから、密室だの一人二役だの、小難しいトリックはなしだ。プロットの方も、複雑で解りにくくなった所は、視点を変えてすぐに説明しなくちゃいけない。そうしないと、読者が途中で読むのが面倒になる。もちろん、文章は平易が良い。当用漢字だけを使う――というふうにして、人気を得るために、存財先生をはじめ、我々は最大限の努力をしているんだよ」
「す、すみません」
横から、桃山というアシスタントが口を挟んだ。彼は、サブ・チーフであった。
「カースケ君。筋川チーフに聞いたけれど、君は確か、大学で《ミステリー研究会》に入っているそうだってね」
「はい」
「だったら、もう一つ注意をしておいた方がいいな。存財先生は、トリックという言葉が大嫌いなんだ。というか、実を言うと、自分で一つも考えられないのだからね。先生の小説に出てくるトリックらしきものは、あれは編集者が考えるんだよ。だから、先生の前では、絶対にトリックとかプロットなどという専門用語は禁句だ。逆に、先生の小説を誉めようと思ったら、『人間が描けてますね』と言えばいい。先生はもともと純文学崩れなんで、その手の言葉に弱いのだ。一番良いのは、『すっごく売れてますね』とか、『ベストセラーまっしぐら』って言葉だな。先生は大阪の出身だから、売り上げとかお金のことに敏感に反応する――どうだい、解ったかい」
「は、はい」
「じゃあ、次の原稿をやってくれ」
「すみませんでした……」
カースケは頭を下げ、自分の仕事に戻ることにした。正直に言って、何だかもうこのアルバイトが嫌になってきた。しかし、通販で買った物の代金を稼ぐためには仕方がない。辛抱辛抱。
三枚目の原稿を仕上げた時、チーフ・デザイナーの筋川が戻ってきた。《ミステリー喫茶》の筋川に顔がよく似ている。しかし、こちらの方は体格が良かった。
「あ、チーフ。彼が、今度来てもらったカースケ君です」
と、桃山が言う。
「おお。兄の紹介で来てくれた人だね。よろしく頼むよ」
「はい、こちらこそ」
立ち上がって直立不動の姿勢を取ったカースケは、頭を深く垂れた。
「そうだな、存財先生にも紹介しておくかな。カースケ君、こっちへ来てくれたまえ」
カースケは筋川に連れられ、二階にある存財の書斎へ入った。広い洋間で、壁にはたくさんの油絵が飾ってある。後で知ったが、バブルの頃に、投機目的で購入した物らしい。
六台のワープロがのった大きな書き物机の向こうに、ベレー帽を被った流行作家の存財がいた。写真で前に見たのよりひどく太っている。ほっぺたが落ちそうな感じで、鼈甲縁のメガネをかけたブルドック――カースケはそんな感じを受けた。
筋川が静かに存財の側に寄り、カースケのことを耳打ちした。すると、目にも止まらない速度で六つのキーボードを叩き続けながら、チラリと存財が顔を上げた。
「――うむ。そうか。まあ、筋川チーフにまかせるから、よろしく頼む」
ちょうど、印刷したばかりの原稿が机の端に置いてあり、カースケはそれを盗み見た。すると、こんな原稿であった。
………………………………………………………………………………
「私は、 」
島村は、
「向こうへ行けばいい」
多喜子は、
「ひどい! 」
三人は、睨み合った。
「しかし、 へ、帰ってくるしかないぞ!」
と、島村は、
「私の、 」
「僕は、
」
義彦は、
「だったら、
」
………………………………………………………………………………
カースケは内心驚いたが、それを何とか顔に出さないよう頑張った。
「――では、失礼します。先生」
と、筋川は頭を下げ、カースケを連れて退室した。
アシスタント・ルームへ戻りながら、カースケは興味心が湧き起こって、思わず尋ねてしまった。
「筋川チーフ。一つお訊きしたいのですが、どうして存財先生は、ほとんど主語だけしか書かれないのですか」
筋川は別に怒りもせず、
「それは、さっきも言ったとおり、先生が超売れっ子だからさ。原稿全部を先生が書いていたら、とうてい注文をさばききれない。かと言って、代筆なんてことは、先生のプライドが許さないのだ。だから、こうして僕らアシスタントがお手伝いをして、分業制で原稿を書き上げるわけだよ。たとえば、僕の役目は、会話と会話の間の背景文章を埋めることさ」
「マンガ家がアシスタントを使うのは知っていましたが、小説家までそうだとは、初めて知りました」
「そんなのは常識だよ。売れっ子はみんなやっていることさ。それに、うちの先生なんかは、自分で書き込んでいる量はずいぶん多い方だよ。会話の鉤括弧まで書いているなんて、本当に立派なことさ。それに、青鉛筆で、スクリーン・トーンを貼る位置を指定するのも先生だからね。ずいぶん、手作業の比率が高い」
「はあ……」
「さあ、とにかく、原稿を仕上げよう。今日は、短編二本と、長編連載を一本完成させなくちゃならないのだよ」
「はい」
カースケは小説家に対していだいていた幻想が崩れ、何だかがっかりした。しかし、こんな人たちばかりでもあるまいと思い直し、とにかくお金のためにやることだけはやろうと、気持ちを切り替えた。
2
昼食を交代で取り、短編原稿を一つ上げた時、ふいの来客があった。その人物は勝手にズカズカとアシスタント・ルームへ入ってきて、迷惑も顧みず、傍若無人な態度でわめき立てた。
「わっはははは。いやあ、諸君。やっちょるね。仕事の進み具合はどうだ。はかどっておるかね。今日は、このお偉い俺様が存財先生と君たちの陣中見舞いに来てやったぞ!」
その姿を一目見て、カースケはゲッと喉の奥で唸った。そして、あわてて机に顔を伏せた。何しろそれは、例の威張り散らし屋のミステリー評論家、豪徳完之介だったからだ。
豪徳は太鼓腹を突き出し、ドシドシと足音を立てながら、アシスタントたちの後ろを歩いて、原稿を覗いて回った。自分の背後まで来られた時には、カースケは気が気ではなかった。
「今度の原稿のできはいいのか。なるべく面白く書いておいてくれよ。年末になったら、ミステリー・クラブ賞の下選考をするのは俺様なんだからな。あんまりつまらない小説だと、予選を通しづらいからな。頼むぜ、諸君!」
「豪徳先生」と、筋川が丁寧に言った。「存財先生は、今、三階でお食事中です。銀座のママが、お弁当を持ってこられたので……」
「解っているよ。だから、ここで時間を潰しているんだ――銀座のママってのは、《SM》って店のママだろ。畜生。いい女を独占しおって、存財先生がうらやましいぞお――おお、ところでだな、そう言えば今は昼なんだな。どうりで俺の腹がグーと減ったと思った。最近は、なかなかウナギを食う暇もないほど、俺は忙しくてな」
「豪徳先生。昨晩の、《燃えるミステリーの達人》も拝見しましたよ。相変わらず、鋭敏な評論で感心させられました」
「当たり前だ、チーフ。俺様を誰だと思っているんだ。業界御用達の大ミステリー評論家、豪徳完之介とは、この俺のことだあ!」
両手を後ろ前に突き出し、歌舞伎役者のように見得を切った彼を、筋川は別室へ連れ出そうとした。ここにいられると作業の邪魔だが、推薦その他の文章を本の帯に書いてもらっている手前、そう邪険にもできない。
「豪徳先生、鰻丼の出前を取りますから、待合い室の方でお待ちいただけませんか」
「そうか。悪いな。じゃあ、ドンブリじゃなくて鰻重を頼む。特上がいいかな……」
筋川がやっとうるさい豪徳を連れ出したので、部屋の中が静かになった。桃山と手草も疲れた顔で、ため息をつく。
「桃山さん。あの豪徳という評論家は、いつもあんな感じなんですか」
声をひそめながら、カースケが尋ねる。
「そうなんだよ」と、桃山もほとほと呆れた顔で言う。「ああやって、しょっちゅう食事や酒をたかりにくるんだ。本当は、存財先生も迷惑しているみたいなんだけど、先生の本の推薦や書評は、ほとんど豪徳氏が書いているんで、強いことも言えないんだよ」
「下らないわね」と言ったのは、手草だった。「私だったら、即座に、あんな奴は追い出してやるわ」
「そうもいかないさ」
「今日は、何しに来たんです?」
と、カースケが尋ねる。
手草は下唇を突き出し、
「たぶん、新刊の惹句の打ち合わせでしょ。どうせ、書く文句なんて、最初から決まっているのよ。《胸を打たれるほど感動した》とか、《ここ数年間で最高の傑作》とか、《この作家と同時代に生まれて幸せである》とか、まあ、そんなところね」
「ああ、そんなところだろう」
桃山も頷く。
「そう言えば」と、手草がニヤリとした。「豪徳さんたら、この前、どこかの《読書ラン》で素人のミステリー・ファン相手にブラインド・テストをして、負けたんですってよ。いい気味だわ」
「ああ、それは僕も聞いた。しかも、相手は素人だったってんだろう。みっともないな」
カースケはギクリとした。それは自分のことだったからだ。
「あのう、その話って、評判になっているんですか」
と、尋ねると、桃山は皮肉な調子で頷き、
「ああ、この業界は狭いからね。アッという間に噂は伝わる――さあ、仕事、仕事。手を休めている暇はないぞ。今夜は徹夜になりそうだし」
「私なんか、もう四日もお風呂に入っていないわ」
と、手草がためいきをつく。
「文句言うな。俺なんか、三週間だぜ」
そんな言葉を聞きながら、カースケは一昨日風呂へ入った自分の幸せを、心の中で噛みしめた。
それから一時間くらいして、廊下の方から騒がしい声がした。存財と豪徳が大声で話しながら、こっちへ来たのだ。
「にゃはははは。豪徳君。とにかく、わしの新作が売れに売れる惹句を考えてくれよ。この前の《かつてこんなに素晴らしい作品はあっただろうか!》ってのは、もう何度も使っていて、あまりインパクトがなかったぞ!」
「うっはははは。そうかね、存財先生。しかし、しょうがないだろうが。例によって、あんたの小説を読まずに書いたんだから、最後を疑問符で締めくくっておかないと、読者に嘘をついたことになる。それだけはまずいからな」
「いっひひひひ。相変わらず、読者を騙すのがうまいな、豪徳君」
「へへへへへ。お互い様さ――それでだな、存財先生。次の作品の週刊誌での紹介文の見出しは、《アガサ・クリスティーを凌ぐか!?》ってのにしようかと思うんだ。《凌いだ!》って書くと嘘になるが、《凌ぐか!?》なら嘘とは言えない。疑問形だからな。そうすれば、読者は、作者がクリスティーに挑戦したかのように勝手に錯覚するだろう」
「おいおい、豪徳君。今度の奴は、いつもどおり、主人公が温泉に入って、被害者が断崖から突き落とされるだけのトラベル・ミステリーだぞ。題名だって、『紅葉狩り温泉殺人事件――タヌキは見ていた。一分十五秒の隙間』というのだ。ぜんぜん、クリスティーとは関係ないんだ」
「関係なんて、どうでもいいんだよ。読者にアピールすれば万々歳だ。何か訴えるものがあれば、本も売れるし、俺の名前も売れる。これこそ一石二鳥だ」
「まあ、そうか」
「そうさ」
「わっははははは」
「うっひひひひひ」
二人は馬鹿笑いしながら、アシスタント・ルームに入ってきた。カースケはまた顔を伏せて、原稿の手入れに集中している振りをした。
「ところで、豪徳君。君はあいかわらず、あの外車の何とかいうオープンカーに乗っているのか。屋根のない車を運転するなんて、命を捨てているようなものだ。自殺行為だからな。わしのようにベンツにしたまえ。ベンツに」
「大丈夫だよ。安全対策はしてあるとメーカーは言っている」
「そうかな。ひっくり返ったら悲惨だと思うがな――ああ、筋川君」
と、存財先生はチーフに声をかけた。
「はい、何でしょうか。先生?」
「今度の新作でも、豪徳君が、新聞広告の推薦文を書いてくれることになった。それで、どの惹句が良いか、君が選んでおいてくれないか。わしは忙しいので、そんな暇はないのだ」
「はい。かしこまりました」
「じゃ、頼むよ」
と、言い残して、存財先生はさっさと部屋を出ていってしまった。
「豪徳先生、それでは、見本を見せていただけますか」
筋川チーフが言うと、豪徳は、
「ああ、これだ――みんな素晴らしい惹句だから、どれでもいいぞ」
と、胸ポケットから折り畳んだ紙を取り出した。
「手草君。人数分コピーを取って、みんなにも回してくれ」
と、筋川はそれを手草に渡した。
彼女はコピー機で印刷した紙を、桃山やカースケにも配った。
それには、こんなふうに書いてあった。
………………………………………………………………………………
(1) 読み終わった途端に茫然自失となった。こんなに面白い本があっていいのだろうか。『』の凄さを説明することはできない。
(2) 荒れ果てた都会の乱れた精神を、これほど熾烈に書ききった本が、他にあるだろうか。
(3) 私にはこの『』という小説をどう説明したら良いか解らない。何故なら、私には説明するだけの言葉も表現力もないからだ。
(4) 胸が熱くなった。目頭が熱くなった。これほどの物語を、ここ何年も読んだことがない。これは、たくさんあるここ十年間のベスト1の内の1つである。
(5) 『』は、文句の言えない傑作である。感動のプロローグから、激動のエピローグまで、すべてが面白い。
(6) 読む前から決まった。『』は、今年度のアンケート第1位に!
(7) 買え! 買え! 買え! 買え! お願いだから買ってくれ!
BY 豪徳完之介
………………………………………………………………………………
これに目を通して、カースケは心の中で呆れに呆れてしまった。
〈何だこりゃ? いずれもどこかで見たことある惹句ばかりじゃないか〉
しかし、当の豪徳は悦に入って、タバコを吸いながら、
「うはははは。どうだ。見事な宣伝文句ばかりだろう。この道ウン十年の俺様が、長年育ててきた惹句ばかりだ。これさえ付ければ、どんな小説でも売れるのは間違いないぞ!」
と、自慢したのである。
「豪徳先生」
と、紙面から顔を上げた筋川が言った。少し気むずかしい表情をしている。
「これってもしかすると、この前のうちの先生の新刊、『直角の交錯の死角の殺意の逆転の遊戯の証明の構造の亀裂』の時にもお持ちになった物ではありませんか」
「あん? ああ、無論そうさ。あの時には、一番目が採用になったから、今回は二番目から七番目の内から選べばよろしい。もちろん、『』の部分に題名が入る。まあ、言うなれば、これは宣伝用文章のテンプレートだな。こうやって、前もってひな形を作っておくと、応用が利くというわけさ」
「しかし、豪徳先生。今回の『紅葉狩り温泉殺人事件』はわりと早く原稿が上がりそうなので、できましたら、実際にお読みいただいた上で、内容にピッタリな惹句を考えていただきたいのですが」
「何を言うか、筋川君!」と、豪徳は灰皿でタバコを揉み消し、急に険しい顔になった。「この忙しくて有名な俺様に、わざわざ小説を読んで惹句を付けろと言うのか。馬鹿も休み休み言いたまえ。そんなことをしなくても、惹句などこれで充分だ。だいたいだな、俺は、過去にそんな面倒なことをしたことは一度もないんだぞ!」
「はあ。申し訳ございません」
「解ればいいさ――ほら、さっさと選べ! 時は金なりだ!」
筋川はアシスタント全員の顔を見回したが、カースケを含めて誰も発言をしなかった。それで彼は、
「それでは、私は、三番目が良いかと思います」
と、脱力感たっぷりに言った。
ところが、豪徳は機嫌を直して、
「おお、そうか。筋川君、君は目が高いぞ。俺もだな、その惹句には自信があるんだ――《私にはこの『紅葉狩り温泉殺人事件』という小説をどう説明したら良いか解らない。何故なら、私には説明するだけの言葉も表現力もないからだ》――うむ、素晴らしい! これなら、存財先生も喜ぶし、編集者も一発でOKを出すだろうな!」
「――そうでしょうね」
「よし。じゃあ、存財先生にはこれで決定したと言っておいてくれ。俺は、凡要社の担当編集者にFAXしておくからな」
「ありがとうございます」
筋川が礼を言うと、豪徳はふんぞり返って部屋を出ていこうとした。
しかし、カースケの我慢もそれまでだった。
「ちょっと待ってください!」彼は大声を上げて立ち上がり、手に持っていた物差しを机の上に叩きつけた。「ふざけるのもいい加減にしてほしいですね!」
「何だと!?」
豪徳が言い、皆も驚いてカースケの方を見た。
お偉い評論家は反射的に怖い顔をして、カースケを睨んだ。
「貴様、今、何と言った! それは、この俺様に言ったことか!」
「そうですとも!」興奮したカースケは、もう見境がつかなくなっていた。「あなた以外に他に誰がいると言うんです!」
豪徳は怒りに顔を真っ赤にして、
「面白い! この若造め! 俺様にそんな口を訊くとは、いったいどういうつもりだ!」
「どういうつもりもこういうつもりもありませんね。ミステリーを愛する読者を代表して、あなたに一言、文句を言おうと思っただけですよ!」
「文句? 何の文句だ!?」
「あなたのデタラメな態度ですよ。原稿をちゃんと読みもせず、でき合いの惹句を何度も使い回したり、あらすじばかりの書評を読まされるのはもうたくさんです。少しは真面目に仕事をしたらどうなんですか!」
「ば、馬鹿を言え!」と、豪徳は怒鳴り、それから、急に目を丸くすると、「ああ! お、お前は――も、もしや!?」
と、カースケの顔に向かって太い指をまっすぐ突きつけた。その時になって、ようやく彼のことを思い出したらしい。
その様子を見て、カースケの方は少し冷静を取り戻した。それで、居住まいを正すと、
「そうですよ。僕ですよ。以前、《舞羅運》という高級《読書ラン》でお会いしたカースケです。あなたをミステリーのブラインド・テストで破った好青年ですよ。覚えていてくださいましたか」
豪徳は急に狼狽して、
「す、筋川! こいつは何だ! なんで、こんな不逞の輩がここにいるんだ!」
事態がよく解らない筋川はあわてた顔で、
「え、ええ、それはですね。彼は今日入った新人のアシスタントなんです……」
と、かろうじて説明した
「くそう! いいか、こんな奴はすぐにクビにしろ! 冗談じゃない! ああ、気分が悪い! 存財先生には、俺から言っておくから、すぐに、こいつをここから追い出すんだ! そうじゃなかったら、俺はもう、存財先生の応援はしないからな!」
「は、はい」
と、筋川はひどく困惑しながら頷いた。
豪徳はすごい勢いでドアをあけ、それを思いっきり叩きつけるようにして退出した。
部屋の中が静まり返る。
最初に声を出したのは、手草だった。
「ねえ、カースケ君。ミステリーのブラインド・テストで、豪徳さんを負かした人物って、本当にあなたなの?」
「はい……」
カースケは少し落ち込みながら答えた。どんな理由があるにせよ、騒ぎを起こしてしまったのは間違いなかったからだ。
「愉快ねえ」
と、手草は笑い、桃山と顔を見合わせる。
だが、筋川は困りきった顔で、
「カースケ君。まずいよ。豪徳先生とうちの先生とは親友どうしなんだ。だから――」
「はい、解っています。こんな事態を引き起こして申し訳ありませんでした。僕はこれで失礼します。皆さんにはお詫びの言葉もありません」
「うん。僕たちはどうでもいいんだけど、先生がね――じゃ、すまないけど、先生が来る前に、君はここから立ち去ってくれるかい」
「そうします……すみませんでした……」
カースケは頭を深々と下げ、部屋を出た。そして、誰の見送りもないまま、この家を後にした。
まだ陽は高い。よく晴れた日だった。
しかし、カースケの気持ちは曇っていた。がっくりきていた。豪徳に喧嘩を売ったことは後悔していなかったが、アルバイト料をふいにしたのが悔やまれたのだ。
『どうして、僕はこう辛抱が足りないのだろう……』
カースケは自己嫌悪に陥り、ズボンのポケットに手を突っ込み、背中を丸めて、ゆっくりと自分のバイクを停めている方へ歩きだした。この話をした時、ミユキに何と言われるか、それが少し心配だった。
《五月九日日曜日 カースケが先輩に連れられ、東京ビッグサイトへ行く》
1
土曜日の夜、打ちひしがれたカースケが家でふて寝をしていると、一本の電話がかかってきた。
「おい、カースケ、いるか!」受話器の向こうで威勢の良い声が聞こえた。「おれだ、{ルビ
すずきじゅん}鈴木順{/ルビ}だ。解るか、鈴木のスーヤンだぞ!」
相手は、去年大学を卒業した《ミステリー研究会》の先輩だった。髪を七三に分けていて、黒縁のメガネをかけた、外見からしてわりと生真面目な性格の人物だった。
「解りますよ」と、カースケは苦笑しながら答えた。「だって、鈴木先輩。こうやって電話を取ってるんですから」
「そうだな。それは正しい認識だ。ところで、カースケ。お前、明日は暇か」
「僕ですか。ええ、暇ですが……」
いきなり尋ねられて、カースケは何事かと思った。
「だったら、俺に一日付き合ってくれないかな。ちょっと急な仕事が俺の所に回ってきたんだが、人手が足りなくて困っているんだ。アルバイト料をはずむから、頼むよ!」
「え、アルバイト料!?」
カースケは、その言葉に過敏に反応した。
「ああ。どうだ、一日二万円プラス交通費と食費で」
「いいです。やります。やります!」
「よし、決まった。じゃあ、午前九時に、東京駅八重洲口にある待ち合わせ場所の《銀の鈴》へ来てくれ。別に何も準備は要らないから、身一つでな」
「解りました。ところで、何をすればいいんですか」
「俺のアシスタントだよ。お台場にある東京ビッグサイトという展示場へ行くから、一緒に付いてきてくれ」
「何があるんですか」
「《ミステリー・ドラフト会議》という大イベントだよ」
「何ですか、それ」
「おい、おい。お前、《ミステリー研究会に》に入っているくせに、出版業界における年一回の最大のお祭りを知らないのか」
「すみません」と、カースケは受話器を耳に当てたまま頭を下げ、「確か鈴木先輩は、神保町にある奇譚社という出版社へお勤めになったんでしたよね」
「そうさ。しかも、先月から《奇譚社ミステリー》というノベルスを出している部署へ配属になった。それで、明日、東京ビッグサイトへ行かなくてはならないんだ」
「《ミステリー・ドラフト会議》って、何をする会議なのですか」
「そんなのは、明日、向こうへ行けば解る。じゃあ、俺は準備があって忙しいから電話を切るぞ。東京駅でまたな――」
鈴木は用件を言い終わると、さっさと電話を切った。
そういうわけで、日曜日の午前九時というわりと早い時間に、カースケは東京駅の《銀の鈴》にいた。改装工事が終わって前よりもだいぶ広々とした感じになり、ずいぶんたくさんの人が待ち合わせに使っていた。
「――すまん。すまん。カースケ」
と、彼は後ろから肩を叩かれた。
振り返ると、ポマードで髪を固めた、青い背広姿の鈴木が立っていた。
「あ、鈴木先輩。お久しぶりです」
カースケは相手の姿を見て、笑顔になった。
「何だよ。俺の顔に何か付いているか」
鈴木が少し口を尖らせる。
「だって、前は、いつもボロボロのTシャツとジーパンしか着なかったのに。サラリーマンに見えるんで――」
「馬鹿か、お前は。俺はもう責任ある社会人なの。身なりぐらいちゃんとするよ。それより、開場が九時半で、ドラフト会議が始まるのが十時半だ。時間はあるが、事前準備もあるので急ごうか。タクシーで行くぞ」
鈴木が威勢よく言い、二人は歩きだした。
「ずいぶん豪勢ですね。バスもあるんじゃないですか」
「いいんだよ、タクシー代くらい。何しろ今日のドラフト会議での抽選によって、この一年間のミステリー出版の行方や動向が決まるんだからな。どの社も必死だよ。予算だってたくさん出るわけさ」
二人は地上に出ると、タクシーに乗った。
カースケは、車の椅子の中で体をもじもじさせながら尋ねた。
「――ところで、僕は何をすればいいんですか」
「まあ、俺の相談役というところだな。本当は別の担当者が二人いたんだけど、一昨日、急に会社の役員が心臓麻痺で死んでな、ちょっと手薄になっちまったんだ。俺もお前もピンチ・ヒッターというわけさ。しかし、成果は上げなくてはならない」
「実際には、ドラフト会議で何が行なわれるんです?」
「簡単に言えば、来年度、自分の会社に本を書いてもらうミステリー作家をくじ引きで当てるわけだよ。人気作家には注文が殺到するから、その混乱を解消するために、出版権を抽選で決めるわけだな。これなら公平なシステムなんで、出版社側も納得するし、作家の方も、次はどこで書くかと頭を悩まさなくていい」
「へえ。いつからそんな会議が?」
「一昨年からだよ。まだ始まったばかりの新しい方法だ」
「ぜんぜん知りませんでした」
カースケは感心した。
鈴木は偉ぶって、
「そういうのを、勉強不足と言うのだ」
「じゃあ、今日のドラフト会議で、なるべく人気があって、売り出した時に部数の稼げる作家を手に入れる――それが、僕らの役目であるわけなのですね」
「おお、カースケ。飲み込みが早いぞ。まったくそのとおりだ。それで、お前にはだな、最近、大学生とかに人気のある作家が誰か、それを教えてもらおうと思ったんだ」
「解りました。と言っても、新本格推理作家なら、誰でも人気があるんじゃないですか」
意外に道は空いていたので、三十分ほどで、タクシーは東京ビッグサイトに着いた。鈴木は勝手知ったる会場なのか、代わった形をしたその建物に向かってまっすぐ歩いていく。他にも大勢の人が、そこに向かっていた。ガラス張りの入り口の所で、鈴木は二人分の入場許可書を提示し、会場案内と、二銭銅貨を象った通行バッジをもらった。
カースケにバッジを一つ渡してから、鈴木は、
「俺たちの行くのは、ミステリー・ゾーンだ。他に、純文学ゾーンとSFゾーンと時代劇ゾーンと恋愛小説ゾーンがあって、そっちでもドラフト会議がやられている。だけど、会場が一番大きいのはミステリー・ゾーンだ。広いから迷子になるなよ」
「《ミステリー・ゾーン》なんて言うと、何だか一昔前にやっていたSFテレビ番組みたいですね」
と、カースケは笑った。
エレベーターで地下へ下り、巨大な体育館のような会場へ入る。すでにかなりの人数の人間が顔を見せていた。鈴木は案内を確認しながら、出版社参列者席へ向かう。会場の奥には、大きな舞台があって、作家や作家の代理人が雁首を揃えるためのブースが設けられていた。
ようやく、カースケたちが自分たちの席を見つけた時、隣に座っていた中年の男性が鈴木に声をかけた。
「おや、奇譚社さんは、鈴木君が代表かい?」
白髪でなかなか品の良さそうな人物だった。銀縁の四角いメガネをかけている。
「あ、これは、水晶出版の加賀さん。どうも御無沙汰しています」
鈴木はすかさず頭を下げ、カースケもそれに倣った。
「まあ、お掛けなさい。そんなにかしこまらないで」
「はい。では――」
「そっちの人は?」
と、微笑みながら、加賀はカースケの方を見た。
鈴木が彼を紹介しながら、
「カースケといって、僕の大学の後輩なんですよ。実を言いますとね、原宿の《舞羅運》で、評論家の豪徳氏をやりこめたのがこいつなんです。みどころがあるんで、今日は、僕のアシスタントとして連れてきました」
「それはそれは」と、加賀はにこやかに笑うと、「あの武勇伝は私も聞いているよ。実に愉快な話だ。しかし、そうなると、今年の奇譚社さんは強敵だな。目当ての作家さんを取られないようにしなくちゃ」
「何をおっしゃるウサギさん。大丈夫ですよ。加賀さんの所とうちでは規模が違いすぎます。うちは、わりと新人狙いですから」
「まあ、正々堂々と抽選で戦おうじゃないか」
「はい。どうもありがとうございます」
と、鈴木は頭を下げてから、カースケに、
「おい、カースケ。こちらの加賀さんはな、あの全二百巻の日本本格推理小説全集とか、ディクスン・カー新訳全集とか、大阪圭吉完全全集などを編まれた方なんだぞ。我々ミステリー出版関係者の鏡のようなお方だ」
「そうなんですか。それはすごい!」と、カースケは声を上げて、「僕、今に絶対にお金を貯めて、あの日本本格推理小説全集を買おうと思っているんですよ!」
「ははは。それはぜひ頼むよ」と、加賀はまんざらでもない顔をし、「ところで、鈴木君。最近の奇譚社ノベルスはなかなかすごいじゃないか。あの新人作家、何て言ったっけ――そうそう。竜禅寺幸典先生と言ったかな。彼の『瓦礫の館の悲劇』と『螺旋の館の悲劇』を読んだけれど、実に面白かったよ」
「あ、そう言っていただけると嬉しいです。うちの社の久々のヒットなものですから――ところで、加賀さんの方はどうですか。何か新しい企画とはないんですか。ちょっと小耳に挟んだところでは、新本格推理作家を集めて、面白い企画を練っておられるとか」
「ほほう。なかなかの情報通だね、鈴木君。どこから聞いたんだい」
「いえ、ちょっとその辺から……」
「そうか。まあ、君と私の仲だから、こっそり教えようかな。まだあまり、人には言わないでくれるかな」
「もちろんです」
加賀は、鈴木とカースケの方へ少し顔を寄せ、小声で、
「うちの水晶叢書で、《新本格推理ジュニア・シリーズ》というのを出すことにしたんだよ。新本格推理の先生方に、少年少女向けの本格的な推理小説を書き下ろしてもらってだね、未来の重要な購買層である少年少女に、最新の推理小説の面白さを知ってもらおうという計画なんだよ」
「それは、いい考えですね。やられたなあ!」鈴木は大袈裟に嘆いたが、まんざら嘘でもなさそうだった。「――で、どんなラインナップですか」
加賀は鞄から一枚の紙を取り出し、それを二人に見せた。
「まだ、初期企画の段階だけどね、これだよ――」
………………………………………………………………………………
北村薫『スキップ・スキップ・ランランラン!』魔法のスキップをすると、過去へタイム・スリップする少女の物語。
竹本健治『ウロボロスのどらえもん』訳が解らない異次元推理。
法月綸太郎『法月綸太郎 最後の事件』最後の一撃。
我孫子武丸『人形は小遣い欲しさに推理する』二人はついに結婚するか。
京極夏彦『鉄像の檻』小坊主の一休さんと珍念さんが、和尚さん失踪事件について推理合戦をする。
芦辺拓『黄昏の怪人――ZQ18号の函』怪人対巨人の戦い。
篠田真由美『少年ドラキュラと少女カーミラの恋』そういう話。
麻耶雄嵩『ジュブナイル版 夏と冬の奏鳴曲』子供向けに、地球内部の構造を優しく読み解く科学ミステリー小説。
山口雅也『キッド・ピストルズの学園生活』。若き名探偵の推理。
島田荘司『頭痛――子供にも解る死刑問題』読んでいるだけで頭が痛くなるような超奇想ミステリー。
歌野晶午『薬中探偵と七つの事件』薬物中毒の探偵が事件を解決し、子供たちにドラッグの恐ろしさを教える。
折原一『変態者』。変態のオンパレード。
有栖川有栖『中国雑伎団の謎』殺されたパンダの謎を、火村が推理する。
笠井潔『量子学者の一人二役』もしくは、『科学者の不在証明』難しい話。
西澤保彦『渡辺のジュースの素の家の冒険』という話。
二階堂黎人『幽霊城の秘密』少年探偵シンちゃんが、幽霊城の秘密を暴く。
………………………………………………………………………………
カースケは、このリストを見て、面白そうな作品ばかり並んでいるので喜んだ。
「すごいですね、加賀さん。これが全部、本当に出るんですか」
「うん。著者の皆さんから、だいたい仮承諾をもらったところだよ。まだ、他にも何人か声をかけているんだがね。私としては、久々に手応えを感じているところだ。来年始めから刊行開始の予定だから、本が出たら、カースケ君、君もぜひ買って読んでくれたまえ」
「はい、もちろんです。今から楽しみです――でも、綾辻行人さんの名前がないんですね」
「ああ、綾辻先生からは昨日返事があった。一番最後の刊行なら参加してくださるそうなんだ。たぶん、『少年殺人鬼』か『百辺館の殺人』という作品を書き下ろしてくださるだろう」
「法月綸太郎さんは、本当に出るんですか」
「シッ。大きな声では言えないが、だめなら、代作という手もある。大乱歩の頃からの常套手段だ。千街晶之とか佳多山大地あたりの若手評論家に代筆させようと思う」
「なるほど。そうですね」
カースケが頷くのと同時に、鈴木は大きなため息をついて、
「いいなあ。いいなあ。水晶出版社さんは大きな会社だからいいなあ。こんな面白い企画ができて、本当にいいなあ。僕もやりたいなあ」
と、子供みたいなだだをこねだした。
「何を言うかね、鈴木君」と、苦笑した加賀さんは、リストを片づけながら言った。「出版社の大きさなんて関係ないよ。ここに名前のある作家の先生方は、みんな本格推理を愛しておられる方々ばかりだ。つまり、こちらがそれに応えられるような面白い企画を立てれば、ちゃんと原稿を書いてくださるんだよ。最近は、読者も作家も趣味性を大事にしている。だから、そうした面を強調して企画を立てればいいのさ」
「そうですね。すみません。僕が間違っていました」
鈴木は照れて、頭のうしろをかいた。
「解ってくれればいいさ。まあ、君もがんばりたまえよ」
ベテランの加賀は、若い編集者を励ます。
二人の会話を聞きながら、カースケは、出版社の編集という仕事のたいへんさの一端が解ったような気がした。
加賀がトイレに立つと、鈴木は急に真面目な顔になり、
「カースケ。それでは、そろそろ偵察に行ってきてくれ」
と、小声で指示を出した。
「偵察?」
訳が分からず、カースケは訊き返した。
「そうだよ。他の会社の入札参加者たちが、誰に投票しようとしているか、近くに行って、こっそり話を聞いてくるんだ」
「じゃあ、僕にスパイをしろと言うんですか」
カースケは驚いて目を丸くした。
「そうさ。当たり前だろう。じゃなきゃ、何で、お前を高いアルバイト料で雇ったりすると思うんだ――いいか。散歩でもしている振りをして、それとなく情報を収集してきてくれ」
「はあ……解りました」
カースケはそう答えるしかなかった。
彼は立ち上がり、まわりを見た。参列者の席はまだ半分ほどしか埋まっていない。とりあえず、ロビーに出てみることにした。
2
カースケは、広いロビーの端にあった自動販売機で缶コーヒーを三本買い、それを胸にかかえて周囲の様子を窺った。大勢の編集者がいる。喫煙コーナーで一人でタバコを吸っている者、あるいは同僚と打ち合わせをする者、他社の編集者と挨拶する者、こそこそと何かの資料を確認している者、カースケ同様、鋭い目であたりに気を配っている者、やたらにうろうろする者――など、実に様々であった。
カースケはそうした人々の間をゆっくりと縫って歩き、誰か人を捜しているような素振りを見せた。そうして、側を通り過ぎる際に、皆がどんな話をしているのかと、聞き耳を立てた。
しかし、どの編集者も意外にガードがかたかった。近寄ると口を噤むか、顔を背けたりして、なかなか会話の内容を聞き取ることができなかった。それでも、一応、各社が、ベストセラーを連発する有名作家とか、最近、何らかの文学賞を受賞して話題を呼んでいる作家などに的を絞っていることは感じた。
〈そりゃそうだよな。どこの出版社だって、売れない作家より、売れる作家が欲しいに決まってるもんな〉
そして、カースケが会場の方へ戻ろうとした時だった。談笑しながら、入り口を通りすぎようとする二人の人物が見えた。一人は痩せぎすでやや黒い顔をした男。もう一人は、誰あろう、あの傲慢な評論家、豪徳完之介だったのである。
「何てことだ!」
小さく口に出したカースケは、さっそくこの二人の後を、一メートルほど離れて付け始めた。
「うっはははは」と、例によって、豪徳の馬鹿笑いがあたりに響き渡った。「{ルビ
かたあし}片芦{/ルビ}君よ。安心していたまえ。この俺様が凡要社で出している白鯨ブックスの顧問となったからには、必ず、売れっ子の作家を抽選で当ててやるからな」
片芦と呼ばれた編集者は背中を丸め、揉み手をせんばかりにへりくだり、
「へへへへへ。豪徳先生。どうかよろしくお願いしやす。先生のお力で、わが凡要社に、たくさんの良い作家を引き当ててください」
「おお、解っとる、解ってる、大船に乗った気でいなさい。この豪徳はな、伊達にこの業界で人脈を持っているわけじゃないのだ」
片芦は豪徳を席へ案内しながら、
「――で、先生。本格推理作家部門ですが、誰に投票すればよろしいでしょうか」
と、尋ねた。
「本格?」と、豪徳はゲジゲジのような眉毛を片方つり上げ、「何が本格だ。あんなたいして売れない物はやめたらどうだ。どうせ、ベストセラーなんか出っこないんだから。それより、お軽いトラベル・ミステリーの方がいいぞ。それもだな、テレビの二時間ドラマの原作になるような奴だ」
「それはそうなんですが、一応、白鯨ブックスでは、広義のミステリー叢書をうたっているものですから、何冊かに一冊は、本格推理も入れたいんでございますよ。ところが、うちの編集部は、そちらの方面にはうといものでして……」
「つまり、島田荘司やその子分どもの長編が欲しいと言うのだな」
「へい。そのとおりでごぜいますだ。お代官様」
「解った。そんなのだって、俺が一声かければ簡単なことだ」
「お頼みいたします」
と、片芦は深々とお辞儀をし、参列者席の一番中央に豪徳を座らせた。彼はその横に腰を下ろし、鞄の中から缶ビールを取り出して豪徳に手渡した。そして、小ずるそうに微笑むと、
「ところで、豪徳先生。前々からお願いしておりました、存財四五郎先生の書き下ろし長編の方はいかがでしょうか。我が社で、年間、三冊執筆していただく件は、御承諾いただけたんでしょうか」
すると、豪徳はふんぞり返ってビールを一口飲み、
「うむ。それがだな。二冊なら書けるというんだ。何しろ、存財君は超売れっ子だろう。他社でも引っ張りだこなんだ。スケジュールの調整がつかないんだな」
「そこを何とか、豪徳先生のお力で――」
「一冊を二冊に増やしただけでも、この俺様の功績なんだが――」
「はい。もちろん、それは重々承知しております」
「そう言えば、存財君は、今度、どこか温泉旅行にでも行きたいと行ってたなあ。彼はスキーが好きだから、北海道あたりへ行って、ついでに温泉に入れるといいだろうなあ」
「豪徳先生もスキーをなさるので?」
「いいや。俺はあんな面倒なものはやらん。だから、温泉に浸かっていることにするよ。それから、俺はホテルよりも、高級和風旅館が好みだな。落ち着けるから」
「解りました」と、片芦は胸を拳で叩いた。「もちろん、取材旅行ということになれば、当社の方で全面的に費用等の面倒は見させていただきます。ただ、私は寒い所が苦手ですし、スキーもできませんので、できれば、ゴルフと温泉などという組み合わせはいかがでしょうか。九州の別府にですね、実に良い温泉旅館があるんですよ」
「おお、それはいいな。存財君も俺も、ゴルフは大好きだ」
「じゃ、御一緒ということで――」
「うむ。君がそんなに頼むなら、俺も同行しないわけにはいかないな。何しろ、俺は存財君の親友だからな。忙しい身だが、付いていってやろう。銀座の《SM》のママや女の子たちも呼べるといいな。夜は宴会で大騒ぎだ。うひひひひ――」
彼らの後ろの席に座り、二人の話を盗み聞きしていたカースケ、もうそれ以上耐えられなかった。聞けば聞くほどムカムカして、胸が悪くなった。
〈まったく、何て奴なんだ!〉
彼は静かにそこを離れると、鈴木の所まで戻った。
「――おう、遅かったじゃないか、カースケ」と、加賀と話をしていた鈴木が言った。「どうだ、成果はあったか」
「それが、あまりないんです」
と、カースケは正直に言い、彼らに缶コーヒーを渡した。そして、一応は仕入れた情報を鈴木に伝えた。
「そうか。まあ、仕方がない。どこも、抽選までは秘密保持に躍起になっているからな」
カースケは怒られることを覚悟していたのだが、鈴木はさっぱりとした顔で頷いた。
「ほら、君たち。いよいよ、ドラフト会議が始まるぞ」
と、加賀が姿勢を正して舞台の方を見たので、鈴木とカースケも椅子に座り直した。舞台の上には、作家用のブースが一列に横に並び、一回目の抽選対象となる作家や、その代理人が座っている。その背後には、派手な電光掲示板や、会場の風景を映している巨大なモニターがあった。
加賀と鈴木が、揃って上着の胸ポケットからPHSを取り出した。二人は電源を確認する。カースケは不思議に思って尋ねた。
「鈴木先輩。それ、何に使うんですか」
「ああ、これか。抽選が始まったら、このPHSを使って、対象となった作家の先生に投票するのさ。会社の登録番号と、先生の個別番号を打ち込むんだ。そうして、くじ引きが行なわれ、当選した会社の名が、あそこの電光掲示板に表示されるという仕組みなんだよ。これだと、非常にスピーディーに議事が進行する」
「ずいぶん、進歩的な方法でやっているんですね」
と、カースケは驚いた。それから、彼はパンフレットを見て質問した。
「先輩。最初の抽選は、新人作家たちなのですね」
「そうだ。去年、江戸川乱歩賞とか、横溝正史賞とか、鮎川哲也賞とかでデビューした作家たちを抽選するんだ。うまくすれば、彼らの第二作を自分たちの会社で出版できるかもしれん。新人賞から出てきた作家は将来有望だから、どこの社も虎視眈々と狙っているのだよ」
「だったら、乱歩賞受賞作家で決まりですね」
「ところがそうもいかん。乱歩賞作家の場合、講談社の世話が行き届いているから、ほとんど二作目も講談社から出ると決まっている。逆に、サントリー・ミステリー大賞とか、鮎川賞は狙い目だな。二作目が他社から出るケースも多いので、新人作家を獲得するチャンスだ」
「なるほど。それで、鈴木先輩は誰を狙っているんです?」
鈴木は加賀に聞こえないよう、カースケの耳元で囁いた。
「去年の鮎川賞を獲った{ルビ あすかべかつのり}飛鳥部勝則{/ルビ}先生だよ。物語の線は細いが、あの図象学ミステリーという趣向は面白かった。うちの奇譚社ノベルスにはぴったりだ」
「解りました」と、カースケは頷き、再度パンフレットを見て、「そして、午後に行なわれるベテラン作家の抽選が、今日の目玉であるわけなのですね」
「そのとおりだ。そのドラフトで勝たなくてはならない。絶対にお目当ての先生を引き当てるのだ」
「誰にしますか。赤川次郎先生ですか、内田康夫先生ですか、森村誠一先生ですか。当てれば、来年のベストセラーは確実ですよ」
すると、鈴木は顔を横に振って、
「そうしたいのは山々だが、うちでは無理だ」
「どうしてです?」
「競争率が高すぎる。ベストセラー作家には、多数の会社が投票する。引き当てればいいが、はずれてみろ、目も当てられん。うちのような小出版社はそんな危険は犯せないのだ。確実な投票をするしかない」
「じゃあ、芦辺拓先生とか北森鴻先生とかの若手はどうです」
「マニアの評価は高いけれど、もう少し部数がはけるといいんだがな」
「じゃあ、島田荘司先生はどうです。売れ行きも素晴らしいし、評価も高いですからね」
「島田先生の原稿は喉から手が出るほど欲しいさ。先生の御手洗ものや吉敷ものは途轍もなく面白いし、売れるのも解っている――しかし、一つだけ問題があるんだ」
「何です?」
「小説を書いてくださればいいが、もしも、『秋好事件』みたいな死刑囚問題を扱ったノンフィックションの原稿を渡されたらどうする。うちでは絶対に出せないぞ」
「何故ですか」
「ああいうのは、名誉毀損とかの訴訟沙汰を引き起こすことがあるんだ。大手の出版社なら裁判費用も出せるが、うちにはない」
「残念ですね」
「ああ、残念だ」
「僕は、山口雅也先生のキッド・ピストルズものが読みたいですね」
「山口先生は、未だ行方不明なんだ」
「行方不明? 初耳です」
「あれ、知らなかったか。有名な話だぞ。昨年、有栖川有栖先生、芦辺拓先生、二階堂黎人先生の三人が『鮎川哲也読本』という本を編んだだろう。その時に、編者が特別寄稿を北村薫先生にしか頼まなかったものだから、山口先生はむくれてしまってな、雲隠れをしてしまったんだよ。どうやら、イギリスでレコード漁りをしているという噂だがね」
「そう言えば、山口先生も、熱烈な鮎川哲也マニアでしたものね」
「そうさ。編者の先生方も、その辺を配慮してくれれば良かったのにな……」
鈴木はほとほと困ったという顔をした。
「だったら、やはり新本格の第一人者である綾辻行人先生を狙うしかないでしょう。『暗黒館の殺人』という新作を書く予定で、もう執筆に入っているはずですよ。それが奇譚社ノベルスで出たら大事件じゃありませんか」
「凄いな。大いに話題になるし、相当売れるだろうな――だが、綾辻先生にも投票はできないな。いや、しない方がいい」
「と言いますと?」
「『暗黒館の殺人』が本当に、来年中に刊行できると思うか。それまでに、確実に原稿が上がるのか。そんな確信を、お前はどうやったら持てるんだ、カースケ?」
「うーん」
「法月綸太郎先生も同じだ。ぜひうちで書いてもらいたいのだが、このドラフトで、わが社が先生方の出版権を抑えていられるのも一年間しかない。その間、先生方に原稿を書いてもらう努力を続けるのはいいが、書き上がらなかったりしたら大変だ。経費ばかりかかって利益がない。相当悲惨なことになるぞ」
「そうですか……」と、カースケは腕組みして考えた。「そうすると、新本格推理の作家ってみんな難しいですね。どの人も、本を出すインターバルが妙に長いですからね」
「そうなんだ」
「じゃあ、西澤保彦先生はどうですか。人気も鰻登りで、年間六冊も書く力を持っていますよ」
「ああ、俺もそう考えていたところだ。というか、新本格なら西澤先生しかないという感じだな。他にも早書きの人はいるが、うちのノベルスは{ルビ
こころざし}志{/ルビ}や質も落としたくないんでね」
「当然ですね。ただ売れりゃあいいってもんじゃないですし――」
ようやく、二人の相談がまとまった頃、ドラフト会議が本格的に始まった。照明が暗くなり、たくさんのスポットライトが舞台を照らす。電光掲示板が様々な色を発光し、タキシードを着た司会者が袖から勢い良く出てきた。
「――皆さん、お待たせしました。ただ今より、《一九九九年度、ミステリー・ドラフト会議》を開催いたします。今年、ノミネートされたミステリー作家の総勢は百二十三名、抽選に参加してくださた出版社の数は三十六社になります。おかげさまで大盛況と申せましょう。それでは、本格推理小説の新人部門から抽選を行ないますので、入札をされる編集者の方々は準備をお願いします!」
会場ががやがやと騒がしくなる。
舞台ではレーザー光線が飛び交い、派手な音楽が鳴り響き、京極系コスプレの若い男女がヒップホップ系音楽をバックに踊りまくる。電光掲示板には、《新人作家部門》という文字が浮き上がった。
踊り手が引っ込むと、ふたたび司会者が舞台中央に現われ、声高に紹介した。
「エントリー・ナンバー一番。昨年、原書房から『三〇〇〇年の密室』でデビューされた{ルビ
つかとうはじめ}柄刀一{/ルビ}先生! 北海道在住! 推薦者は、有栖川有栖先生と二階堂黎人先生でーす!」
舞台中央階段の上にスモークが噴き出し、黄金色の二枚扉をバニー・ガールが両側からあける。そして、名前を呼ばれた作家の柄刀一氏が緊張の面もちで出てきた。
「柄刀先生! こちらにどうぞ!」
司会者が呼びかけ、柄刀一氏はぎこちなく片手を上げて観客席にアピールしながら、階段を下りる。スラリと背の高い、理知的な顔をした人物だった。
簡単なインタビューがあり、その後、現在執筆中の作品や、今後の作品に関する構想などを作家自らが語る。出版社の編集たちは、それを参考に、彼に入札するかどうか最終的な判断を下すのだ。
そうした様子を見ながら、カースケは鈴木に尋ねた。
「先輩はどうするんですか。僕は、あの人は将来有望な作家だと思いますが」
「うむ。そうなんだけども、俺の仕入れた情報だと、講談社や角川書店ももうとっくに目を付けていて、契約金の提示などの接触も行なわれたらしい。そうなると、土壇場での逆指名もあり得るし、契約金が吊り上がるがら、うちでは手が出せない可能性もある」
「逆指名?」
「契約金の最低入札価格という制度があるんだよ。PHSで指名する際、それも打ち込む必要がある。そして、最低入札価格以上の出版社が出揃ったところで抽選が行なわれるわけだけど、二十歳以上の作家の場合には、逆指名も認められているんだ」
「つまり、大手の出版社は、契約金をちらつかせて先に話をつけてあるということですか」
「ああ」
「そうですか。悔しいですね」
「悔しいがしょうがない。各部門とも、入札権は二回ずつしかないからな。大事に指名しなくてはならない――」
新人作家の部門が終わると、昼休みの休憩時間になった。鈴木とカースケは購買所でパンと牛乳を買い、ロビーの椅子で昼食を取った。そこでもカースケは聞き耳を立て、他社がベテラン作家の誰を狙っているのか、できるかぎり情報収集に務めた。
3
いよいよ、作家生活二年以上、二十年未満の中堅作家の部門になった。舞台では作家の派手な紹介が続き、次々と指名が行なわれ、抽選の結果、出版社との新契約が成立していく。十人ほどの作家のドラフト会議が終わったが、それまでで一番入札数の多かった作家は、予想どおり京極夏彦氏であった。加賀の水晶出版社を含めた二十五社が獲得に名乗りを上げ、逆指名はなく、団子公団社の{ルビ
よいやま}酔山{/ルビ}という出版部長がくじ引きで指名権を勝ち取った。そして、契約金六億八千万(推定)が提示され、即座に出版権の締結がなされたのである。
「すごいなあ……」と、カースケは心底から感心した。「やっぱり売れっ子作家は違いますねえ」
鈴木はじたんだ踏んで、
「ああ、世の中は不公平だあ! どうして、この世に京極夏彦が一人しかいないんだあ! 俺にも一人くらいくれよおお!」
と、嘆くのであった。
カースケは苦笑しながら、鈴木の横の加賀に、
「加賀さん、今の指名は惜しかったですね。せっかく水晶出版社は二位を引き当てたのに」
ところが、加賀は満足げな顔で、
「ははは。いいや、大丈夫だよ、カースケ君。むしろ私はね、一位指名じゃなくて助かったと思っているのさ」
と、意外な返事をしたのである。
「と言いますと?」
「一位の場合には、契約金を払わなくてはならないが、二位以下は必要ない。京極先生は大作をお書きになるが、筆も早い。うまくすれば、年内にもう一冊新作を書いてくださるだろう。そうすれば、その本はうちのものだからね」
加賀はしてやったりという顔で、早くも次の指名の準備を始めた。カースケはそういう駆け引きがあったのかと、このドラフト会議の奥深さや難しさや楽しさに、あらためて感じ入ったである。
4
ドラフト会議の第三部は、作家生活二十年以上のベテラン作家部門であった。また、その次の第四部は、冒険・ハードボイルド作家部門だった。舞台の上には、プロレスで使われるような金網で囲まれたリングが設置される。もちろん、ここで、作家同士の金網デスマッチが行なわれ、それが、投票の参考になるのだ。言うまでもなく、冒険・ハードボイルドの作家は肉弾的でタフな上、喧嘩にも強くなくてはならない。弱々しかったり病的な作家など、小説のイメージが壊れて売れ行きが落ちる。
第五部はファンタジー部門だ。ここでは、ファッション審査と技能審査に重きが置かれる。作家全員が思い思いの美しい甲冑を身につけ、長剣や槍や盾を手にして出てくる。『琥珀の城の殺人』の篠田真由美などは、兜に七色の鳥の羽を付け、白馬にまたがって、舞台の袖から堂々と出てきたほどだ。
そして、甲冑を着たこれらの作家たちによる、一対一の決闘という注目の催しものがある。これが技能審査だ。聞くところによると、本物の武器が使われるために、昨年は数名の負傷者が出たそうだった。しかも、この試合には、イギリスのブックメーカーが掛け率を設定しているので、ギャンブルとしても人気があった。
第六部は、今年新設されたホラー作家部門であった。二十五メートル・プールにゲル状のスライムが流し入れられ、その中を小説家が最後まで泳ぎきれるかどうか試される。何人か途中で溺れてしまう者もいたが、幸い死者は出なかった。
5
夕方の休憩時間が終わると、もう午後七時になっていた。食堂で軽い夕食を取ったカースケと鈴木は、あらためて会場に戻った。
「さあ、カースケ。今日のメイン・イベントだ。《{ルビ
ささみず}笹水{/}氏のオークション》が始まるぞ!」
と、鈴木は武者震いをして言った。
「笹水氏?」
カースケは尋ねた。
「うん。笹水{ルビ くりす}久利須{/ルビ}という元華族出の金持ちが行なうオークションだ。この道五十年のミステリー・マニアでね、その人が資財をなげうって、十二年前に始めたのさ。ようするに、ミステリー作家の来年の出版権を競りに賭けるわけだ。この歴史あるオークションに出られる作家は一部の人気作家に限られるから、指名されたら非常に名誉なことなんだよ。また、お目当ての作家を競り落とした編集者も、みんなからその幸運と優秀性において尊敬される。だから、業界中の人間が目の色を変えて、このオークションの行方を見守っているのさ」
「なるほど。盛り上がりそうな催しですね」と、カースケは熱を込めて頷いた。「それで、今回は誰が競りに出ているんですか」
「『サマー・アポカリプス』や『ヴァンパイヤー戦争』で有名な、笠井潔先生だよ」
鈴木が畳みかけるように言った。
「え、本当ですか!」と、カースケは喜び顔で驚く。「笠井潔先生と言えば、日本文学全体の有り様に幻滅して、何年か前に八ヶ岳山麓に隠遁してしまった伝説の作家じゃありませんか。霞を食べて文章を書くという、ミステリー仙人とも呼ばれている人でしょう」
「そのとおり。だけど本当なのさ。それも、俺が得た特別情報によれば、以前、ある雑誌に連載したままだった矢吹カケル・シリーズの大作、『オイディプス症候群』がいよいよ完成するらしいのだ。つまり、今回の競りは、笠井先生の待望の新作に対するものだと考えていい」
「じゃあ、ぜひ、その権利を競り落としましょう!」
カースケは身を乗り出した。
「ああ、もちろんだ。俺も真剣にやるぞ。社運を賭けるつもりだ。社長からも、かなりの額まで出して良いという許可を得ているからな!」
鈴木も興奮ぎみに言う。
カースケはちょっと思案すると、
「鈴木先輩。このオークションにも、何か特別な規約とかローカル・ルールがあるんですか。やはり、出版権は一年限りなんですか」
「そうだよ。一年間限り有効さ。それから、ドラフト会議と違うのは、あっちは出版社と作家の契約だが、こっちは、作家と編集者の一対一の契約になる。つまり、ここで競り落とされた作家の担当には、競り落とした編集者が必ず付かなくてはならない。また逆に、作家の方には、編集者を忌避する権利がある。仕事を始めてみて、気に入らない編集者だったら、途中で{ルビ
くび}馘{/ルビ}にすることができるんだ」
それを聞いて、カースケの目がキラリと輝いた。
「もしも、担当編集者が途中で病気になって、小説家のお世話ができなくなったらどうするんです?」
「契約は失効する」
「作家がこの編集者はだめだと判断しても、契約は無効になるんですね。その場合には、競り金はどうなります?」
「一度競ったお金はどんなことがあっても戻ってこない。何故なら、笹水氏が運営している、ミステリー迎賓館に寄付されるからだ。知っているだろう、外来のミステリー関係者を遇するために建てられたお城のような建物を」
「そうですか――」
と、カースケは頷き、にんまりする。
「何だ?」
鈴木は怪訝な顔で尋ねる。
「何でもありません」と、カースケは惚けて、「で、競争率は高いですか」
「もちろん、高いさ」と、答えた鈴木は舞台の方を指さし、「――ほら、最前列を見てみろ。笠井先生と過去に仕事をしたことがある編集者が雁首を揃えているぞ。右端から、高文社の{ルビ
げたむら}下駄村{/ルビ}氏、遅河書房の{ルビ
ぶせ}武背{/ルビ}氏、団子公団社の{ルビ
よいやま}酔山{/ルビ}氏、住営社の{ルビ
おちくぼ}落久保{/ルビ}氏、薔薇書房の{ルビ
いたげ}板下{/ルビ}氏だ」
――と、その時だった。
彼らのすぐ後ろで、聞き知っている声が聞こえたのだった。カースケが振り返ると、そこの座席に腰掛けたのは、あの凡要社の片芦編集者と、評論家の豪徳であった。
「――おいおい、片芦君よ」と、豪徳の嫌味な声が響き渡った。「東京に住んでいない笠井潔なんていう作家を{ルビ
せ}競{/ルビ}ったってしょうがいないだろうが。こんな所はさっさと退散して、銀座か新橋へでも繰り出さないか」
「ですが、豪徳先生。仕方がないんですよ。うちの部長が笠井先生の評論のファンでしてね、必ずオークションに参加してこいとの命令なんですよ」
「何が評論だ。作家が、小説を書く片手間にやるようなことじゃないぞ。評論活動というのは神聖にして学術的なのだ。両立できるほど甘いもんじゃない」
豪徳は吐き捨てるように言い、葉巻きを口にくわえて火を点けた。
白くて臭い煙が流れてきて、タバコを吸わないカースケはむせ返りそうになった。そして、それが、彼の怒りを爆発させる原動力となった。
「豪徳さん!」
と、気づいた時には、立ち上がったカースケは、椅子越しに手を伸ばし、相手の口から葉巻きをもぎ取っていた。
「この会場は禁煙ですよ!」カースケは、それを床に投げ捨て、足でもみ消した。「あなたは、そんな最低限の道徳心もないのですか。それに、何が小説家の片手間ですか。普段、いいかげんな書評ばかり書いて糊口を凌いでいて、しかも、代表著作と言ったって、あなたのは印象書評をまとめただけでしょう。そんな業績しかないくせに、他人のことをどうのこうの批判できる立場ですか!」
「な、何! き、貴様!」
と、豪徳は真っ赤になり、怒りに顔を震わせながら、カースケを睨みつけた。
カースケは腕組みして、豪徳を見下ろすと、
「ほうら、見てごらんなさい。あなたは、僕の名前さえろくに覚えていない。ミジンコほどの記憶力もないんだから困っちゃう。いいですか。もう一度お教えしましょう。僕の名前はカースケです。この前、あなたと《舞羅運》で、ミステリーのブラインド・テストをやったカースケですよ」
「き、貴様!」
と、豪徳は泡を吹く勢いで言った。そして、拳を握りしめて立ち上がった。
「お前なんぞが、ここに、何しに来た! ここはな、素人が顔を出すような所じゃないんだぞ!」
それを聞いて、横から鈴木が慇懃な態度で口を挟んだ。
「これはこれは豪徳先生。どうも失礼しました。私、前に一度お目にかかった奇譚社の鈴木でございます。この者は私の大学の後輩でして、本日は、我が社の顧問としてこちらに来てもらっています」
「何だと? お前の所は、こんなド素人に意見を聞いているというのか! まったくくだらない出版社だな!」
豪徳は軽蔑したように怒鳴った。
「彼は素人かもしれませんが、率直な意見を持っています」
「そんなものが役に立つか!」豪徳は毒づくと、面食らっている凡要社の片芦に、「おい、片芦君。行くぞ。胸くそ悪い。こんな所に一秒とていられるか!」
と、立ち去ろうとしした。
すると、カースケは鈴木の方を向いて、わざとらしく、
「良かったですね、鈴木さん。凡要社さんは、オークションに参加しないようですよ。これで、笠井先生の小説は僕らのものだ。どうやら、評論家の豪徳氏は、いつものごとく勉強不足で、笠井先生がカケル・シリーズの次の大作を完成されたのを御存知ないらしい。競争相手が減って、大いに助かりましたよね!」
と、早口にまくし立てたのである。
すると、豪徳の顔がふぐのように膨れ上がり、肌の色が赤から青に変色した。
「ば、馬鹿にするな! そんなことぐらい、俺様だって知っているさ! 何を戯けたことを!」
「え、そうなんですか!」と、カースケは歓声を上げると、「まあ、どうでもいいですよ、豪徳さん。僕らは僕らのやり方でオークションに参加します。どんなことがあっても、他の人には負けません。今回は、奇譚社も社運をかけて笠井先生を競り落とすつもりなんですからね。笠井先生の待望の新作は、来年度の話題をさらって、とても売れるだろうなあ!」
豪徳はますます怒りにかられ、全身をブルブルと震わせた。
「若造! この俺様をここまで怒らせたからには、覚悟はできているんだろうな!」
「覚悟って何ですか」
カースケは空惚けた。
ようやく事態を把握した凡要社の片芦が、横から鈴木に文句を言った。
「奇譚社の鈴木さん。あなたの連れてきた顧問の若者は、どうやら、礼儀知らずのようですな。有名で著名で公明な評論家の豪徳先生に向かって、こんな生意気な口を利くなんて」
「ああ、どうもすみません……」
と、鈴木は軽く頭を下げたが、あまり恐縮している風ではなかった。
しかし、片芦は笠に着て、
「まったく、おたくのような弱小出版社に絡まれるなんて、我が社も地に落ちたものだ」
などと嫌味を言った。
カースケはそれを耳にした瞬間、
「ミステリー好きに、大出版社も中小出版社もないでしょう」と、言い返した。そして、相手が返事をするよりも早く、「それよりも、ねえ、豪徳さんに片芦さん。良かったら、今度のオークションで、僕たちと勝負をしませんか」
と、提案をした。
「勝負だと!」
豪徳は目をむいて怒鳴った。
「ええ。あなた方が笠井氏の出版権をせり落としたら、僕は、僕の宝物である《まだらの紐》の蛇の抜け殻の皮を上げますよ。もしも、あなた方が負けたら、何かあなたの宝物をもらいたいものですね」
「良かろう!」と、豪徳は血走った目でカースケを睨んだ。「どうせ、オークションで笠井潔を競り落とすつもりだったんだからな――それならば、俺様の方は、ダシール・ハメットが愛用していた灰皿を賭けに出してやる。一九二〇年代のシカゴ製だ。それでどうだ!」
「ええ、いいですね」
カースケはにんまりとした。
「どうですか、やりますか」
と、鈴木も、凡要社の片芦に尋ねる。
片芦は挑戦的な目で頷き、
「もちろん、かまわないよ。勝つのはこっちと決まっているからね」
と、自信まんまんに返事をする。そして、自分の顧問の方を向き、
「さあ、豪徳先生。こんな弱小出版のやつらを相手にするのはもうやめましょう。オークションが始まります。もっと前で参加しましょう――」
そう言って、二人は前席へ移動していってしまった。
彼らが充分に離れるのを待って、鈴木が半分あきれたように言った。
「――おい、カースケ。お前は、ずいぶん無謀なことをするな。豪徳と言えば、実力はともかく、この業界ではずいぶんと顔を利かせているお偉い評論家なんだぞ」
カースケは頭の後ろを照れたようにかきながら、椅子に座り、
「へへへ。知ってますよ。でもね、読者にすれば、良い評論か悪い評論かってことが大事なんであって、評論家のキャリアや顔の広さなんてぜんぜん関係ありませんよ。だいいち、豪徳みたいにミステリーの本質も解らないミステリー評論家なんて、生ゴミ以下の存在ですからね――や、始まるぞ!」
カースケが前を見たので、鈴木もつられて舞台の方へ視線をやった。タキシード姿にモノクルを付け、髪をオールバックにし、カイゼル髭を生やした老人が出てきて、優雅にお辞儀をした。
「あれが、競り売り人の笹水氏だ。ふだんは軽井沢の豪邸に隠れ住んでいて、年に一度だけ、このオークションで顔を見せるんだよ。ミステリーの本や雑誌の蒐集にかけては伝説の人だ」
「――どうも、お待たせしました、皆さん!」
笹水の声は玲瓏と会場に響き渡り、簡単な前口上の後、すぐにオークションが開始された。参加者の席は、水を打ったように静かになっていた。異様なほどの熱気と期待感が溢れている。巨大スクリーンに、ピッケルを片手に持ち、南アルプスの断崖をよじ登ろうとしている登山姿の笠井潔氏が映った。
「鈴木さん。笠井先生の出版権は、いくらくらいで競り落とされると思いますか」
「そうだな。規定の二十万円から始まって、一千万円の攻防というところじゃないかな。そこまでなら、何とかうちも付いていけるんだが……」
「解りました」
と、カースケは頷いた。
競り売り人は競り台を木槌を叩き、静粛を求めた。これが、オークション開始の合図であった。会場全体にさらなる緊張が走る。
「――それでは、今世紀、日本が生んだ世紀のミステリー作家、笠井潔先生の来年の出版権を競りに賭けます。最低価格は二十万円。ここからお願いします」
競り売り人が愛想良く言うと、前の方で誰かが手を上げて、
「三十万円!」
と、さっそく声をかけた。
その途端、間髪入れず、カースケが大声で叫んだ。
「三百万!」
会場が激しくどよめいた。というのも、普通、こうした競りは、順繰りに下から値を付けていくものだからである。
「三百万円!?」と、驚いた競り売り人が、復唱した。「三百万円です! 他にありますか!」
カースケは皆の目が自分に集まったのを感じると、立ち上がって、わざとすました顔をした。こちらを見ている目の中には、豪徳と片芦の憎悪に満ちた視線もあった。
「三百十万!」
低い声でそう応じたのは豪徳だった。
「五百万!」
カースケは平気な顔で値をつり上げる。
横にいる鈴木は、何が起こったのかよく解らず、茫然としている。
豪徳は一瞬振り向き、歯ぎしりしながら、
「五百五十万!」
と、競り売り人に告げる。
「五百五十万が出ました! 他には!?」
会場は興奮の坩堝と化した。競り売り人も明らかに気持ちが高揚している。年齢が年齢だけに、血圧が心配である。
「六百万!」
そう言ったのは、光文社の下駄村という編集者であった。この急激な競りに対して、彼もあわてて参入したのである。
「六百十万!」
住営社の落久保編集者である。
「七百万円!」
しかし、カースケはまったく動じることになく、そう宣言した。
こちらを怖い顔で睨む豪徳の顔が、また赤く膨れ上がった。
「七百三十万だ!」
豪徳が怒鳴り、
「八百五十万!」
と、カースケが応じる。
「九百万!」
「千二百万!」
「千二百万円の大台が出ましたあ!」
二人の応酬に、競り売り人はあらん限りの声で叫んだ。
カースケは、ニヤニヤしながら豪徳や凡要社の片芦の方を見ると、べーと舌を突き出した。そして、
「千三百万!」
と、また値をつり上げた。
怒り心頭に走った豪徳はスクッと立ち上がり、太い手を振り回して、
「千三百五十万だ! 解ったか!」
と、大声を出した。
すぐに、カースケはその上を行く。
「千三百八十万!」
「千四百万円だ! 畜生!」
豪徳が力の限りに叫ぶ。
会場の他の者たちは、もうすっかり、この二人の対決に見入っていた。こんな緊迫した競りは、ここ数年来まったくなかったことだった。いったいどこまで値が上がるのか……。
ところが、その瞬間、カースケは肩を小さくすくめると、首を左右に振りながら、スッと椅子に座ったのだった。
「さあ、千四百万円が出ました! 笠井潔先生の新作小説の出版権に千四百万です! 他にはいませんか! 千四百万円以上はいませんか!」
競り売り人が懸命に煽るが、誰も声を上げない。それはそうである。鈴木がカースケに言ったとおり、この競りにおいては、本当は上限一千万円くらいが妥当な額だったからだ。
「売った!」
と、競り売り人は鋭く声を発し、同時に、木槌を力一杯たたき付けた。会場から驚きの声と拍手が湧き起こる。この瞬間に、来年度の笠井潔氏の出版権は、凡要社の片芦編集者の下に落ちたのである。
前の方で、立ち上がった豪徳と片芦が、周囲の万雷の拍手の中、強い握手を交わす。しかも、勝ち誇った豪徳は、カースケの方を向き、
「どうだ、若造! 思い知ったか! 賭けは俺様の勝ちだ! 素人の癖に、この豪徳様に戦いを挑むとは百年早いわ! 解ったら、《まだらの紐》の蛇の抜け殻の皮を、さっさと俺に寄越せ! そして二度と、このミステリー業界のことに口を出すんじゃないぞ! わっはははは!」
と、高笑いをしたのである。
「ああ、何てことだ!」と、カースケは椅子から滑り落ち、ガクリと膝を突いた。「ぼ、僕が負けるなんて……」
「これが当然の結果だ!」ますます豪徳は有頂天になった。「所詮、日本は商業主義の国だ。資本力がある方が必ず勝ち残るのだ! 解ったら、さっさと立ち去るがいい! ざまあみろ! この素人めが!」
豪徳は有頂天になってそれだけ言うと、競り売り人に誘われて、片芦氏と共に舞台の方へ向かった。観衆も、敗者のカースケには興味をなくし、皆、晴れがましく壇上へ上がる豪徳の方へ視線を移していた。
「皆さん、凡要社の片芦編集者と、評論家の豪徳氏に、もう一度拍手を!」
競り売り人が威勢よく言い、万雷の拍手が会場を包んだ。
それを一瞥すると、カースケは手をはたきながら、さっさと立ち上がった。
「――さて、オークションも終わりましたね。先輩、帰りましょうか」
「何だ、今のショックの表情は、単なるポーズだったのか」
鈴木はあきれて尋ねた。
「当たり前ですよ」カースケはクスリと笑う。「オークションの勝利者に、ちょっとだけ花を持たせたわけです」
「それにしても、どうするんだ、カースケ?」と、パンフレットを鞄に片づけながら、鈴木が尋ねる。「競りに負けたからには、豪徳氏に、お前の宝物を差し出さなくてはならないぞ」
カースケは小さく肩をすくめると、
「ええ。約束は約束ですからね。でも、あんな物は、喜んで豪徳氏に進呈しますよ。何しろ、蛇は何回でも脱皮するんですからね。一つくらい皮を渡しても、そうおしくはありません」
「何だ、そうか。お前って、意外にずるい奴だな」
と、鈴木はニヤリとする。
「それに、あの二人には、四百万円もの余分な出費をさせてやりましたからね。それだけでも、僕の胸はスッとしました」
カースケも同じくニヤリとする。
「ははは。なるほどな。お前のあの無茶な競り方は、それが狙いだったのか。最初に豪徳を挑発しておき、競りが始まると同時に値段をいきなりつり上げ、奴がむきになるよう仕向けたんだな。そして、最後はわざと高い値段で、あいつらに落札させたわけか」
「そういうことです。まあ、どこで引くかはけっこうスリルがありましたけれどね。失敗すると、こっちが高い値で競り落としかねませんでしたから――」
さっぱりした顔で、二人は出口の方へ歩きだした。壇上では、凡要社の鈴木と豪徳が、競り売り人の笹水氏と挨拶を交わし、契約書の締結をしようとしている。会場は相変わらずひどく湧いていたが、カースケも鈴木も二度と振り返ることはなかった。
そんな彼らに気づいた者がいて、能天気な観衆の声がかかる――。
「よく戦ったぞ! 来年もまた来いよ!」
《五月二十二土曜日 カースケとミユキはゲームで遊ぶ》
土曜日の夜、カースケとミユキは、カースケのアパートで本を読んでいた。一昨日、ようやく届けられた島田荘司氏の新刊、『涙流れるままに』である。
同じ本を二セットも買うのは無駄かと思ったのだが、こうして二人でいっぺんに読めるのだから、ぜんぜん無駄ではなかった。ヘルス・メーターの方だって、健康管理に役立つ。今は、脈拍や心拍を測るセンサーをミユキが自分の体に取り付けている。
しかも、実際の発売日より一ヵ月も前にこれだけの傑作を読めるのだから、ミステリー好きには堪えられない。昼過ぎから、夕食の時間を別として、二人はずっとこの小説に没頭していた。
時計が午後十時をさす頃、ようやくミユキが背伸びをして、目をパチパチさせた。彼女は本を開いたままテーブルの上に伏せると、
「ねえ、カースケさん。少し他のことをしない?」
と、恋人に声をかけた。
「他のこと?」と、カースケも栞を本の間に挟んで言う。「いいよ。何をする?」
「あのね。カースケさんがこの前教えてくれた、《ミステリー{ルビ
デュエル}決闘{/ルビ}カード・ゲーム》をやりましょうよ」
ミユキが言ったのは、アメリカから始まって日本でも人気がある《マジック・アンド・ギャザリング》というカード・ゲームのミステリー版であった。最近、一部のマニアの間で大流行しているものである。子供たちの間では、ポケモン・カードが蔓延している。
「うん。やろう!」
カースケは嬉しそうに言うと、常備してあるリュックサックから、デッキを二組と決闘シートを取り出した。デッキというのは、何千種類もある様々なカードの中から、自分の使いやすい物を四十枚集めた一揃いのことである。この二組のデッキも、もちろん、カースケが自分の好みで組み合わせたものだった。
「ミユキ。どっちでも好きなデッキを取っていいよ。片方のデッキがロジック系を中心として揃えたもの。もう一つがトリック系を中心に揃えたものだ」
「私は、北村薫さんや有栖川有栖さんが好きだから、ロジック系デッキがいい」
「じゃあ、僕がトリック系のカードだ。容赦はしないぞ」
「望むところよ」
二人はそれぞれのデッキをよくシャッフルし、まず五枚ずつの手札を取った。プレーヤーはそれぞれ二〇〇〇点をライフ・ポイントとして持ち、カードによる戦いを順次繰り広げて、その点数がなくなった方が負けとなる。
「先攻は私ね――」
と、ミユキは一枚のカードを抜き、二人の間に広げたビニール製の決闘シートの上に出した。これには、江戸川乱歩のパノラマ島と横溝正史の獄門島の写実的な地図が描いてある。プレーヤーはそれぞれの島を陣地として戦うのだ。
「行くわよ、カースケさん。私のメイン・カードはクイーンの《九尾の猫》。攻撃力一九〇〇。守備力一〇〇〇。このモンスターは連続殺人鬼だから、攻撃力は強いわよ」
カースケはニヤリとすると、
「連続殺人鬼で来たなら、こっちも殺人鬼で勝負だ。メイン・カードは綾辻行人のズバリ《殺人鬼》。攻撃力二三〇〇。守備力一七〇〇の大怪物だぞ。それから、複合カードとして、さらに《キリオン・スレイの剣》カードを出す。これは、ナイフや剣や刀を使う犯人の攻撃力を、一時的にプラス三〇〇点にするものだ。この二枚で攻撃! 二六〇〇点マイナス一九〇〇点で相手を撃破! 七〇〇点の勝ちだ!」
「ふふふ。カースケさん。甘いわよ。《九尾の狐》は正体が解らないのよ。だから、相手の攻撃力は半分になる。つまり、あなたのカードは一三〇〇点しか攻撃力がないわけ。だから、私のカードをやっつけることはできないわ」
「何だって!」
カースケはショックを受けた。うっかり忘れていたのだ。
「そんな!」
ミユキはクスクス笑い、それから余裕の顔で、手札を一枚場に晒らし、《九尾の猫》の横に置いた。
「私は、西澤保彦の《念力密室!》カードを出すわ。相手を密室の中に閉じこめ、念力で締め付けて、その攻撃力と守備力を五〇〇点ずつマスナスさせるカードよ。と言うことは、カースケさんの《殺人鬼》カードの攻撃力は一八〇〇点になるわね。《九尾の猫》と《念力密室!》で攻撃! 《殺人鬼》を撃破! カースケさんはマイナス一〇〇点で、ライフ・ポイントは一九〇〇に下がったわね」
「くっ。よくもやったな、ミユキ!」
カースケは悔しさに歯ぎしりした。そして、小考すると、
「じゃあ、僕の今度のメイン・カードは《ドグラ・マグラ》だぞ。攻撃力一二〇〇点。守備力は二二〇〇点だ。モンスターは監獄の中に入っているから、守りは恐ろしくかたいからな。これを防衛状態で出す。しかも、攻撃してきた相手の頭を混乱させるのだ!」
彼は、そのカードを《防衛》表示の印として、横向きに置いた。
「そんな物を出しても無駄よ」
「何とでも言え!」
「今度の{ルビ ターン}回{/ルビ}では、私はカードを一枚、場に伏せるわ」
ミユキは言ったとおり、抜いたカードを裏返しのまま、また《九尾の狐》の横に置いた。
「罠カードか{ルビ トリック}仕掛け{/ルビ}カードだな。それなら、こっちの回では、もう一枚モンスター・カードを出そう。僕の手持ちの中で最高のカード、山口雅也の《十三人の探偵士》カードだ! 十三人の探偵がいっぺんに攻撃を繰り出すんだ。いくら君のカードだって、これにはかなうまい。何しろ、守備力は三〇だが、攻撃力は五六〇〇もある。攻撃! 《九尾の猫》を撃破! 二八〇〇マイナス一九〇〇で、九〇〇点の減点さ!」
しかし、ミユキはまったく平気な顔で、
「カースケさん。あなたの攻撃なんか、こっちは初めからお見通しよ。おほほほほぼ」
「な、何だって!?」
「場に伏せたカードを見せてあげましょうか」と、ミユキは、それをめくった。「あなたが山口雅也のカードで来るなら、こっちは、西澤保彦カードで対抗するわ。《七回死んだ男》。死者復活のカードを、事前に場に用意してあったんだから!」
「うわあ!」
「《七回死んだ男》カードの効力によって、《九尾の猫》は七回生き返るのよ!」
「まさか! 何てことだ! そんな手があったとは!」
カースケは頭をかかえた。
「だから、私はロジック系カードを選んだのよ。頭脳の勝利ね」
「何を! まだまだだ! そっちが復活カードを使うなら、こっちだってそうだ! 山口雅也の《生ける屍》カードを出してやる! どうだ! これで、ゾンビ化して《殺人鬼》カードが復活すのだあ!」
「あ、そんなカードを持っていたなんて知らなかったわ! この前までなかったじゃない! ひきょうよ!」
ミユキは金切り声を上げた。
「はっはっはっ。一昨日、高田馬場のBIGBOXの前でミユキを待っている時に、ダースモールのTシャツを着たオーモリ某とかいう怪しげな{ルビ
バイヤー}男{/ルビ}が近づいてきて、闇販売のミステリー・カードがあるがどうかと耳打ちされたのさ。それを何枚か買っておいたわけさ」
「まあ。高かったんじゃないの?」
「それほどでもないよ。その代わり、その男、すごく口がうまくてさ、妙な内容のノベルスを一冊押しつけられたけどね」
「ようし。それなら、私は北森鴻の《狐罠》カードを出してやる。そっちが攻撃してきた途端、罠に捕まって、モンスターは撃破されるのよ」
「ええ!? すると、こっちは防衛一辺倒かよお――解った。こうなったら、江戸川乱歩の《黄金仮面》を防衛で出してやる。攻撃力一〇〇〇。守備力一五〇〇だ」
「そんな弱いカードを出していいの。遠慮しないわよ」
「余計なお世話だ」
「だったら、私は《九尾の猫》で《黄金仮面》を攻撃! 九〇〇点の勝ちね!」
「はっはっはっ! ところが、《黄金仮面》は、死ぬ前に相手の{ルビ
トリック}仕掛け{/ルビ}カードを盗むことができるんだ。つまり、《七回死んだ男》の効力はすべてこちらのものになる!」
「ああ、やったわね!」と、ミユキは怒り、「だったらいいわよ。私はストックから一枚めくって――ほら、やった! この《帝王死す》カードを出してやる! これは、対戦者の出している一番強いモンスターを一撃で殺してしまうカードなんだから!」
「どっひゃあ! よくもそんなカードを引いたものだ。まいったなあ――《殺人鬼》が使えないなら、次は《蜘蛛男》カードだ」
「いいもん。私の手には《絡新婦》カードがあるんだから。それで五分五分よ。それに、《水晶のピラミッド》カードで、そっちを水攻めしてやるわ!」
「そんな攻撃は、この《鏡よ、鏡》カードの鏡効力で跳ね返してやる――」
と、その時電話が鳴ったので、カースケはテーブルの上に置いてあった子機を取り上げた。ミユキが聞き耳を立てると、どうやら相手は、奇譚社の鈴木のようであった。
「――はい。はい。解りました。それでは、また。はい。どうもありがとうございます」
話を終えると、カースケは子機のスイッチを切った。そして、
「キャッホー!」
と、いきなり奇声を上げ、万歳をしながら飛び上がったのだった。
「ど、どうしたの!?」
面食らったミユキは、狭い部屋の中を駆け回っているカースケに尋ねた。
カースケはミユキの側に座りなおすと、彼女の手を取って、
「やったぞ! やっぱり僕の読みどおりだった。鈴木先輩と僕はね、賭けに勝ったんだよ!」
「賭け? 何の賭け?」
「《ミステリー・ドラフト会議》における《速水氏のオークション》だよ。あのオークションで競り勝った凡要社の片芦氏と豪徳氏だけどね、新作の出版の打ち合わせで、八ヶ岳にいる笠井潔先生の所へ行ったところ、あっと言う間に外へ蹴り出されたそうなんだ。二人は、山の麓まで転がり落ちたらしい」
「どうして?」
「何故かと言えば、あの二人はスキーができないから、笠井先生をゴルフで接待しようとしたらしい。それで、九州への温泉旅行を持ちかけたら、その途端に笠井先生の不興を買ってしまい、追い出されたというわけなんだよ」
「まあ」
「つまりだね、解るかい、ミユキ――彼らがあのオークションで払った千四百万円という大金は、まったくの無駄金になったということなのさ。契約は無効になったんだ!」
「すごい!」
「笠井先生が大のスキー好きだというのは、ミステリー・ファンの間では常識になっている。また、笠井先生は、スキーのできる編集者としか付き合いをしないという話も聞いていた。
ところが、あの凡要社の片芦氏も豪徳氏もまったくスキーが滑れない。だから、彼らが笠井先生のへ顔を出しても、結局は気に入ってもらえず、新作小説は手に入らないだろうと推測したんだよ。それで僕は、オークションであんな無茶な競り方をしたんだ。そして、その推測がまさに的中したというわけさ」
「みごとね、カースケさん。やっぱり頭がいいわ!」
ミユキも大いに喜んだ。
「いやあ、それほどでもないよ」
と、カースケは照れて赤くなった。
「ところで、豪徳さんには、カースケさんの宝物を送ったわけ?」
と、ミユキは尋ねる。
「うん。それは約束を守ったよ。宅配便で送った。ちょっとおしかったけどね、こうやって最終的に賭けに勝ったんだから、それも安いものさ。それに、鈴木先輩が今度イギリスへ行った時に、新しい《まだらの紐》の蛇の抜け殻の皮を買ってきてくれるって言ってくれたしね」
「そう。良かったわね」
ミユキはまた微笑むと、せそうなカースケの頬にキスをした。
カースケはミユキの肩を抱き、彼女の頭を優しく撫でながら質問した。
「ねえ、ミユキ。こういう状況を何て言うか知っているかい」
「何て言うの?」
「めでたし、めでたしさ――」
『この作品は虚構であり、ギャグです。書かれていることを本気にしないでください。また、作中で勝手にお名前と作品名を使わせていただいた作家の皆さんに感謝を表します。そして、気に障ったらごめんなさい』
《了》
戻る |
表紙 |
