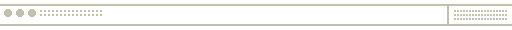
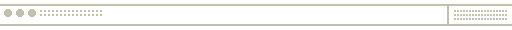
以下の作品は、個人で楽しむ他は、禁複製です。
「二十一世紀のミステリーに向けて」
(これは、「海燕」誌に載せたものの原稿です)
1.ミステリーという文学の現状
論考の前提として、まず「ミステリー」という言葉の定義をしておく。
「ミステリー」とは、「小説」という《虚構の物語》の中の、「純文学」「歴史小説」「時代小説」「SF小説」「冒険小説」「恐怖小説」などと並び立つ、文学上の一範疇である。そしてかつ、世の中に有形無形で存在するあらゆる《謎》を、自己の物語中に含んだ小説ジャンルの総称である。
ここで言う《謎》とは、誰が殺人者か?という疑惑に起因する謎から、密室殺人のような推理小説特有の人工的な謎、幸福な生活を送っていたはずの人妻が何故突然失踪したかというような人間心理の謎など、どんな形でもかまわない。極端な話、物語の中に何か一つでも謎が見いだせれば、広義に解釈して、ミステリーと称して良いだろう。
ただしそれは、結末で合理的に解決される謎であることが望ましい。ストーン・ヘンジの謎とか、ナスカ絵の謎のような歴史上の疑問や、UFOや宇宙人の謎といったような神秘的で超自然的な謎は、また別の小説範疇やノン・フィクションに任せるべきである。
では、ミステリーを細分化するとどうなるか。
その作業の手助けとして、現在の日本のミステリー界を見回してみよう すると「大衆娯楽小説と同義語化したミステリー」という素晴らしく多様化した状況が(真の繁栄かどうかは別にして)見受けられる。
鮎川哲也・島田荘司氏を代表とする純粋な「推理小説」、森村誠一・小杉健治氏を代表とする「社会派」、西村京太郎・内田康夫氏を代表とする「トラベル・ミステリー」、志水辰夫・大沢在昌氏を代表とする「ハードボイルド」、宮部みゆき・小池真理子氏を代表とする「サスペンス&スリラー」、逢坂剛・高村薫氏を代表とする「謀報小説」等、ありとあらゆる部門が存在している。したがって、《現代のミステリー》というのは、逆に見れば、このような個別ジャンルの集合体だと理解できよう。
ここに上げた多種のジャンルは、その性格によって大きく二つに分けられる。すなわち《推理的小説》と《捜査的小説》である。
《推理的小説》という区分に含まれるのは、従来からの「探偵小説」や「推理小説」である。
《捜査的小説》という区分に含まれるのは、その他の「ハードボイルド」「警察小説」「犯罪小説」「サスペンス&スリラー」「スパイ小説」等である。
この二つ性格は、どういう違いを有するか。定義すると次のようになる。
《推理的小説》とは、ミステリーのうち、謎を推理という思索的行為によって解決する物語である。
《捜査的小説》とは、ミステリーのうち、謎を捜査という体験的行動によって解決する物語である。
最大の違いは、謎の探求の仕方だ。《推理的小説》の場合には、文字どおり探偵もしくはその他の人物の推理によって謎の解明をみるわけで、そのためには必然的に物語中にちりばめられた手がかりが必要になる。推理小説の物語中に、よく「読者への挑戦」が挿入されるが、それは手がかりを過不足なく、公平に読者へも分け与えたという、作者からの明確な意志表示である。
しかし、《捜査的小説》の場合には必ずしも手がかりは必要なく、物語の推移や探偵の行動によって、順次結論・結末にたどりつけばよい。謎の解決は、どちらかというと、作者から一方的に提示されることになる。
したがって、この二つの小説区分は、「ミステリー」という一つの名前の元にあっても、根本的には、性質や目的がまったく違う種類のものなのだ。これはミステリーを論じる時には非常に重要な要項なのだが、残念ながら一般的に、明確には認識されていない。
日本では、戦前、ミステリーは「探偵小説」と呼び称された。大戦後、探偵の「偵」の字が当用漢字から落とされたことと、「探偵小説」だけでは枠にくくれない作品が出てきたために、カテゴリー全体に新しい名称が必要になり、木々高太郎らが提唱した「推理小説」という言葉が定着した。その後、さらに多様化した作品が続々と生まれ、翻訳がなされると、さらに「推理小説」という名称ではすべてのジャンルを表現しきれない時代が来た。そこで近年、「ミステリー」という(あいまいで)便利な名称が頻繁に使われるようになったのである。
2.彼らは何故「推理小説」のみを誹謗するか
ところで、時々、次のようなミステリー評論を目にすることがある。
「推理小説もしょせん小説なのだから、人間が書けていなくてはならない」「推理小説としては弱いが、小説としては立派に書けている」「もっと社会性が盛り込まれると、単なるゲーム的推理小説から脱皮し、高級なミステリーになる」「本格推理小説は行き詰り、ハードホイルドや犯罪小説が取って代った」「推理小説には、リアリティがない」
これらの文章を読んで、その意見に大いに賛同される方もあるだろう。しかし、私と同様に、そこに何か偏ったような、奇妙な違和感を覚える人も多くいると思う。
その理由は明白で、これらには、「純粋な推理小説」に対しての敵意が含まれている、と感じられる。批評というよりも、むしろ非難や批判が先に立ち、末節部分をあげつらった誹謗のように見える。
私にとって興味深いのは、こういった意見を述べるミステリー作家や評論家が、必ず非推理小説系の人間であるということだ。実際、この人々はスリラーやサスペンス、警察小説や犯罪小説などの書き手や愛読者であり、「推理小説」を論じる立場としては部外者にすぎない。そんな人間が、何故か、大人気ない態度で推理小説を糾弾するのだ。
当然のことであるけれども、江戸川乱歩や横溝正史、高木彬光、鮎川哲也、島田荘司、綾辻行人などの本格系の推理作家がこうした発言をするのを見たことがない。
ある本の解説で、北村薫氏が《あちら側》と《こちら側》という言葉を使っていたが、これを借りれば、それらはすべて《あちら側》の人間の発言だと認められる。根本的に、《彼ら》は「推理小説」の本質が何たるかを知らず、また、愛情も感じていないような気がする。個人の嗜好はあるにせよ、ミステリー・プロパーを自称する者が、《センス・オブ・ミステリー》という文学的感性を有していないのは、ずいぶん悲しいことだ。
前記の中傷的意見に対しても、反論は容易に成立しよう。
「社会派推理小説も推理小説ならば、推理的な部分が描けていなければならない」「優れた推理小説は、考え抜かれたトリックとプロットが構築されていなければならない」「小説としては書けているのかもしれないが、推理小説としては落第である」「社会派ミステリーは、無味乾燥で、物語として味気ない」
しかし、こうした言葉の応酬は、他のジャンルの欠如した部分を、別のジャンルの優位点に立脚して侮蔑しているにすぎない。どんな小説でも、立場が代ればいくらでも弱点は指摘できる。そんな幼稚な発言は単なる罵倒であり、とうてい批評や論考ではない。
では何故、このような横暴が許されてきたのだろうか。それには、幾つかの特別な経緯があった。
3.推理小説は古く、ハードボイルドは新しいか
まず第一に、次のような意見について言及したい。
「推理小説は行き詰まり、それに代ってハードボイルドが生まれ、後にそれが現代の犯罪捜査小説に進化した」「だから、後から出てきたものほど高級で、古いものほど幼稚である」
この二点の意見は、実は大きな誤解に満ちている。
何を間違っているかというと、ミステリーの発展というのは、ここで言われたような、『探偵小説』→『推理小説』→『新本格派』→『ハードボイルド』→『スパイ』→『犯罪・警察小説』→『サイコ・サスペンスー』と、単なる一本道で進化してきたものではぜんぜんないという事実だ。
それは、付図のチャートを見てもらえば一目瞭然であろう。
ミステリーという文学は、一八四一年、エドガー・アラン・ポーによって「謎と論理の物語」として誕生した。コナン・ドイルを代表として繁栄の道を歩み始めた探偵小説は、当初、シャーロック・ホームズ等の主人公の魅力で読ませる犯罪奇譚風の物語だった。それが、《謎の提示》《手がかりの挿入》《解答の論理性》という内包するゲーム性をしだいに顕著にし、「推理小説」としてのルールの確立をはかる。
一九二〇年代には、欧米で続々と推理小説の傑作が書かれ、『推理小説の黄金期』と呼ばれる時代が来た。一九三〇年代になり、アガサ・クリスティーやエラリー・クイーン、ディクスン・カーなどといったこの分野の最高の芸術家が出現すると、フェア・プレイの精神を旗に掲げて、推理小説はついにその様式美を完成させる。
同じ頃、アメリカのパルプ・マガジンから、ヘミングウェイなどのアメリカ文学と拮抗して、一つの文体様式が勃興する。ハメットらによる「ハードボイルド」である。また、クロフツ流の平凡警官探偵物は警察小説へと変貌し、米ソの冷戦を背景としたスパイ小説が時代の寵児となる。
一方、ゴシック小説に端を発するサスペンス&スリラーも、ラインハートなどの通俗読み物の時代を経て、しだいに推理小説からプロット技術を導入する。そして、アイリッシュ等の、技巧的で繊細な犯罪心理小説へと変化する。
すなわち、ミステリーのジャンルの多様化は、推理小説の黄金期と時を同じくして始まっているのだ。そしてもう一つ重要な点は、それ以降、どのジャンルも並列的に存在してきたということであろう。
結論を言うと、前記の過った認識というのは、日本へ入ってくる翻訳ミステリーの順番から生じたものにすぎない。
明治から大正にかけては、ポーやドイルやルブランなどの「探偵小説」が、大戦前にはチャスタートンやヴァン・ダインやクイーンなどの「推理小説」が、戦後すぐには、スピレーンやハメットやチャンドラーなどの「ハードボイルド」が、昭和三十年代には、フレミング、アンブラー、カレ、などの「スパイ小説」が、昭和四十年代には、マクベインやシューヴァル=ヴァールーやマッギヴァーンらの「警察・犯罪捜査小説」が、次々と我々日本人の目に触れた。
という次第だから、このミステリー翻訳史をもって、《彼ら》はミステリーそのものの発展と誤解しているのだ。もちろん、当時の少ない資料を元にした精一杯の批評を、いまさら非難しようとは思わない。しかし、この古臭い意見に相変わらず固執している者がいるのはどうかと思う。やはり、歴史的な総括というものは繰り返し行なわれてしかるべきで、逐次、古い価値観を新しい価値観へと是正してほしい。江戸川乱歩の『正・続幻影城』以降、しばらくの間、日本におけるミステリーの評論と研究には、残念ながら空白の部分がかなりあったように思う。
4.推理小説にリアリティはないか
推理小説 特に探偵小説を踏まえて、その大仰な設定や雰囲気やトリックに関し、「リアリティがない」と評するのも、《あちら側》の人間の常套手段だ。
凝りに凝ったトリック。幾つもかさなる偶然。わざとらしい殺人予告。意味ありげな会話。古めかしい舞台となる館。
そこにリアリティがない。そんな猟奇的な犯罪は現実には起こらない。だから、もっと現実に即した生身の犯罪を描くべきだ。
これは正しい意見だろうか。
例えば、不可能犯罪の巨匠であるカーの作品は、よく非現実的だと言われる。怪奇的なムードや幽霊奇譚、魔女信仰や狼憑きなどのオカルティズム、中世ヨーロッパの歴史的事実などが物語の背景となり、密室殺人などのトリックと渾然一体となっている。あの江戸川乱歩でさえ、カーのオカルティズムを《アン・リアル》と紹介した。
けれども、私はこれにまったく賛同できない。何故なら、自分の身のまわりの世界を鑑みた時、そこは《神秘》で囲まれているからだ。テレビでは、スプーン曲げを始めとする超能力番組、UFOを題材にした宇宙人番組、心霊術師や占い師の出て来る番組があふれ、その手の本や雑誌が書店に並び、親戚や友人の中には信仰宗教に熱中してしまっている者もいる。
とすると、本当は私たちは、オカルティズムに毒された世界で暮らしているのかもしれない。だとすれば、自分一人が超自然的な現象を信じていないからといって、そういう小説を「リアリティがない」などと断言して良いはずがない。
もちろん、作品中の(つじつま合わせ的な)現実感は必要である。物理学や自然科学に基づいた最低限の法則も守られる必要がある。しかし、どんな突拍子もない物語が展開しようと、しょせん、小説はフィックションであるという点を忘れるべきでない。そうでないと、取材した事実をやたらに羅列しただけの情報小説になってしまう。 実を言うと、私はハードボイルドや私立探偵小説を読んだ時、その作品中にあるわざとらしさに辟易することがある。登場人物のどいつもこいつもが、心にとってつけたような、それこそ作り物めいたワンパターンの傷を負っている。雇い主に対する私立探偵の、信じられないようなぞんざいな言葉使いと尊大な態度。秘守義務もそっちのけに、自分の解決した事件を(小説にして)ベラベラとしゃべってしまう軽薄さ 。
見方を変えれば、こういう点も、「リアリティがない」と切り捨てられよう。要は作品世界にどんな印象を持つかというのは、読者個人個人の趣味の問題にすぎない。その感性の問題を、ある一定の客観性が必要な批評とすり替えることは罪悪なのである。
真実のところ、小説は現実迫真的であろうと空想非科学的であろうと、スタイルはどうでもかまわないはずだ。様々なタイプの小説が問題なく書ける環境があり、それが様々な嗜好を持つ読者の前に齟齬なく提供され、誰でも不自由なく手にできる体制があることが、何より貴重なのである。
5.クロスオーバーからボーダーレスへ
とにかく、ミステリーのみがいたずらに、内部のどのジャンルが高級だの低級だのと言って愚劣な内紛をしていて良いはずがない。それよりは、お互いの長所を認め合い、切磋琢磨していく方がより建設的である。ジャンルごとの差別的な発言など、読者にとって何一つ有益でなく、無意味だ。小説というのは人生の娯楽の享受の一端であり、突き詰めていくと、面白くて感動を与えてくれさえすればどうでもいいわけだ。
故に、個々のジャンルの特質に磨きをかけることもその探求の道であり、他のジャンルの良さを吸収して、自分の面白さの中に取り込むこともやぶさかではない。現に、ジャンル同士のクロスオーバーなども、過去から現代に至るまで数え切れないほどなされている。
クロフツの作品は間違いなく探偵小説だが、経済物やスパイ物の先駆的な作品さえある。ロス・マクドナルドの作品は、ハードボイルトといっても、プロットはかなり推理小説に近い。真相の隠し方の幾つかはもろにそれである。レジナルド・ヒルやコリン・デクスターの作品は、実際の内容は犯罪捜査小説であるが、外面的には推理小説風の仮面と衣をまとっている。
このように、骨子が本格推理であり、文体はハードボイルドであり、キャラクター造形はローカルな警察小説などという作品が、この世界ではいくらでも散見できるようになった。
今述べた例は、ミテスリー内部のジャンル・ミックスであるが、同様に、ミステリーと他の小説との交流も多々存在している。しかも、それはそれほど近年に始まったことではない。
例えば、推理小説と歴史小説の合体は、一九三八年にカーが『エドモンド・ゴッドフリー卿殺害事件』を発表したところから始まる。彼は、歴史学上で払拭されていない実際の事件の謎に、推理小説的な推理と論理的解決を与える目的でこれを書いた。また後年になると、作品の舞台の年代を過去に取る方式の歴史ミステリーというジャンルも開拓した。
歴史推理は、前述のカーの作品に触発を受けたリリアン・デ・ラ・トーレの『消えたエリザベス』、さらにジョセフィン・ティの『時の娘』などが続き、近年のピーター・ラウゼイの『ビクトリアン・ミステリ』や、エリス・ピータースの『カドフェル・シリーズ』などの諸作に至る。
一方、他の小説の方から、ミステリーへと接近や融合を企てた例もある。
アイザック・アジモフの『鋼鉄都市』や『裸の太陽』は、SFの中にミステリーのエッセンスを十二分に取り込んだ奇跡のような作品である。この二作の出現によって、SFとミステリーは甘い蜜月を過ごし、「SFミステリー」という新しい子孫を残した。最近でも、『重力の衰える時』というハードボイルド・スタイルのSFや、『約束の地』というハードボイルドでありながら近未来を背景にした作品が書かれている。
日本においても事は同じで、古くは「捕物帖」などは、時代ミステリーの先駆と言っても良いだろう。そして、現在進行形の試みとなれば、まさに百花繚乱である。
島田荘司氏は『奇想、天を動かす』以降、積極的に社会悪の糾弾という叫びを作品中に取り入れ、強烈な物語の進み具合の中に、殺人動機や舞台背景を色濃く浮き彫りにしている。綾辻行人氏は『時計館の殺人』などにスプラッター趣味を加味することで、本格推理に欠如しやすい中盤のサスペンス不足を補った。我孫子武丸氏は『メビウスの殺人』において人工知能というSFテーマと、他メディアであるパソコン通信を融合させるという実験を試みた。それは翌年、『殺戮に至る病』というプロット重視の傑作へと昇華する。法月綸太郎氏は、『一の悲劇』で古典的なトリックを洗練し、誘拐事件に溶け込ませてみごとな現代ドラマに仕立あげた。井上夢人氏は『クラインの壷』で、六〇年代SFの使い古されたアイデアを、ミステリーという形式に焼きなおすことで、新たな生命を吹き込むことに成功した。
毎年恒例のミステリー・ベスト10の選出にあがる欧米の候補作を見ていると、その内容の多種多様さと混沌とした様に注目せざるをえない。現代の欧米ミステリーでは、もはやジャンルの垣根は存在しないという印象を強く受ける。全体で一つのミステリーなのだ。あるいは、個々の作家の数だけ、個々のジャンルが存在していると言える。
国内作品の投票の方を見ても、ベスト10の半分近くを船戸与一氏ら冒険小説系が占めている。つまり、現代ミステリーというカテゴリーは、冒険小説や他のエンターテイメントと一体化し、区別しにくくなっている現状なのだ。
ミステリーは古くから、小説という紙面の上の活字メディアだけではなく、積極的に、映画、演劇、TV、TVゲームなどに進出してきた(というか、取り込まれてきた)。特に、最近の映画やTVでは、ミステリー的手法と物語展開を用いた娯楽作品が不可欠になっている。近頃、レンタル・ビデオで流行っているVシネマの監督・脚本家たちが、必死にM・スピレーン等の翻訳本を古本屋で漁っているという。原作、または、筋立てや道具立てのパクリにするためだそうである。
かつて『マイアミ沖殺人事件』という、手がかりとなる物的証拠(マッチの燃えかすや髪の毛や写真)を頁のそちこちに貼り付けた企画本が出た。が今や、レーザー・ディスクやCDによるTVゲームなどの他メディアが、まさにそれと同等以上の立体感と臨場感を我々に味合わせてくれる。
実際問題、ミステリーが映像化されるとなると、鏡を使ったトリックなど、視覚に頼って文章では表現しにくかった事項に、新たな可能性が開けてくる。音響等においても同様である。
つまるところ、ミステリーにおいては、メディア上のボーダーラインすら存在しなくなって(必要なくなって)いる状況なのだ。
6.二十一世紀の推理小説
以前、ある推理作家が「ミステリーには、《型破り》なんてものは存在しない」と語っていたが、卓見である これはけっして否定的意見ではなく、純粋主義から発露した言葉だ。「新本格派」と呼ばれる推理小説作家たちが、近年、続々と力の入った作品を発表し続けているが、実は彼らは、《まったく新規な》物を書こうとしているわけではなく、ただ単に、《今まで書かれたもののうち、一番良いもの》を書こうと努力しているにすぎない。そのためには、独創的なトリック、新鮮なプロット、驚異的な結末を案出することが必然であるというだけなのだ。
二十一世紀に向けて、これからもミステリーという小説部門はあらゆる試行錯誤と文学上の実験を繰り返すだろう。特に、推理小説以外のジャンルは風俗活写的な色彩が濃いが故に、自ずからその変貌を受け入れるしかない。現にスパイ小説などは、冷戦の終結と共にすでに存亡の危機にさえさらされ、観光案内化している。また、英米ミステリー全体が、映画の原作化の様相を呈している。
推理小説という古城においても、押し寄せる流行と時代の波を避けるわけにはいかない。しかし、いつの時代においても、この堅固な古城だけは新たな住人を得てますます美しく光輝き、独自の様式美を失わないだろう。奏でる曲は同じでも、奏でる楽器は、積極的かつ意欲的に最新の物を取り入れているからだ。
私自身作家として、ありとあらゆる形態の小説に挑戦していきたい。しかし、ことミステリーとなった場合には、いつまで経ってもガチガチの「本格」でありたいと思う。先に述べたこととは逆説的に聞こえるかもしれないが、実は「本格推理小説」というものは、ぜったいに映像不可能なジャンルなのだ それは、一連の横溝正史の映画が、すべて犯人を主人公にした情念の物語に改変されていたことからも指摘できる。
近年のSF小説に勢いがない理由の一つは、映画の特撮技術が進み、下手をすると小説以上のアピールを映像や画面から受け取ることができるせいだろう。その点、本格推理は先に述べたルール性の顕示によって、完全なる映像的創造方法を拒否している。であるからして、そこに私たち推理小説作家としての誇りと、活路と、書いていく醍醐味があるわけだ。
新世紀に入っても、推理小説の精神と形態は永遠に変わらない。私はそう信じている。ただ、舞台が変わるのみだ。人類が宇宙で容易に生活できるようになった時、月の上での密室殺人(これは、SF作家のラリイ・ニーブンの作品にあった)や、火星上のドーム内での人間(や宇宙人)消失、ワープ空間場でのロケットによるアリバイ崩し、サイボーグとアンドロイドの一人二役などという話が日常茶飯事的に執筆されるかもしれない。そうなったら、それはそれでとても面白いではないか。
*1 個々のカテゴリーは完全に分離しているわけではなく、かなりの部分で重なりあっている。しかし、論議を簡略化するために、ここではそれに触れない。以下、ミステリー内のジャンルについても同様である。
*2 最近では、推理小説的な謎と超自然的な謎とを区別するために、前者を「ミステリー」ではなく「ミステリ」と呼ぶ慣習が出てきた。
*3 ミステリーが出版・掲載される小説中に占める割合の大きさから言える。ただし、文芸小説に較べて、突発的に十万部を越える大ベストセラーは出にくい。これは、ミステリーが、普段は小説を読まない読者を取り込むような話題性で売れるものとは性質を異にしているからだ。
*4 「新本格」という言い方もできるが、ここでは従来の観念である「本格推理」を指す。
*5 最近では、ノベルスという発表形式から、「ノベルス・ミステリー」「ライト・ミステリー」などという呼び名もある。実はこの形態の作品は、推理小説ではなくて、犯罪を扱った中間小説とみるべきである。特徴としては、「〜殺人事件」等と、どの作品も題名が似ている。トリックやプロットが誰にでも解るように単純である。文章に改行が多い。出版点数が多い。などが上げられる
*6 欧米のスパイ小説を、スリラーの系列に含む考え方もある。
*7 私はこの文章中、これは推理小説で「ある」とか「ない」とかいう言葉をしばしば使うであろう。しかし、これは一つのものを別のものと区別しているのであって、けっして、「ある」方が「合」で「ない」方か「否である」といったような差別的な意図を持たない。
*8 「ミステリー」という名称には、多分に出版社側の商業的な政策も含まれている。悪く言えば、ミステリーと冠することで、それに近似した小説まで売ってしまおうという魂胆があることは否めない。これは、「漫画」「劇画」「風刺絵」等を、「コミック」という総称で呼ぶ最近のやり方と同じである。
*9 『キッド・ピストルズの妄想』山口雅也著 東京創元社 一九九三年。
*10 一九四〇年代以降、「推理小説」が少しも進歩していないように見えるのは、それが袋小路に陥って自滅したからではない。単純な話、推理小説という形式があらゆる点で「完成」をみたからに他ならない。当然のことだが、完成してしまったものは、いくらいじろうとも変貌のしようがないのだ。
*11 一八四一年四月、フィラデルフィアの「グレアム雑誌」に発表された『モルグ街の殺人』によって、ミステリーの栄光の歴史が始まる。
*12 ヴァン・ダインは推理小説の戒め一つとして、「謎を解くにあたって、読者は探偵と平等の機会を持たねばならない。すべての手がかりは、明白に記述されていなくてはならない」としている。
*13 もともと怪奇小説や冒険小説などのドラマツルギーを持って生まれたミステリーであれば、ゲーム性に縛られず、物語の展開や人間ドラマを重視した作品 ハードボイルドや犯罪小説 が生まれても何らおかしくはない。しかし、論理的手がかりの提出がないという点については、ミステリー理論としては、ポー以前の状態への遡行現象である。
*14 ただし、批評や研究というのは小説ほど発表の場もなく、金銭の面でも割の合うものではないことは考慮する必要がある。
*15 普通の読者は本を読みながら、「探偵小説」は第一次世界大戦での大量死による人間性の喪失から、個人の尊厳の復権のために生まれたとか、「ハードボイルド」の探偵がお約束どおり殴られて負傷すると、治療用の保健金が下りるのだろうかなどど、いちいち考えはしない。
*16 歴史ミステリーの作品の中には、SFと合体したものもある。『ビロードの悪魔』『火よ燃えろ!』『恐怖は同じ』などを参照。
*17 我孫子武丸氏は、『かまいたちの夜』というアドベンチャー型のゲームソフトのシナリオも手掛けている。
*18 その一方で、変装を含む一人二役とか、叙述的プロットなど、読者に登場人物が実際には見えないことを前提にしたトリックは使いずらくなる。
 戻る |
 表紙 |
