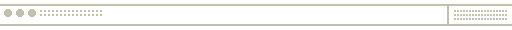
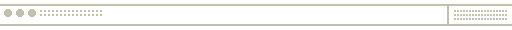
こには、未発表の小説などが置いてあります。個人で楽しむ他は禁転載です。
[長編の一部]
以下、長編『奇跡島の不思議』の別バージョンの一部(最初と最後)です。『奇跡島の不思議』のネタバレを含みますので、先にそちらをお読みください。
『奇跡島の不思議』の別バージョンについて
1 バージョンについて
『奇跡島の不思議』には、AバージョンとBバージョンがある。九六年十一月に角川書店から出版されたのは、実はBの方なのだ。
では、AとBは何が違うのか。それは、ここに収録されたAのプロローグとエピローグを読んでもらえれば一目瞭然だろう。元のAを再構築するには、角川書店版のプロローグと第十八章の代わりに、Aの第0章と第十八章を入れれば良い(もう少し正確には、角川版の第一章の一部を省く必要がある)。それによって、同じようでいて、実はだいぶ違った〝騙り〟と〝狙い〟を持った物語に変化する。角川版はすでにお読みいただいたとおり、ストレートな本格推理小説である。しかし、Aの方はかなりメタ本格を意識したものだった(というか、メタ本格そのものだろう。それも、かなりギャグがかっている)。
Aを出版するべきか、Bを出すべきかは、筆者も担当編集者も最後の最後まで迷った。そのために、角川版の冒頭の人物紹介には、少しゴタゴタした部分が残ってしまった。
正直に言えば、現在でもAの方に少し未練がある。
(ここからは、犯人等について言及する。したがって、まだ角川版を未読の方は、お読みにならないように御忠告申し上げる)
2 作品の成立過程
『奇跡島の不思議』をお読みになった方で、推理小説に詳しい方は、大別して二つの内のどららかの感想を持ったのではないだろうか。
一つは、鮎川哲也先生の『りら荘事件』に似ている。もくしは、影響を受けているというもの。二つ目は、綾辻行人氏の『霧越邸殺人事件』と麻耶雄嵩氏の『夏と冬の奏鳴曲』に似ている。もしくは影響を受けているというもの。
こうした感想や批判は当然至極であり、筆者は反論するつもりはない。どの作品も、閉鎖状況下における連続殺人というプロットを扱った推理小説として、歴史に残る名作である。筆者がそれらに強く影響されなかったと言ったら、その方が嘘になる(ただし、『りら荘』との類似――美術家サークルであること――は、後から《SRの会》の友人K君に指摘されて気づいた)。
その中でも、麻耶氏の『夏と冬の奏鳴曲』は、『奇跡島の不思議』の執筆の直接的な起因となっている。筆者は、麻耶氏の『翼ある闇』と『夏と冬の奏鳴曲』を、自分の推理小説のオールタイム・ベストに入れたいと思うほど愛読している。『聖アウスラ修道院の惨劇』が、『夏と冬の奏鳴曲』と同時に講談社ノベルスで出版されたことなどは、筆者の自己満足的な喜びとなっているほどだ。
筆者は幸運にも、ゲラの段階から『夏と冬の奏鳴曲』を読むことができた。当然、たいへんな感銘と感動を受けた。そして、その興奮も冷めやらぬ内に、一気呵成に、角川版の長編と同じ題名の『奇跡島の不思議』という百枚の短編を書いた。
この短編版は、長編版に含まれている龍門有香子の不可思議な死を、名探偵・二階堂蘭子が解き明かすという内容だった。しかし、あまりに急いで書いたために、できは良くなかった。無理も多かったし、文章や設定にも問題があった。そのため、この作品は、長編として熟成するまで、筆者の胸の内にしまい込んでおくことになったのである。
本格推理小説は、他のミステリーと異なり、アイデアやトリックを思いついただけでは完成しない。アイデアやトリックを磨きに磨いた上で初めて創作が始まる。完結するのに、長い時間がかかるのはざらだ。『奇跡島の不思議』も、そうした事情の元に――成功したかどうかは別として――存在が始まった作品だった。
3 プロットについて
連続殺人事件で、犯人を隠す手法に、《相乗り殺人》もしくは《リレー殺人》という形態があるのは周知のとおりである。しかし、筆者はあまりこの方法を好ましく思っていない。やはり長編での犯人は、最初から最後まで一貫した、そしてできればたった一人であるのが好ましいと思っている。もちろん、これは理想であって、プロットやトリックを複雑にすればするほど実現不可能になる。
《リレー殺人》という犯人のプロットを最初に作った者は天才だった(それ故、鮎川先生の『りら荘事件』は、永遠に傑作の名を失わない)。だが、後からそれを模倣する者は凡庸である。だから、筆者はこの型を使いたくなかったし、できれば、その型を最終的にひっくり返す形で作品を作り上げたかった。『奇跡島の不思議』のAバージョンには、当初からそういう狙いがあったのである。
では、具体的にそれをどうするかについては、昔から腹案があった。少女マンガの手法を小説に取り込み、メタ・ミステリー化を計ろうというものである。少女マンガでは、登場人物がしばしば自分が虚構的世界の住人であることを忘れ、あるいは無視して読者に話しかける。一方、ミステリーには、アンチ・ミステリーという形態がある。小説内人物ではなく、たとえば、読者が犯人であるとか、世の中の人間全部が犯人であるとか、かなり抽象化した概念の犯人像をテキスト的に創造しうる。
つまり、空想内部と現実読者との境界を、登場人物を媒体として意図的に取り払らう形を、小説に応用できると考えたのだ。
4 最終形態
にもかかわらず、最終的にはAバージョンは捨てることにした。その理由はいろいろあるのだが、一つには、小森健太朗氏と彼の作品の存在が大きい。筆者が以前から考えていたこの方法論は、彼の手によってすでに何冊かの本になっている。体言化された作品がある以上、筆者が同傾向のものを書いても所詮二番煎じでしかない。
もちろん、筆者は本格推理小説を様式美であると思っている人間なので、その範疇での反復や模倣は可だ。それでも、今回は自己諧謔的なこのAを捨て、通常の、ある意味でオーソドックスな作品を発表することにした。もしかすると、多種にわたる新たな本格ミステリーが模索・試作されている現在、オーソドックスであることが一番斬新であり、目新しいのではないかとの計算も立ったからだ。
それでは、別バージョンへどうぞ
『奇跡島のへ不思議』別バージョン
第0章 人間たちを紹介する
1
地獄を見た――。
この物語の語り手として、あの血も凍るような恐怖の、そして、不可思議な事件を、どこから読者諸君へ述べたらいいかと考えあぐねている。事件は、《奇跡島》と呼ばれる太平洋の海原に浮かぶ小さな孤島で起きたが、その内容には凄まじいものがあり、新聞やマスコミなどでもかなり大騒ぎになったから、『ああ、あの連続殺人事件のことか』と、覚えている方も多数あるだろう。私たちがその島へ初めて渡ったのが一九八六年の十月のことだから、もうすでに十年前の話になる。
私を含む大学の仲間たちは、ある特別の目的を持って、この無人の島にひっそりと建っている《白亜の館》という屋敷を訪れた。もちろん、島へ行く以前の私たちは、そこで、あのような命にかかわる途轍もない災厄に襲われることになろうとは、まったく夢にも想像していなかった。事件は、常識や日常の尺度ではとうてい計れないような恐ろしい出来事の連続であった。こうして事件が終わり、長い月日が経った今も、仲間を血の海の中でなくしたあの大惨劇が、その異常性故に、本当に起こったことなのかどうか、私は解らなくなることがある。
その事件の詳細を読者諸君に語る前に、まず自己紹介から始めよう。
私の名前は、加々美光一。何だか、一昔前の縫いぐるみ式特撮怪獣映画の主人公みたいな安っぽい名前である。当然、嫌悪するほどではないにしても、自分ではあまり気に入っていない。もっとも、自分の名前が好きだという者にまだ出会ったことがないから、そうした感情はわりと一般的なのだろう。メルヴィルの『白鯨』に出てくる主人公でさえ、仮名で通したのだから、名前という単なる付票に、私が何の価値も見いださなくても特に問題はあるまい。
あの島へ渡った当時の私の年齢は、二十一歳だった。東京にある如月美術大学の三年生で、芸術研究サークル《ミューズ》の一員だった。
父親は加々美光冶といって、号を光禄とし、その道では少しは名の知れた彫刻家兼工芸家だった。東北地方の美術館や博物館へ行くと、時々、父の作品がうやうやしく飾ってあることがあって、作者の親族としては何だか面はゆい気持ちになる。私の家は仙台藩士の出で、父の祖父の代までは相当栄えていたそうである。
父は、今の私から見ると、非常に独創的で才能のある芸術家だった。米沢に、武田信玄ゆかりの同朋寺という古い寺があるのだが、そこの欄干に父が彫った二つの龍があり、彼の代表作として、現代美術図鑑などにも紹介されている。また、長野霧泉高原美術館の正面入り口にある双子の裸婦像などは、ある展覧会で特選と文部大臣賞を同時受賞したものである。秋田県立陶芸博物館に目玉として収められている二対の『織部焼葡萄文様角皿』などは、私のような半素人が見ても真の傑作だと思う。
ただし、父は恐ろしいほどの寡作家であり、生涯に残した作品数はそれほど多くない。芸術家にありがちな気むずかしい性質をしていた。仕事の選り好みも激しく、自分の気に入ったものしか絶対に手を付けなかった。当然のことながら、出入りの美術商人たちにも評判が悪く、固定したファンは付かず、大きな仕事を何度も逃がした。したがって、表向きの名声とは裏腹に、収入は少なくて、私の家はいつも貧窮した状態にあった。
母は多恵といったが、やはり武家の血を引く旧弊な女だった。実家はかなり古い家柄で、本家と分家の間で親族結婚がなされることが慣習となっていた。だが、明治維新を迎えた後は、新しい血を入れようと、外部との婚姻も積極的に結ぶようになっていた。父と母の婚姻は、そんなことを画策する母の縁者の希望で実現したものだった。
母は、多恵という名前の音のとおり、ひたすら父の横暴や気まぐれに堪え忍んだ。死ぬまでついぞ、夫に対して一言も口答えをしたことがない女だった。忍従の日々という言葉があるが、それは母のためにあるもののように思う。そして私も、彼の怒りを買わぬよう、じっと息をひそめて暮らしていたような気がする。
それでも、子供の頃、私はよく父に殴られた。自分ではこれといった理由も思い当たらないのにである。父は仕事に行き詰まると、酒を飲んだくれて、家族に当たり散らす人間だった。私は父が恐ろしくてたまらなかった。だから、父が仕事場から母屋へ戻ってくると、私は奥の部屋へ隠れてしまうか、必ず外へ逃げ出したものである。
私は、赤ん坊の頃から病弱だった。おしめの取れない頃に、引きつけを起こして死にそうになったことがあるというし、熱を出して何日も寝込んだことがある。喘息の発作で窒息しそうになったこともあるし、胃弱のため、下痢が続いてひどく痩せたこともある。そんな私を、母は必死に看病してくれた。だがあの父は、この私をまるで厄介者を見るように扱い、まったく頓着しなかった。
父親が私や母をないがしろにした理由は、小学校へ入学した時にようやく少しだけ合点がいった。それは、彼が私を、自分とは違ったタイプの芸術家に作り上げようと計画していたことに起因する。彼はこの私に、将来洋画家として名を成すよう、物心がつくかつかないかの内から英才教育を施そうと考えていたらしい。しかし、実際に絵筆を持った私には、それだけの才能も資格もなかった。彼の判断したところによれば、せいぜいが、水墨画などの日本画を身に付けるぐらいのことが関の山だったのである。
自分の人生を振り返ってみると、私は非常に多くの後悔を抱えている。しかもその後悔は、ほとんどが私自身の気弱さから生じている。私の引っ込み思案な性質は、明らかに母親似だ。父親の我の強さは、少しも血の中に伝搬していなかった。私は何事に対しても消極的であきらめが早い。父親は、そんな私の煮え切らない性質を特に嫌がった。彼は物事には裏と表、もしくは右と左の二つの側面しかないと思っていた。だから、どんな問題にぶち当たっても、即答ができないと我慢できないのだ。ところが私ときたら、いつでも優柔不断でけじめがなく、物事の黒白を明確に判断することができなかった。
父親は私に失望した。彼は芸術家にありがちな、恐ろしいほどのナルシストであり、エゴイストでもあった。彼は私という子供に、自分の才能を受け継いだ分身を期待したのだ。自分と同じ芸術家の血と魂と素質を私に伝授することを切望したのだ。ところが、私には母親の血が多く流れており、それが裏切られたものだから、私をうとんじ、母をなじり、二人を軽蔑して、最終的には見捨てたわけだった。
長ずるにつれ、私の方でも、そんな父をあからさまに憎むようになった。だから、私は絶対に父のような人間にはなるまいと思った。小学校、中学校、高校と、私はひたすら我慢を重ねて生きた。大学に入ったら、絶対に家を出てやると心の中で決めていた。そのためにも、遠くの大学に受かりたいと願った。幸い父は、私が大学に入ることには反対しなかった。ただ一つの条件は、美術大学に入ることだった。父は職人的徒弟制度の元に芸術家になった男だったので、学歴というものには反撥を感じつつも、自己を卑下し、劣等感を感じている部分もあったのである。
芸術家といえども、美術界に属していれば、結局は一つの社会で息をしているにすぎない。自由業などというのは名ばかりであり、真っ赤な嘘だ。年功序列、学歴、派閥、師弟関係など、他の社会で幅を利かせる制約が、ここでも生きている。いや、それ以上に力を持っている。たとえば、あちこちの美術館で展覧会が開かれているが、あれに自分の絵を出品しようと思えば、必ずどこかの美術会に入会し、特定の人に師事せねばならない。そして、月謝を払い、先生におべんちゃらを言い、付け届けをし、会が主宰する展覧会へ出品するための支度金をひたすら払う。そうして展覧会に何度も作品を出していると、払った金額に応じて先生からお墨付きをもらえる。そのお墨付きの回数によって、次には、中央の大きな展覧会へも絵を出せるようになるのだ。そして、そこでまた莫大な支度金を払い、多くの先生方に媚びを売って取り入る。すると、そこで入選した内容や回数が、自分のプロフィールに華々しく飾られるという仕組みである。
要するに、芸術家の名誉といっても、しょせんは金で買うようにできているのだ。これは、犬の品評会とまるで変わらない。才能だけで、名誉や財産を簡単に築けるわけではないのだ。残念ながら、美術界を牛耳っている輩は、役人でいうところのキャリアに当たる。実戦の経験は浅くても、家柄と学歴と財力が彼の地位を何よりも守る。そして、家柄も学歴も財力もない貧乏芸術家が、その傘下に跪くという構図なのだ。
だから、父は私を何としても美術大学へ入れようとした。それは私のためを思ってではなく、自分の息子の経歴に学歴という箔を付け、己の劣等感の穴埋めをするためだった。だから、珍しく幾つかの仕事をして入学金を作ったり、知り合いの美術関係者に頭を下げたり、絶縁していた母方の親戚にも援助を申し込んだほどだった。
私の方と言えば、彼の元から逃げ出すという目的以外には、別に大学へ行こうが行くまいが、そして将来芸術家を目指そうがどうしようが、いっこうにかまわなかった。実際の話、私に父ほどの芸術的才能がないことははっきり自覚していた。さりとて、別になりたいものや好きな職業があるわけではない。私はいつも心のどこかで、自分を小沼に浮かぶ小さな浮き草だと思っていた。風の向くまま、水の流れるまま、人生の上を漂っていくしかない。うまく美術大学に入学し、問題なく卒業できれば、将来はどこかの博物館か美術館の学芸員にでもなれるだろう。そのくらいの希望しか持ち合わせていなかったのだ。
一応の受験勉強をして、父親の根回しもあったためか、私は無事、東京三鷹市にある如月美術大学に入学することができた。昔の美術大学なら、実地試験に秀でた者なら試験に通りやすかったのだろうが、現在の試験制度では、普通科の大学のように一般科目試験が重視される。その点は、私のような凡人にも好都合だった。
私は大学の近くにアパートを借り、生まれて初めて独り暮らしをした。しかし何よりも嬉しかったのが、あの横暴な父親から遠く離れて生活できるということだった。
入学式の当日、私は《ミューズ》という美術研究サークルに入会した。その理由は、単に一番最初にこの会のメンバーが声をかけてきたからである。実際のところ、何を研究する会なのかも知らず、私は入会届に署名していた。しかしまさかそのせいで、三年後に、《奇跡島》におけるあのような死ぬほど恐ろしい事件に遭遇してしまうとは……。
父が死んだのは、私が大学二年生になったばかりの時だった。母親から電話が入り、父親の訃報を知った。酔っぱらった父が、市内を流れる穂坂川の欄干から転落して、水死したのである。雪解けで増水していたため、かなり下流に流され、救助された時にはもう息はなかったという。
私はこのことにまったく悲しみを覚えなかった。むしろ、じわじわと心の中から幸福感が沸き上がってきたほどだ。母からこの連絡を受けた時、最初に感じたのは、『俺は、これでやっと自由になった』という開放感だった。私は、父親の死を喜んだのである。
私はとうとう、芸術家加々美光禄の人物たるものを理解し得なかった。芸術家として、彼が何を終生追い求めたのか少しも興味がないし、その内面性には最後まで共感を持ち得なかった。もちろん、父親としての光治を愛したことなどは一度もない。
今の私にとって、彼は戒名の彫られた一個の位牌にすぎない。
私の体の中には、確かに彼から受け継いだ染色体やDNAが含まれているのだろう。だが、私は私で、彼とはまったく別の人生を歩んでいくことだろう……。
2
長々と私のことを述べてきたが、実を言うと、そのような私の身の上話は、この物語にとってはさほど重要ではない。たとえば、私が東京大学で学んでいて、将来は大蔵省の官僚になるつもりでいても、あるいは、高卒で事務職を選んでいたとしても、それから、サッカーか何かのスポーツ選手であったとしても、スイミング・クラブのコーチを職業としていたとしても、ぜんぜんかまわないのである。もっと極端なことを言えば、私を単なる《人間A》という記号で扱っても、この物語の性質上何の問題はない。
それにもかかわらず、私が自分の過去を大げさに振り返ってみたのは、これは、この小説の作者である二階堂黎人の勝手な都合であって、単に小説上のお約束を彼が履行しているにすぎない。つまり、私が血肉の通った立派な人間に見えないと、『この小説は人間が書けていない』などという画一的な非難を誰かさんからされて、彼が困るからだ。小説用語では、それを〝キャラを立てる〟と言ったりするらしいのだが、登場人物の性格付けを明確にして、読者に印象付ける手法といことになる。要するに、冒頭でこうして私に生い立ちを語らせたのは、作者にとって都合の良い自衛策の一環にすぎないわけである。
私はその辺のことにあまり詳しくないので、後で出番のあるミステリー好きの後輩に、どういうことか訊いてみた。彼が言うところによると、『現実社会の有様を忠実に写実するリアリティ』と、『空想や虚構で成立している小説世界を迫真的に読者に伝えるリアリティ』は、当然区別されてしかるべきなのに、その見分けのできない愚か者がどこかの世界に巣くっているそうなのである。そのために、多くの推理小説作家や見識のある愛読者がひどい迷惑を受けているそうなのだ。
したがって、たった今も、この小説の作者は変なことを考えている。それは、第一章からの物語中ではなくて、この第0章において、私以外の登場人物も全部早々と紹介してしまおうかという横着なことだ。
だが、彼は何故、そしてどこから、そんな奇妙なことを思いついたのだろうか。これは正真正銘の小説であって、評論や演劇の脚本、ゲーム、漫画、パソコンソフトなどではないはずだ。普通、小説では、私が今読者に直に語りかけているような二人称での対話は行なわれない。それが常識である。
それには、深い(浅い?)訳がある。
知っている人は知っているが、二階堂黎人は、ジョン・ディクスン・カーという外国の推理小説作家の作品が大好きである。カラスじゃあるまいし、やたらに自分の小説や随筆の中でカー、カーと書き込んでは大騒ぎをしている。学生の頃に、海外翻訳ものを多数出しているH書房へ友人と二人で殴り込みをかけ、『カーを復刻しろ!』と怒鳴りまくった。銀座の文壇バーへ行くと、ホステス相手に酔った勢いで、『おれ様は、日本で一番のカー・ファンだぞ。SやYやMが怖くて、酒が飲めるか!』などと言い放つ。ある大学の公演では、『カーは本妻、クイーンは召使い』などと暴言を吐き、良識あるミステリー・ファンのひんしゅくを買っている。あげくの果てには、JDC
振興会とかいう秘密結社から命を狙われたりもしている。
その作者が、だいぶ昔に『三つの棺』というカーの代表作を読んでいた時のことだった。確か、高校一年か二年の時らしいが、中央線の混雑した電車の中で、彼はあたりもはばからず突然、『うひゃー!』と叫んだのだ。無論、周囲から咎めるような注目を浴びてしまい、恥ずかしくなって赤面した。これは作り事の話のように思われるかもしれないが、あくまで事実である。
しかしながら、作者は何故、場所柄もわきまえずにそんな突拍子もない驚きの声を上げたのだろうか。それは、『三つの棺』の中に、驚天動地としか言えない奇妙なことが書かれていたからなのだ。この本の中に《密室講義》という有名な章があるが、問題はその中の一部分だった。
それは、主人公のフェル博士が別の登場人物から尋ねられて、次のように述べる場面である。
「――しかし、もし不可能な状態を分析しようとされるのだったら」と、ペチスが口をはさんだ。「なぜ推理小説を論ずるのですか?」
「なぜならば」と、博士はずばりと言った。「われわれは推理小説の中にいる人物であり、そうでないふりをして読者たちをバカにするわけにはいかないからだ。手のこんだ口実をつくり出して、推理小説の論議に引きずりこむのはやめようじゃないか。書物の中の人物にできる、最も立派な研究を率直に誇ろうじゃないか」
三田村裕訳
どうだろう。この文章を今初めて読んだ読者諸氏も、あの時の作者と同様の驚きを味わったのではないだろうか。
『われわれは推理小説の中にいる人物であり』だってえ!?
前代未聞の文章である。
いったいどこの世界に、小説中の登場人物が自ら、自分が作者によって創作された人物であることを暴露したり、自分の活躍する場が、現実とは異なる小説世界であることをあえて唱えたりするだろうか。小説はフィクションというぐらいだから、確かに虚構ではある。だが、その虚構の物語をあたかも現実の物語であるかのごとく楽しむのが、小説というものではないだろうか。たとえ、SFやファンタジーのような絵空事であっても、その絵空事が醸し出す現実感に浸り、逆にその絵空事が普段我々に体験できないことを心象として与えてくれるからこそ、私たちは小説を好むのだ。
つまり、作者も読者も――そして、小説中の登場人物ですら――すべてが架空のものであることを是認しながら、しかしその事実を意識外にあえて追いやり、進んで虚構の世界に身を委ねるのが、本来の小説の姿ではないだろうか。
にもかかわらず、『三つの棺』では、その不文律を自らぶちこわしているのである。本来なら、百万言を費やしても、何で彼らが密室殺人に関して小説のトリックを議論するのか、様々な理由をねつ造すべきであろう。それがむしろ、お約束というものである。
カーという作家のやったことは、私には本当にひどいこととしか思えない。せっかく面白い小説に酔いしれ、空想の世界に精神を自由に飛翔させているのに、突然後ろから冷水を浴びせられ、現実に無理やり引き戻されたようなものだ。私のような常識ある人間には、こんな横暴はまったく理解できない。その点に関しては、私と同じミューズの仲間である後輩が、《メタ・ミステリー》がどうしたと、何たらかんたら言っていた。たぶん、彼自身がもう少し後に出てきて、どういうことなのか説明してくれるだろう。しかし、現時点における私にはぜんぜん納得できない。
とにかく、二階堂黎人はその『三つの棺』を読んでから、いつかは同じような不道徳な冒険を犯してみたいという欲望にとらわれた。そしてついに、この『奇跡島の不思議』という新作の執筆に際して、その禁断の行為を試してしまったわけなのである。
だから、私は作者に命じられるまま、こうして読者諸氏に直接内幕を白状している。
しかし、いい迷惑なのは、私を始めとする登場人物や、この本の担当者であるK書店という出版社の編集さんだ。そして、もしかすると、まともな推理小説を読みたいと思ってこの本を買った読者諸氏が、一番の被害者かもしれない(ただし、もう少し後の頁から、まともに話が展開するので、少しだけ我慢して読み続けてほしい)。
二階堂黎人という作家は、原稿を書き上げる前には、編集さんといえどもその小説の内容をほとんど漏らさないのを信条としている。だから、担当の編集さん――仮にY氏としておくが――は、今、この原稿がこんなおかしな具合に進行しているのをまったく知らない。
Y氏はこの新作について、作者から『奇跡島の不思議』という題名と、美術界にまつわる連続殺人事件ものですという概略しか聞かされていない。また彼は、蘭子シリーズみたいな本格を書いてくださいと作者に頼んである。だからたぶん、Y氏はこの小説を、横溝正史の『獄門島』みたいな正統派の作品だと思っているはずなのである。
それなのに……。
ああ、可哀相なY氏。私は彼に同情する。
どうせ、この原稿の仕上がりはかなり遅いはずだ。Y氏はさんざんそれを待つことになる。そして、締め切りぎりぎりにやっと手に入れた原稿は、こんな奇妙なものなのである。出版までの時間を見ても、もはや手直しのしようがないではないか。私には、Y氏がこの原稿の初稿を読み終えた時のひどく悩み苦しむ様が如実に想像できる。
そうか、だからなのか。何だか、私には作者の企みが解った気がする。
作者は、この作品の執筆開始をずいぶん怠けていた。もっと早くから着手できたはずなのに、先輩作家のI・O氏と共に取材と称してあちこち遊び呆けていた。今になって思うと、計画的にわざと書き出すのを遅らせ、必然的にでき上がりも遅らせようとしている節がある。
まあ、いい。言い訳は、どこかの場で作者自らがするはずだ。私のような一介の登場人物にすぎない男の責任ではない。私は早く物語へ入れるよう、話を進めるだけだ。そこで私は、まず何を最初に語ろうかと、わざとらしく考えてみることにする。やはり、舞台となる《奇跡島》について、故事伝来を交えて語るというのが、この手の推理小説の正しい在り方であろう。
ところが……。
3
「ああ! 加々美さん、こんな所にいたんだ! ずるいやあ!」
若くて、躍動した声。見なくても誰か解る。武田紫苑、十八歳。高校三年生。これも後で、別にわざとらしく出てくると思うが、武田留美子というミューズの仲間の従弟だ。たいへんな美少年で、小柄なので、下手をすると中学生にも見える。これが少女漫画なら、間違いなく、背中にバラの花束を背負って出てくるタイプである。
「――シオン」
私は声のした方を見る。
舞台の袖から――と言ったって、小説で戯曲や演劇ではないから、これは比喩的な表現なのだが――彼が若鹿のように駆けてきた。
彼の俊敏そうな姿を目にしながら、私は『何がこんな所だ』と心の中で小言を呟く。実際、ここをこんな所と言うのは変な言いぐさだ。私や彼が、今こうして存在している場所をどこだと思っているのだろう。存在としての私たち登場人物は、文字間と行間に仮想的に作り出された小さな意識の傀儡にすぎない。
「いやだなあ。加々美さん、また一人で何か難しいことをぶつぶつ言ってたんでしょう。だめだめ。だいたい加々美さんてさ、少し性格が暗いよ。今時ね、そんなのは流行らないんだよ。もっと、パアーッといかなくちゃ。いつだって、自分だけが不幸を背負っているような不景気な顔をしているんだから。根暗だよ。
それにさ、自分一人抜け駆けして、読者にアピールしようなんてずるいよ。今はね、推理小説だって女性の読者がすごく多いんだから、ボクみたいな、可愛くて愛される人物を前面に押し出さなくっちゃだめさ。それで、うまくレギュラーになったりすると、コミケなんかで売っている同人誌の題材にバーンと使われるんだ。もちろん、お耽美系だよ。
何だったら言って。ボクがこの物語の主人公になるから。
あ、そうだ。ねえ、ねえ、加々美さん、知っている? ボクはまだ見たことがないんだけど、同人誌に『島田本』てのがあるらしくてさ、もちろん、有名作家の島田荘司氏のことだけどさ、その本に、U氏っていう名の好色で酒好きな編集者が出てくるんだって……」
若くて美形の紫苑は、私たち仲間内のアイドルである。なかなか愛される性格をしている。だが残念ながら、おしゃべりがすぎる。
「シオン」と、私はうんざりした声で言った。「そんなことはいいからさ、自分でさっさと読者に挨拶をしたらどうだ」
「あ、そうか」と、紫苑は照れて、ペロリと舌を出す。「失敗しちゃった。それじゃあ、あらためて――ええと、皆さん、こんにちは。ボク、武田紫苑です。良かったら、軽めにシオンって呼んでください。みんなもそう呼んでいますから。
身長は一六五センチ、体重五十キロ、右きき、髪はサラサラのセミロングで、眼鏡はかけていません。目が大きくて、鼻筋は通っていて、唇がぷっくりしています。萩尾望都の『トーマの心臓』や、竹宮恵子の『風と木の詩』に出てくる主人公に似ているかな。子供の頃、よく女の子に間違えられたし、小学校では、《シオ子》という渾名があったくらですからね。それで、少しいじめられたりもしたけど、ボク、ぜんぜん平気でした。
今、如月高校の三年生です。従姉のルミちゃんこと留美子がミューズに属しているんで、よく大学の方のサークルに顔を出してます。僕の高校は、加々美さんたちが勉強している――遊んでいるかな――如月美術大学の付属で、敷地がすぐ隣にあるからなんです」
「君の所も、ルミコの家も、けっこう金持ちだったよな」
「うん。ルミちゃんのパパと、僕のパパが武田貿易って会社をやっているんだ。社長と専務でね。おじいちゃんの代からの会社で、年商何億とか言ってた。まあ、そんなに豪勢な金持ちじゃないけど、お金には困っていない」
私は軽く微笑んで、
「君もルミコも、脳天気な性格だってことを、詳しく説明しておいた方が良くないか」
「ああっ、それはひどい。加々美さん、ずいぶんだよ。それじゃあ、僕もルミちゃんも、単なる馬鹿みたいじゃないかあ」
すると、
「――誰が馬鹿ですって、シオン!」
と、ちょっと舌足らずの可愛い声が横から飛んできた。
「あ、ルミちゃん、いらっしゃい」
紫苑が嬉しそうに大声を上げる。
満面に無邪気な笑みを浮かべ、上手の袖から――これも比喩的表現である――スキップしながら出場したのは、さっき言った彼の従姉の留美子である。
「ずるいじゃないの、シオン。自分ばっかり先に、読者の皆さんに紹介されちゃうなんて。あたしの方が年上なのよ。それに普通はね、あたしみたいな美少女をメインにした方が、読者のウケだっていいはずよ。特に、男性読者は大喜びだと思うな。このふわふわの巻き毛を見て。池田理代子先生や、西谷祥子先生が描く美少女によく似てるでしょ!」
留美子は襟元の髪の舌に手を入れてポーズを取り、こちらを媚びるような目で見る。
自分で自分のことを美少女というだけあり、確かに人目を引く容貌だ。というより、とても私と同じ大学三年生には見えない。小柄な体格で、顔立ちもひどく幼い。大きな潤みがちの目と長い睫毛を持ち、唇も果実のように熟れている。笑うとえくぼができる。髪は長く伸ばした巻き毛で、あちらこちらに赤い小さなリボンが結んである。まるで、花園に飛び交う蝶々のように。
彼女の容貌を際立たせているのは、その露悪的な、ピンクハウス系びっくりの少女趣味の服装だった。ロリータ・ファッションとでもいうのだろうか。服装や持ち物が、まるで小学生のようなのだ。今日の格好だって、フリルの付いたピンク色のブラウスに花柄のフレアのミニスカートを着て、白いソックスとコルクのサンダルを履いている。普通のハンドバックは持たず、レースやフリルやキルティングや花飾りの付いたバスケットを愛用している。しかも、そのバスケットの中には、たいがい小さな縫いぐるみが入っている。
可憐と言えば可憐だが、留美子の外見や精神年齢は幼稚すぎる。こういう女性たちのことを、確かアリス症候群と言ったと思うが、まさに言い得て妙である。
「ねえ、ねえ、加々美くん。今日のあたしの髪型、ステキ?」
「ああ、いいね」
と言いつつ、私は内心やれやれと思っていた。従姉弟同士で同じようなことを言ってやがる。この二人は顔形も似ているので、同じ服装をして遠目に並んだら、間違いなく双子に見えるだろう。
紫苑がニヤニヤしながら言う。
「そうかな、読者はルミちゃんの顔を見て、呆れるんじゃないの」
「何でよお」と、言い返してから、留美子は私にしなだれかかった。「加々美くん。あたしも自己紹介していいでしょう。ねえ、お願いん」
彼女は、蜜より甘ったるい声で言った。
「もちろんだよ、ね、加々美さん」
代わりに答えたのはシオンだった。こんな時は彼女に加勢する。
「あのね、シオン。あたしは加々美さんに聞いているんだから、黙っていてよね」
「あ、そんなこと言いながら、こっそり加々美さんと腕を組んでいる。エッチだなあ」
「いやあね、腕くらいで。くだらない。紫苑て、子供だわ。それに、あたし、前から加々美さんのこと大好きだって言っているでしょう」
「でもさ、加々美さんは、ルミちゃんのこと何とも思っていないって言っているじゃないか」
「嫌いとも言ってないじゃないの。微妙な男心って奴よ。子供は、大人の恋愛に口を出さないでよね。イー」
「そんな意固地なことを言ってたら、絶対に加々美さんに振られるんだからね。イー」
私は、ムキになって睨めっこをする二人の間に割って入った。
「もう。いいよ。ほら、ルミコ、読者が待っているよ」
「あ、いけない。そうだったわ」
留美子はあわてて居住まいを正すと、髪に手をやって形を確かめた。バスケットを床に置いて、軽くお辞儀をする。
「読者の皆さん、初めまして。あたし、プリティー、ラブリィー、キューティーのルミコで~す。年齢は二十一歳。加々美さんと同じ大学の三年生なの。もちろん、ミューズに入っていますわん。シオンは、自分がみんなのアイドルだと思っているけど、本当は、ア・タ・シ。
好きなものは、人形系なの。フランス人形から縫いぐるみ、アンティック・ドールまで、何でも好き。趣味でたっくさん集めているの。一番大事にしているのが、パパに最初に買ってもらったくまのパディントンちゃん。それから、少女小説がだあ~い好き。特に、『赤毛のアン』とか『若草物語』とか『あしながおじさん』とかは、あたしのバイブルなんだもん。もう数え切れないほど読んじゃったわ。この本は、ベッドの枕元にいつもおいてあるのよ。みんなあたしの赤ちゃんだから、とっても大事にしているの」
「みなさん、ルミちゃんは、頭の中身が赤ちゃんなんで~す」
「やめてったら、シオン!」
私は、彼女たちの話を聞いているだけで疲れてきた。この二人が揃うと、いつもこうした痴話喧嘩が始まるのだ。本当はすごく仲が良いのだが、似た者同士なのでかえって困るのである。
4
「――やあ、君たち、ずいぶん楽しそうじゃないか」
そこに現われたのは、島へ渡るこのメンバー、ミューズのリーダーだった。名前は麻生真梨央。非常に落ち着いた雰囲気と、物静かな口調でしゃべる青年だ。四年生なのだが、一年間の浪人と一年間の留年をしているため、我々の内の最年長者である。
「あ、麻生さん!」と、紫苑がはしゃいだ。「今ね、僕たち、読者の皆さんに挨拶してたんだ。麻生さんもどう?」
「なるほどね」と頷き、彼は切れ長の目を細めると、この頁を読んでいる読者の方をまっすぐ見た。「皆さん、初めまして。俺は麻生真梨央といいます。ミューズ・サークルの部長をしています。どうか最後まで、この小説にお付き合いをくださいますよう、よろしくお願いします」
留美子は私の腕を離し、今度は真梨央の腕に自分の腕を絡ませた。上目遣いに彼の顔を見上げる。
「麻生さん、それだけえ? もっと、言うことないのお? それじゃあ、寂しいわよお」
「いや、いいよ」真梨央は軽く微笑み、しかし冷めた声で答えた。「自分で自分の説明なんかしたら少しも客観的になれない。俺について何か語るなら、ここは、加々美に頼もう」
「はい」
私は素直に答える。私は彼という人間が大好きだった。リーダーとして全幅の信頼を寄せているので、何事にも逆らう気がしないのだ。
真梨央は非常に背が高い。肌が白く、髪の毛の色は栗色である。しかも、かなり痩せ形だから、その独特の風貌は人目を引く。実は祖父がイギリス人なので、四分の一だけ白色人種の血が混ざっているのだ。上背があるのもそのためだろう。高校の時には、バレーボール部に籍を置いていたこともあるという。
顎の長い顔は彫りが深く、顎が少し長くて、目鼻立ちがはっきりしている。時折物憂げな眼差しをし、言動は仙人のように穏やかだった。ちょっとジョン・レノンに似たところがあり、一昔前の瞑想好きなヒッピーという雰囲気をしていた。温厚な性格で、勤勉で、責任感も強いので、サークルの仲間たち全員からたいへん慕われている。
「――どうですか、こんなふうな説明で」
私は尋ねた。
「そうだな」と、真梨央は薄く笑った。「ちょっと誉めすぎな感じがするが、まあいいさ。ありがとう――そうだな。他には、このお気に入りの帽子のことでも言っておいてもらおうか」
真梨央は、外に出る時には、いつでも帽子を被っている。今日は、オレンジのチューリップ・ハットである。下から、カールした長髪がはみ出ている。服装は、ワークシャツの上に革のベストを着て、長い足によく似合う――最近では珍しい――ベルボトムのジーンズをはいている。
「あのね」と、留美子が口を挟んだ。「ジョン・レノンっていうより、トーベ・ヤンソンの『ムーミン』に出てくるスナフキンって言った方が、よく解るわよ」
「スナフキンだってさ!」と、紫苑がちゃかした。「やめてほしいなあ。あんなむっつりの案山子野郎を引き合いに出すのは。真梨央さんのイメージが、崩れちゃうよ」
「野郎とは何よ。野郎なんてのはね、不良の使う言葉なのよ」
「はい、はい。ルミちゃんはお上品ですよーだ」
どららにしても、真梨央が思想家タイプであるのは間違いない。普段から彼は思索的であり、絵画の他にも演劇や詩を愛している。
「もういいよ。二人とも」と、真梨央が静かに諭した。「喧嘩なんかしている暇はないんだぞ。これから、俺たちが例の《奇跡島》へ渡ると、どうなると思う。俺たちの身にはな、数々の恐ろしい試練が待ち受けているんだ。だから、今から仲間割れをしているようじゃ、誰も生き残れないぞ」
「ええ! 《奇跡島》って、そんなに怖い所なの!」
紫苑が目を丸くする。
「そうさ」
真梨央ははっきりと頷いた。私は、彼の目の中に何か不吉な色が一瞬浮かんだのを見た気がした。
「俺はさっき、ちょっと先の方の頁を覗いてきたんだ。そこでは、目を覆いたくなるような惨劇が起こっていた。たいへんなことになるんだ」
「ま、まさか、あたしたち、死んだりしませんよね」
と、留美子が自分の肩を抱いて、大げさに震える仕草をした。
真梨央は少し暗い顔をして、肩をすくめた。
「それは読者の興を醒ますことになるから、何も言えないな。それに、知らない方がいいのさ。もしも、自分が連続殺人の犠牲者になると解っていたら、おっかなくって精神的に耐えられないじゃないか。もう少し待つんだ。そうすれば、何もかもが解るから……」
「ぎょえええ。ボク、死にたくないよー!」
真っ青になった紫苑が、万歳をする格好で悲鳴を上げた。
5
「――おい、加々美。俺たちの出番はまだかよ」
「そうですよ。先輩。もうこの章もかなり進んでいますよ。後の仲間は、まとめて紹介した方がいいんじゃないですか」
「そうですわ、加々美先輩。早く紹介してくださいませんか」
「おいらも、すっかり待ちくたびれたっす」
あははは。やっぱりみんな出てきたかと、私は思った。他の者が自己紹介をしていて、彼らが黙っているはずがない。新たな登場人物が、今回、《奇跡島》へ行くミューズのメンバーの残りだ。順番に、榊原
忠久、日野原剛 、加嶋友美、木田純也の四人である。
「誰から話しますか」
私が訊くと、
「俺だ」
指先にタバコをはさみ、気取った仕草でこれを吸っている榊原が返事をした。彼はたいへんなヘビー・スモーカーである。
「加々美、俺のことは、《画伯》という渾名で読者へ紹介してくれよ。四年生の俺は、真梨央を除けば一番の年長だ。その上、美術展に出品している油絵が何度も入選しているエリートだぜ。このミューズの中でも、才能豊かな特別な存在なんだからな」
「画伯さん」と、紫苑が澄ました顔で口を挟んだ。「自分でそれだけ自己主張すれば、もう加々美さんが何も言うことはないよ。それに、そういう性格って、読者に嫌われるんだよ」
細い銀縁の眼鏡の端を人差し指で少し持ち上げ、榊原は薄く唇の端をねじ曲げた。
「何を言うかと思えば、子供は仕方がない。俺がこういう少し意地の悪い性格に設定されているのもな、作者の狙いなんだぞ。この方がメンバー間で性格が際立つだろう。それだけ、読者が登場人物を区別しやすくなるんだ。そんなことも解らないのかよ」
「じゃあ、榊原さんは、頭が切れて、僕らの中では一番芸術的センスがあるけど、その分、威張りん坊で、皮肉屋で、傲慢で、人からは嫌われているっていう立場なんだね」
榊原はムッとした顔で紫苑を睨みつける。後ろで留美子がクスクス笑った。
彼は少し細身の体躯で、背丈は普通。顔は顎が尖りぎみのため、性格の鋭さが強調されて見える。目は細くて少し三白眼の感じ。伸ばした前髪を左の耳の方へ流している。黒いスタンドカラーの服を着ているので、一見カトリック神父に見えたりする。
「加々美。俺の履歴に触れていいぞ」
注文を付けられたので、そうすることにする。
彼は埼玉の浦和の出身である。小学生の頃から、美術の神童として知られていた。中学生の時には、すでに上野で開かれる《桔梗展》に入選をはたし、それ以降、毎年新作を出品している。原田勝正という地元にいる西洋画の大家の門下におり、《永紫会》という大きな美術団体にも属している。彼の理論武装した前衛的な画風には早くもファンが付いており、銀座の画廊でも絵の取り引きがある。したがって、学校の教授や他の生徒たちも、彼には一目置いているのである。
「うーん、画に描いたような敵 役だなあ」
と、紫苑が腕組みして彼の様子を見定める。
「おいおい。シオン、人の悪口はそれくらいにしておけよ。自分の気持ちが醜くなるだけだぞ」
達観した口調で諭したのは、真梨央だった。側にある椅子を引き寄せ、長い足を組んで、彼は舞台監督のようにそこに腰かける。
「はい、すみません」
さすがのシオンも、真梨央に注意されると素直になる。
「ホントに、シオンって、一言多いんだからあ」
と、留美子が混ぜっ返した。
「加々美先輩。今度は、自分が話をしていいですか」
スポーツマンのような堂々たる体格で前へグイッと出てきたのは、二年生の日野原剛だ。よく日焼けした顔。角張った顎、太い首。少し肌寒く感じることもあるこの十月の上旬に、ノースリーブのシャツとジーパンという格好。露出した肩や胸も筋肉隆々である。額には、ランボーみたいにアイヌのバンダナをしている。
日野原の大学での専攻は、私と同じ彫刻科。どちらかというと近代彫刻の方が好きだ。だから、彼は作品を作る際の材料を選ばない。金属類の切断や溶接もお手の物だ。ウエイト・トレーニングをしているのは、そういった重量級の素材に負けない肉体と体力を作るためだと言う。
「うん。やってくれよ」
私は言い、少し下手に下がって彼に場所を譲った。
「読者の皆さん、自分は日野原剛であります。タケシって呼んでください。将来の夢は、自分の作品がどこかの近代美術館の敷地に飾られることです。岡本太郎の《太陽の塔》のような、なるべく大きなモニュメントを造りたいですね。付き合っている女性はいません。現在、恋人募集中です。優しい性格の女の子を期待します」
「えー、タケシさんて、ホモじゃなかったの!?」
シオンがまた素っ頓狂な声を上げた。
「何でだよ。何で、この俺様がホモなんだよ!」
日野原はごっつい顔を前に突き出し、シオンに言った。彼は普通に喋っていても声がやたらに大きい。
「だってさ。いつもそんなマッチョな格好をしているし、女の子を連れているのを見たこともないし」
「馬鹿を言うなよな。そうか、シオン。そんなに俺様のことが気になるなら、なんなら、お前を恋人にしてやってもいいんだぞ。もっと近くへ来いよ、ほら、きつく抱きしめてやるからさ」
「うわあぁぁぁ。いやだあああ。たすけてええぇぇぇ――」
「あーらら、シオンたら、逃げちゃったわ」
と、留美子が嬉しそうに言う。
楽屋の方へ逃げ込んだ紫苑を見て、私たちも全員ゲラゲラ笑った。
「次は、私でいいでしょうか」
上品な感じで確認したのは、一年生の加嶋友美だ。
彼女はそれほどの美人ではないが、丸顔にくりっとした目が愛らしい。黒い髪は、額の中央でハート型に分けて両側に流してあり、黒目がちな瞳と共にエキゾチックな印象を与えた。体格はどちらかと言うと肉感的なタイプで、白いブラウスに包まれた胸がはち切れそうに盛り上がっている。デニムのズボンも、腰から太股にかけて豊かな曲線を描いている。
「こんにちは。理知的な性格で、事件を冷静に観察する役割のはずの加嶋友美です。次に出てくる《ダルマ》君こと木田君と同じで、この大学の一年生です。専攻は日本画。水墨画や屏風絵、浮世絵についてなら博識なんですけど、残念ながら、《奇跡島》にあるのは西洋骨董ばかりですから、あまりいいところが見せられないかもしれません」
「それより、友美ちゃんが、真梨央さんの新しい恋人だってこと、ちゃんと説明した方が良くないかな」
と、日野原が爽やかな顔で付け足した。
友美はちょっと顔を赤らめたが、当の真梨央は、私たちの後方で椅子に座ったまま他人事のように澄ましている。彼はもともとあまり表情を変える方ではない。
「あら、自分で言うんですか」
そう答えながら、友美はまんざらでもない顔をした。
「言えばいいじゃないか、友美」と、吐き捨てる感じでせせら笑ったのは、榊原だった。「別に隠しておくこともないしな。そうだろ、真梨央?」
年上であり、リーダーでもある真梨央を呼びつけにするのは、傍若無人な彼だけである。
真梨央は物憂い表情で返事をした。
「ああ、隠す必要はないな。だが、自分から言いふらすような性質のものでもない。だから、話すなら、また加々美にやってもらうのがいいだろう」
私は、みんなの意見を聞こうと顔を見回した。しかし、誰も何も言わなかったので、結局、私が議事を進行するしかないようだった。
「別に僕が言うこともないのですが、麻生さんと友美は、彼女が今年入学して、このサークルに入った時から、すぐに付き合い始めたんでしたね。どっちかと言うと、友美の方が積極的だったと思います。正直に言えば、僕らは何故、麻生さんが友美とそういう仲になったのか、よく解らないです。だいたい、友美は、以前の麻生さんの好きな女性のタイプじゃないので、もしかして……」
「まあ、ひどい」と、友美が真剣に怒った顔をして口を挟んだ。「加々美先輩。いくら何でも、それはひどいですわ。それじゃあ、まるで私がたいへんなあばずれみたいではありませんか。私が真面目に麻生さんとお付き合いをしているのをよく知っているくせに……」
友美が唇を尖らせ、少し涙ぐんだ。
「あ、ごめん。ごめん」
弱った私はチラリと真梨央の方を見たが、彼は相変わらずどこ吹く風という顔をしている。
「……あのお、すみません。おいらの番はまだでしょうか」
弱々しい声がどこからか聞こえた。見ると、日野原の背後に隠れるように立っていた木田純也だった。通称は《ダルマさん》。その渾名のとおり、かなり太っている。
「急いで顔出しをしておかないと、頁もなくなるし、島への船が出ちゃうかもしれないですよねえ」
「そう思ったら、遠慮なんかせず、さっさと喋ればいいだろう」
タバコを深く吸った榊原が、紫の煙を彼の丸い顔に吹き付けた。
「そ、そおですか」
木田は、牛乳瓶の底のような厚いレンズの眼鏡をかけている。その奥で、小さなドングリ眼が怯えたように左右に動く。直毛の髪は少し脂質で、前髪が長く、七三に分けてある。色白で太っている上、背が低い。体格はビア樽のようだ。彼はたいへんな本の虫で、なかなかの知識人だが、どちらかと言うと、アニメ・オタク系の人間を想像してもらえば間違いない。
「あ、あの、何を言えば、いいんですか」
「好きな女の子のタイプは?」
紫苑の声だった。いつの間にか戻ってきていて、留美子と友美の間から顔を出している。彼はふざけて言ったのだが、木田は真に受けて、顔を真っ赤にした。
「え、ええ。好きな、タイプですか。あのう、そのお……」
榊原がふんと鼻で笑った。
「ダルマ、そんなことはどうでもいいよ。お前の専攻とか、趣味とかを言え。時間の無駄さ」
「は、はい」木田は榊原にいつも虐められているので、まったく抵抗ができない。「ど、読者の皆さん、おいらは、工芸科に通っている木田純也です。青森の出でして、どうも訛りが抜けないんですが、まあ、それは誇りに思っているぐらいですので、そんなに恥ずかしくはないです。ええと、工芸科を選んだのも、ゆくゆくは地元に帰って茶器を焼きたいからです。いずれ、自分の窯を持てるようになったらいいですね。
好きな物は本ですね。とにかく、本がないと生きていけません。特に、推理小説には目がありまっせん。チェスタートンとアントニー・バークリーがお気に入りです。あ、あの、年齢は十九歳です。血液型はO型。星座はやぎ座です。食べ物は、ラーメンと餃子が好物です……ええと、あのう、こんなもんで、自己紹介はいいんでしょうか。先輩方?」
「いいんじゃない」
と、お気楽に答えたのは留美子だった。
「……というわけで、加々美さん、これで全員、島へ行く者が揃ったわけだね」
と、紫苑がうきうきした声で言った。
「ああ、うん」
私は曖昧に頷く。
6
私は読者の便を計って――というか、作者がそうしろと命じるので――今まで出てきた人物を一覧にすることにした。参考にしてほしい。
《ミューズ》のメンバー
加々美光一 如月美術大学、三年生。
麻生真梨央 同、四年生。
加嶋友美 同、一年生。
日野原剛 同、二年生。
武田留美子 同、三年生。
榊原忠久 同、四年生。《画伯》
木田純也 同、一年生。《ダルマ》
武田紫苑 如月付属高校、三年生
「なるほど、この八人が、《奇跡島》へ渡る仲間たちか……」
と、真梨央が遠い目をして言った。その言い方には、どこか虚無的な響きがあった。そのため、私たちはみな何か胸に小さな不安を感じた。
「八人がどうした」と、榊原が唇をへの字に曲げて言った。「十三人よりは不吉じゃないだろう」
紫苑は、みんなの顔をキョロキョロと見た。
「でもさ、作者は何だって、このプロローグでこうやって、みんなの名前を加々美さんに並べさせたりするの?」
「そ、それはですね」と、木田が最初に口を開いた。「たぶん二階堂黎人が、この小説で、《犯人当て》をやろうとしているからじゃないですかね」
「犯人当て? それって、なあに?」
留美子が小首を傾げて尋ねる。
「推理小説におる常套的な遊びなんですよ。推理小説の登場人物の中には、当然、被害者と犯人がいるわけですよね。ですから、最後の解決の前に、作者が《読者への挑戦》を挟んで、お前に犯人が解ったかと、読者に対して思考上の戦いを挑むわけです。読者が犯人を推理できれば読者の勝ち、推理できなければ作者の勝ちってことなんです。そのためには、もちろん、解決を納得いく形で提示するための手がかりと伏線が、物語中にちゃんと挿入されている必要があるんですがね。よく論理的な推理小説っていう言い方をするのは、データーの出揃っているそういう形のもののことです」
「手がかりがないといけないわけ」
「当然です。それがなくて、解決だけが何の脈絡もなく、最後にポンとポケットから出てくるように書かれているのは、絶対に《推理小説》とは言えないんです。そんなのは偽物ですよ。都合のいいことに、現在はそういう曖昧なものを、単に《ミステリー》とか《広義のミステリー》と呼ぶ慣例があります。おいらのようなマニアに言わせると、プロットを立てずに適当に書いているようなものは、《推理小説》というラベルを貼っちゃあいけないんですよ」
「へえ、違うんだあ」
と、留美子が訳も解らないのに感心する。
紫苑が目玉をクリクリ動かして、
「あ、ボク、解った。今朝の新聞に、ベストセラー・ミステリー作家のXXXXの新作の広告が出ていたんだけどさ。そこに、『名探偵・●●●●の推理が冴える!』って書いてあったんだ。でもさ、本当は、『名探偵・●●●●の思いつきが冴える!』って書くべきなんだよね!」
木田は、鏡餅のような顔に浮かんだ冷や汗を袖で拭きながら、
「……シオン君。それはずいぶん危ない発言ですね。削除ものですよ」
「そう?」
「ええ……そ、それはともかく、登場人物一覧まで出て来たってことは、きっと間違いなく、この小説の終わりの方に、《読者への挑戦》という頁が挟まれているはずですよ。手がかりはすべて出揃った。読者諸君よ、犯人の名前をみごと看破してみよってね」
日野原がゴリラのように胸を叩きながら、
「ということは、このメンバーの中に犯人がいるっていうことだね。よし、自分がとっつかまえてやる!」
「被害者もいるということですよ」
「ほえ~」と、紫苑が両手を振り回し、金切り声を上げた。「いやだあ。僕は。死にたくない。死にたくない。犯人になるのだっていやだよお。絶対に生き残ってやるう。独裁者。悪魔。ヒトラー。サタン。チンチクリン。作者の横暴だ。二階堂黎人のば~か。お前なんか嫌いだぞ!」
「今さらそんなことを言っても仕方がないさ。それより、加々美。この八人以外には、登場人物はまったくいないのか」
と、榊原が新しいタバコに火を点けながら、私に尋ねた。
「僕は知りません」
私は正直に答えた。嘘ではなかった。
「そうだ。真梨央さんが知ってますよね。さっき、そう言ってましたよね」
真梨央は小さく頷いた。
「ああ。知っていることは知っている。この他に、三人ぐらいの人間が出てくるようだ。だが、それはたいした問題ではない」
「どうしてだ?」
榊原が尋ねた。
「そいつらは、たぶん脇役だからだよ。主役級は、俺たち八人だけだからさ。だから、俺たちだけが、ちゃんと血肉を持って、目立つように書けていればいいんだ」
「本当に、そうなんですか。麻生先輩」
木田が脂ぎった前髪をかき上げ、分厚い眼鏡の奥から小さな瞳を彼に向けた。
「うん?」
「今も言いましたが、これは推理小説なんですよ」
木田が珍しく口答えしたので、真梨央の表情に、微妙な感情が浮かんだ。
「推理小説だから、どうしたと言うのかね」
「何か、作者に特別な意図があるかもしれないってことですよ。最近の推理小説には、読者を欺くための様々な仕掛けが企ててある例が多いんです。この本の作者が作者ですからね、そんな簡単な話で終わるとは、おいらには思えないですよ」
「作者が作者って、どういう意味なんだい」
私は尋ねた。
「何だか、自分で自分のことを、《トリック至上主義者》とか言って威張っているみたいなんです」
「どんな仕掛けがありそうなのですか、木田さん」
と、友美が質問をした。
「たとえばですね、ここで紹介した人間たちの間に犯人が混じっているように見せかけておいて、ぜんぜん怪しくない脇役の中に隠しておくとかです。あるいは、その脇役の中に、実際にはこの八人のメンバーが変装して隠れているとかですよ。後の場合には、今ここで、実際にその人間を紹介するわけにはいかないですからね。それで、他の人たちの紹介がないわけです。それは、充分に考えられますね」
「なるほどね」
と、私は頷いた。
「しかも、題名を見ても、この話が《孤島もの》だというのは明らかです。となると、孤島という閉鎖空間を利用して、小説中に、何か特別な趣向を盛り込もうとしているのは充分推察できる話です」
「《孤島もの》って、何だい?」
と、日野原が二の腕に力瘤を作りながら尋ねた。
「登場人物たちが、島へ渡り、その島が時化か何かで外部から隔絶されてしまうんです。で、そういう危機的な状況の中で、さらに殺人事件まで起こるんですよ。まさしく、絶体絶命っていう設定でしてね。で、この閉ざされた空間の中では、容疑者が限定されているだけに、事件が進めば進むほど、犯人が誰だか解らない点で不可解が増すんです。アガサ・クリスティーの『そして誰もいなくなった』とか、綾辻行人の『十角館の殺人』なんていう推理小説の名作の名前、知らないっすかあ」
「自分は知らないな」
日野原は素っ気なく答える。
「ちょっと待ってくれないか」と、私は口を挟んだ。「ダルマだけじゃなくて、みんなに注意したいことがある。この物語は、この本が刊行される一九九六年の十年前、一九八六年の十月上旬に事件が設定されている。僕らが島へ渡った日は十月十三日の月曜日だ。だから、本文が始まってからは、気を付けて欲しいんだよ。それ以降に出た書物だとか、テレビや映画の名前なんか出すと、校閲の人や編集さんに迷惑をかけるからね。『十角館の殺人』って、一九八七年の刊行だから、会話に出てくるとまずいぞ」
「そうですね。これから、充分留意します」
木田は素直に反省した。
「そうか!」と、また、紫苑が手を叩きながら大声を上げた。「この本てさあ、もしかして、最近はやりの《メタ・ミステリ》って奴かもしれないね!」
「何、それ」
留美子が、長い睫毛をパタパタとしばたたいた。
「ルミちゃん、知らないの。遅れてるう」
「何よ」
「へへへ。実を言うとね、本当は僕もあんまり詳しくないんだ。だけど、どうやら最近出ている推理小説に多い、読者を引っかけるための手段らしいよ。叙述的トリックとか言っちゃってさ、文章の書き方で、男を女に間違えさせたり、年寄りを若い人物に間違えさせたりして、読者を煙に巻くみたいなんだ。この頃人気のある《新本格推理》とかっていうのは、みんなそれだって、僕がこの前読んだ同人誌に書いてあったよ」
「よく、解んない」
留美子は小首を傾げた。
「私もです」
と、友美がさらさらの髪を撫でながら相槌を打つ。
「卑怯みたいだな」と、日野原が挑むような顔をする。「そんな卑劣な奴は、自分が退治してくれる!」
木田が、説明役を紫苑と交代した。
「シオン君の言うとおりですね。確かに、《メタ・ミステリ》かもしれないですね」
「というと、どういうことだい」
と、日野原は歯をむき出して迫る。
「たとえばですね、今、友美さんは《友美》っていう名前で、しかも、女言葉で話をしていますっよね。その上、真梨央さんと恋人同士だって説明しているあります。とすると、友美さんのことを読者はどう思いますか。男ですか、女ですか」
「女に決まっているじゃないか」
「ところが、それが決まっていないんすでよね。作者は地の文章で、一言も、友美さんが女だとは書いてないんです。語り手に選ばれた加々美さんも、今の所、一言もそんなことは言ってないですよね。つまり、本当は《友美》っていう名前のオカマさんなのかもしれないんですよ。で、事件が起きた時に、被害者の傷の損傷具合や凶器の特性から、犯人が男であると推定された場合に、友美さんは、読者の目からは嫌疑の外に置かれるというわけなんですね」
「そんなあ、私、本当に女です」
友美は抗議した。
「でも、それが叙述的トリックって奴なんですよ」と、木田は熱心に弁護した。「しかし、本質的な意味での《メタ・ミステリ》の説明は、シオン君が言っただけでは不充分なんですよ。というのは、推理小説は、ポーが生み出した瞬間から、次の作品は自ずから前の作品の物語やプロットやトリックを乗り越えていかなくてはならない運命にあったからです。つまり、《メタ》というのは《超える》っていう意味ですから、技法についてだけではなくてですね……」
「もうやめろ、そんな話は」と、榊原がタバコを揉み消しながら言った。「くだらない屁理屈は聞きたくねえよ。問題は、俺たちが《奇跡島》に渡る運命にあり、しかも、死ぬかもしれないってことじゃねえか。そっちの相談の方が大事だ」
「あたし、死にたくな~い」
と、留美子は両手を目頭に当てて、泣き真似をする。
「私だってです」
と、友美も眉をひそめた。
「誰だって、死にたくねえよ。しかし、あきらめるしかない。所詮、俺たちは作者が生み出した空想上の人間だ。物語という将棋の盤上で、作者の都合の良いように動かされる一個一個の駒にすぎない。そんな駒をつかまえてだな、人間が描けているだのどうのと、つまらない御託を述べても時間の無駄なんだよ」
「じゃあ何ですか、画伯さん。私たちに、おめおめ犯罪者の毒牙にかかって殺されろって言うんですか。私は嫌です。せっかく、大好きな麻生さんと恋人同士になれたって言うのに。これから、私たち二人には薔薇色の人生が待っているかもしれないんですよ」
「友美よ」と、榊原が珍しく、同情の色を目に浮かべた。「そんな薔薇色の未来が存在するかどうか、真梨央の顔を見てみろよ。奴が一番、そのことを知っているんだから」
皆はいっせいに、真梨央の方へ顔を向けた。
真梨央は仏像のように無表情だった。深い沼のように静まり返った目で、彼は私たちを見返した。
「俺は何も言うことがない。ここで、俺たちがいくら議論したって無駄だからだ。このすぐ後の頁から、《奇跡島の不思議》という小説が本格的に始まる。舞台は孤島だ。そうなったら、物理的にも観念的にも俺たちには逃げ場はない。俺は運命論でも悲観論者でもないが、なるようにしかならないだろう」
私はためらった後に、言った。
「麻生さん。本当にそれでいいんですか。抵抗するなら、今この瞬間しかありませんよ。小説の中の登場人物にだって意志があります。僕らは人格を持っている。ここで僕たちが作者に強行に出たくないと言えば、出なくてすむ可能性はありますよ。そうすれば、死ななくてすむかもしれない」
「無駄さ、俺たちが出なけりゃあ、作者は他の登場人物を用意するだけだ。そして、小説に出ない登場人物など、最初から存在意義もない。抵抗なんかできはしないさ」
「そうですか……」
私は渋々頷いた。そして、他の仲間たちを見回した。皆、恐れをいだきながらも、勇敢に私の方へ真摯な視線を送っている。
「加々美。話を始めてくれ」
と、真梨央は命じた。
「他のみんなもいいのですね」
私は最終確認をしたが、誰も反対をしなかった。
私は息を飲み、決意した。ここで前口上を述べることが、紙より体積の少ない私の薄っぺらな存在価値に繋がる。
「それでは、読者の皆さん。あらためて申し上げます。いよいよ、本格的な推理小説《奇跡島の不思議》の開幕です。《奇跡島》で何が起こるのか、誰が殺され、誰が生き残り、何者が犯人なのか。そして、この島に発生した途轍もない犯罪の正体とはいったい何なのか。それはすべて、この《孤島の連続殺人事件》を読んでもらえれば、いずれ解ることです。そして、できれば途中で自分でも推理しながら、頁をめくってください――」
「あ、待って、待って、加々美さん!」
大あわてで、紫苑が口を挟んだ。
「何だい」
「さっきさ、《奇跡島》という場所について語るって言ってたじゃない。どういう島か説明するって。でも、まだ何にも言ってないよ」
「いいんだよ」と、私は言った。「作者は、次の章で説明することにしたから」
「へん。勝手な奴だな」
榊原は、そっぽを向いて悪態をついた。
私は苦笑いをした。そしてもう一度、読者の皆さんの方を向き、軽く丁寧に頭を下げる。
「それでは、皆さん、最後にもう一度お尋ねします。心の準備はできましたか。それでは、今度こそ本当に《奇跡島の不思議》の物語を始めます。どうか、最後まで怒らずに読みきってくださいね。
そして、できれば、この事件の犯人が誰か、文中より手がかりを捜し、証拠を集めて、人物の心理を解析して推理してみてください。犯人と探偵を代理とした作家と読者の知的闘争こそが、推理小説の醍醐味ではありませんか――では、ついに死を巡る迷宮的な物語の幕が上がります」
《続・読者への挑戦》
ではふたたび、謹んで読者へ挑戦する――。
推理小説界における数々の先人の例にならい、筆者もここに読者への挑戦を重ねて挟むことにした。
孤島の連続殺人鬼は誰か。
また、動機は何か。
そして、殺人の裏に潜んでいる謎の正体とは。
この後、名探偵氏がすべての残された謎を解き明かすために推理を披露する。その際に活用する厳密なる手がかりと物証を、この頁までで、読者も名探偵氏と同等につかんでいる。筆者はそれを保証する。
誤りなく犯人を指摘するに足りうるだけの解答は、一連の論理的推理と心理的な観察を持ってすれば、実に簡単に提示できるはずである。
ぜひとも、この頁において灰色の脳細胞をフル回転させ、《奇跡島の不思議》における数々の謎を解明してもらいたい。そして、その頭脳の活動で、名探偵氏とこの筆者の知恵と知識を圧倒してもらいたい。
推理小説を愛し、明敏なる頭脳を備えた読者に、作者の仕掛けた謎を解かれ、罠を看破されるならば、筆者はむしろ光栄に思うものである。
よもや、ここまで来れば、読者諸氏に真相が解らないなどということはあるまい――。
第18章 仲間たちの饗宴
1
地獄を見た――。
長い物語が終わった際の私の感想は、まさにそんな感じだった。何しろ、話が始まった時には、まさか自分が犯人にされるとは思っていなかったし、自殺して最期を遂げるなどという打ち合わせもぜんぜんなかったからだ。
やってみると、死ぬ振りというのは、けっこう大変だった。私は自分の性格を、単に優柔不断な男だと思っていた。だが、この小説の最後であらわになった私は少し違っていた。自分のことを熱愛してくれる一人の女を毛嫌いし、死んでしまった別の女の面影をいつまでも執念深く思い続けている。死者へ向けた邪悪な思慕を、殺人における絵画的手法によって情念として島の空間上に展開する――一介の芸術家気取りなのだろうが、なんて陰気な奴なんだろうというのが、自分で自分に対する率直な感想である。
嫌な奴と言えば、風来坊というあの名探偵も、私にとっては嫌な奴だった。飄々としていたり、やたらにニヤニヤして、一見するところ軽薄が洋服を着ているような奴だが、深く澄んだ目をこちらに向け、私の心を見透かすような仕草や、妙に鋭い発言をする。あいつがいなければ、私の犯行はきっと成功して終わったに違いない。私のせっかくの芸術的作品に、あの男がケチを付けたのだ。だから、私があいつを憎むのも当然の権利と言えよう。
ところで、最初の章の冒頭における私の記述を読み返してもらいたい。まるで、私は島から生き残って帰ってきたかのような書き方がされている。こういう嘘に近い表現方法は、ダルマの奴に言わせると、推理小説では《アンフェア》というらしい。この小説は、本格推理を称しているくせに、そんないい加減なことをしていいのだろうか。
そこで、私はふと疑問に思った。もしかして、作者の二階堂黎人は、本当はこの物語を書き出した時に、結末をちゃんと考えていなかったのではないだろうか。少なくとも、私以外の者を犯人にしようと考えていたくせに、何かの理由があって、急遽この私を犯人に変えたのではないだろうか。
どうも、この考えは当たっている気がする。それについては、後でじっくりと作者を問いつめる必要がありそうだ。
話は変わるが、私は今さっきシャワーを浴びて、口の中をよくゆすいで――それにしても、あの絵の具の代わりに口に入れた芝居用の顔料の気持ちの悪いこと。味も感触も最低だった――髭を剃り、着替えて、やっとこうしてくつろいでいる。ついでに言うと、中世の古い絵の具ならともかく、最近市販されている絵の具だと、それほどの毒性はない。したがって、あんな真似をしても容易には死ねない。専門家から指摘される前に、ちゃんと押さえておこう。
私が今いることになっているのは、幕が下りて観客が返った後の舞台上だ。背景などの大道具はまだあるけれども、閑散として実に静かだ。つい先頃まで、ここで血腥い殺人劇が繰り広げられていたとは思えないほどだ。
私は、自分が主演したこの長い物語を思い返してみた。実に悲惨な役どころだった。ずいぶん重たい動機を持った人間にされたものだ。永遠に自分のものにできぬ女神を愛し、その幻影をつかまえようともがき、そして、失楽していく男。悲しい性だ。悲惨でもある。私は、自分で自分が可哀相になった。
おや? 舞台の袖の方から、ガヤガヤと物音や話し声が聞こえてくる。そうか、みんなも来たのか。
「おーい、ここだよ」
私は手を上げ、声をかける。
「やあ、待たせたな」
と、先頭にいた真梨央が晴れ晴れとした顔で返事をした。
私は舞台に戻ってきたメンバーを、一人一人を見る。権堂さんや管理人夫婦、風来坊君はいなかった。ミューズのメンバーだけだった。
「加々美く~ん!」
「加々美さ~ん!」
後から留美子と紫苑が競うように駆けてきて、私に体当たりした。留美子は左手で茶色のテディベアをかかえている。衝撃で、私は何歩か後ろによろけた。
「痛いなあ」
私は顔をしかめたが、留美子はますます私にピンクの頬をすり寄せ、
「あら、シオンが悪いのよ。加々美くんに謝りなさいよ」
「何言ってんだよ、悪いのはルミちゃんだろ。女の癖に、もっとおしとやかにできないの」
「すっごーい、それって、へんけーん!」
「へんけんでも何でも、本当のことですよお!」
留美子と紫苑は、それぞれ私の右腕と左腕を取り――留美子はテディベアを横に投げ捨てて――いつもの諍いを始めた。やれやれ、また、この二人の痴話喧嘩に付き合わなくてはならないのか。
他の仲間たちは、そんな私の災難をニヤニヤ笑って見ている。
「あ、そうだ!」と突然、紫苑が大声を上げる。「ねえ、加々美さん。ちょっとさあ、作者に文句言ってよ。ひどいんだよ」
「ひどい?」
紫苑は私の手を離した。そして、すました顔で斜め横上を向くと、左手を腰に、右手をこめかみあたりに置いて、気取ったポーズを取った。
「そうだよ。ボクみたいな美少年が出る場面ではさ、必ず、背景にバラとかの花を背負うっていうのが、お約束じゃない。それから、時々、ボクのファンの女の子に顔見せをする一コマを挿入するとかさ。そういうステキな場面がぜんぜんないんだもん。おかしいよ。それこそ、ファン・サービスってもんでしょうに」
「あ、知ってるもん」と、留美子が得意気な声を上げる。「それって、河あきらの『いらかの波』というマンガで、元生徒会長っていう人が言ってたことじゃない。真似してるう!」
「真似じゃないよ。ボクみたいな美少年の特権のことだよ」
「だったら、あたしみたいな美少女は、三段ぶち抜きで全身を描かなきゃあ」
と、留美子も負けずに、片足を跳ね上げるポーズを取った。
私は笑いながら、
「ははは。だめだめ。小説の作者って、マンガの作者と違って、アシスタントはいないんだぜ。台詞も地の文も全部一人で書くんだ。背景やコマ割りや、どうでもいいところでの見せ場に凝る余裕なんかないよ」
「そうよね」と、大きな目をしばたたき、長い睫毛を震わせて留美子が言う。「だいたい、シオンって、欲張りじゃないのお。シオンなんか、一番最後まで出番があったんだから、それでいいじゃない。あたしなんか、半分しか出演できなかったんですからね。ホントに、意地悪な作者だわ。ダイッキライ!」
私は二人の小言を聞きながら、真梨央の後ろにいた日野原の顔を見た。
「タケシ。ずいぶん、久しぶりじゃないか」
ちょっと笑いかけると、彼は開口一番言った。、
「いやあ、加々美先輩。自分はまいりましたよ」
「何がだい」
彼はバンダナを巻いた頭の後ろを、大きな手で撫でながら、
「まったく、自分がこのメンバーの中で一番最初に死んでしまうなんて、考えてもみませんでしたよ。ランプシェードに押し潰されて死ぬのなんてのも、変な死に方でつらかったけど、早々と物語の中から退場しちゃうんで、あと、暇を持て余しちゃって」
「死人らしい顔は、充分うまかったぞ」
と、真梨央が後ろを見て、からかった。
日野原は照れて、ますます頭をかき、
「いやあ、みなさんがいる時、息を止めているのはけっこうたいへんでした」
「でも、タケシ君はまだ楽な方ですわ」と、口を尖らせて文句を言ったのは、加嶋友美だった。「私の場合は、溺死でしょう。汚い池の底に、息を止めて沈んでいなくちゃならなかったんですもの。水は冷たいし、水草はヌルヌルして気持ち悪いし、あんな役は二度としたくありません」
真梨央は彼女の顔を愛しげに見ると、長い顎を撫でながら、
「そうだな。今回の事件で一番ひどい目に遭ったのは、友美かもしれないな。御苦労様。でも、迫真の演技だったぜ」
「えへん。そうかしら」
友美はこじんまりした鼻を上に向け、ちょっと得意気な顔をした。
「ボク、ダルマさんは、絶対に殺される役だと思ったんだけどな」
と、紫苑が残念そうに言う。
木田は目をクルクル動かし、
「ど、どうしてっすか、シオン君」
「だって、オタクっていうキャラクターってさ、こういう孤島の連続殺人では、たいてい犯人になりにくいもの。探偵になるにも格好が悪いでしょう。だとすると、途中で簡単に殺されちゃうってのが、常套じゃないの」
「あー、あたしもそう思う!」
と、留美子が手をパチパチ叩いて喜んだ。
木田は恥ずかしそうに赤くなった。
「そんなことはないっすよ。だいいち今回は、おいらは一応探偵の役ですよ。そりゃあ、間違えた推理をする三枚目ですが、おいらがいないと、話が進まなかったじゃないですか」
「まあ、そうだけどね」
紫苑は納得した。
「じゃあ、俺はどうだ、シオン。俺みたいに嫌味なタイプも、途中で殺される役なんじゃないのか」
タバコをくゆらせながら、榊原が口を挟んだ。
「ううん、そんなことはないよ。だってさ、画伯さんが死んじゃったら、疑わしい人物がいなくなっちゃうじゃない。この事件って、結局、美術史観を元にした動機による殺人劇なわけでしょう。だとしたら、画伯さんのような蘊蓄を傾ける中心人物がいないと、話が成り立たないと思うんだ」
「おい、シオン」と、私は声をかけた。「お前、本当は誰が犯人だと思っていたんだ?」
「ボク? ボクは、みんなのことを信じていたよ」
「へえ?」
「だってさ、これって、《孤島》+《館》+《クローズド・サークル》ていう欲張った殺人事件を扱った推理小説でしょう。だったらさ、一番最後になって、ドンデンガエーシ!って感じでさ、死んだと思われていた人が突然出て来た方が、見映え――というか読み応えがいいじゃない。だから、八代百合夏っていう悪魔のような美女が、《白亜の館》にある秘密の部屋か何かにこっそり住んでいてさ、密かにみんなのことを見張っているんじゃないかって、想像しちゃったんだ。残念ながら、そうじゃなかったけどね」
「操り――《陰からの操り》ですね」
と、木田が訳知り顔で言った。
「何それ?」
「事件の背後にいる影の人物のことですよ。その邪悪な心を持った人物が、実は別の犯人を陰から操って事件を起こし、あまつさえ、事件全体を手中に収めているんです。この事件の場合で言えば、今、君が言ったように、八代百合夏か、その祖母なんていう人がすごく怪しいですよね」
「へえ、そんなのがあるんだ」
「そうですよ。クイーンの『十日間の不思議』とか、クリスティーの『ABC殺人』などはぜひ読んでみるといいっす。とても面白いですからね」
「うん」
「ところでですね」と、皆の顔を見回しながら言ったのは友美だった。「私、ちょっと解らないことがあるんですけど」
「何だ?」
と、真梨央が答える。
「あの風来坊さんていう人、いったい誰だったんですか。名前を最後までちゃんと言いませんでしたよね。それに、私、途中で死んでしまったでしょう。だから、船で帰る時に、紫苑君と彼が話をしている場面も見ていないんです」
「あの人は、和菓子屋の息子だよ」
と、紫苑が素っ気なく答える。
「それは、解っていますけど……」
と、友美はすねたように言う。
「えへん」と、木田が咳払いをした。「おいら、あの人が誰だかちゃんと解っているっすよ。では、説明いたします。彼はですね、作者の二階堂黎人が作り出した名探偵の内の一人なんです。名前を言っちゃうと興醒めになるんで、イニシャルだけお教えします。S・Mです――サド・マゾじゃないですよ。
彼は、この物語の十年後にはある旅行会社に務めていて、軽井沢で起こったへんてこな事件でも名探偵ぶりを発揮するっす。和菓子屋の息子っていうのと、お姉さんが三人いるっていうのが決め手になりますね」
「まあ、それで解りました。S・Mさんだったんですか」
「そうしたら、もう一人の方は知っていますか、友美さん。話の途中で、誰かが、戦前の《奇跡島の不思議》事件を解決した巻き毛の名探偵のことに言及していたじゃないですか。その女性の方の名前ですが」
「あ、あれは私も知っています。縦巻きロールの美人と言えば、お蝶夫人――じゃなくて、R・Nさんですよね。東京の国立市に住んでいる」
「あたりっす。さすが、友美さんですね」
私はやれやれと思った。結局、この長い小説は、登場していた探偵の名を隠しておき、最後に正体を明かして読者を驚かすという例の手だったのだ。そんな趣向をしたいがために、これだけの頁数を費やすのだから、本当に推理小説作家というのはおかしな人種だ。
その時、私は紫苑が妙な行動を始めたのを見た。何をしだしたかというと、こうして文字として書かれている自分がいる頁の縁まで移動して、頁をめくり、前の方を一生懸命に覗いているのだ。ちょうど、あなたの右親指が置かれている上あたりです。
「読者さん、ちょっと、その手邪魔だよ」
紫苑は熱心に紙をめくりながら、あなたに文句を言う。
「――何をしてるんだ、シオン?」
私は彼の背後まで行き、尋ねた。
紫苑は、不思議そうな顔をして振り返った。他の者たちも、訝しげな顔をしてこちらを見守っている。
「ねえ、変だよ、加々美さん」
「何がだ?」
「だって、この章の前の頁を見てごらんよ。変な頁があるんだ」
「ここは第十八章だから、前の頁ってのは、第十七章のおしまいの部分だろう。君と風来坊君が最後まで出ていた?」
「それが違うんだよ。いいから、見てごらんよ」
私は背中を押され、頁の縁から前の方を覗いてみた。本の端から外へ落っこちそうになり、ちょっと怖い思いをした。その時には、他のみんなもおかしな事態になっていることに気づき、私たちの所まで移動してきた。
そしてその頁を見た私は、紫苑の言っていることの意味が解った。
「ね、加々美さん」と紫苑は、恐怖がよみがえったように、私と目を見合わせて言った。「おかしいでしょう。事件は、ボクら生き残った者が船で《奇跡島》を去るところですべて終わったんだよね。なのにさ、どうして、第十五章のおしまいのところに続いて、また《読者への挑戦》が挟まっているわけ。それも、御丁寧に、《続・読者への挑戦》ってなっているよ。これ、どういうことなの。もしかして、まだ、実際は事件は終わっていないの!? そんなの、嘘だよね!?」
2
四つん這いになって本の縁から身を乗り出していた私は、立ち上がって膝の埃を払った。振り向くと、皆が青ざめた顔でこちらを見つめている。たぶん、私の顔も彼らに負けず色を失っていたことだろう。
「まさか、もう一つ、《読者への挑戦》があったとは夢にも思わなかったよ……」
「加々美さん、何故なんだろう。この後で、どんでん返しの解決があるなんてことはないよね!?」
紫苑がまた不安そうな声を出したので、私はなるべく落ち着いて返事をした。
「平気さ。事件はちゃんと完全に終わったさ。だって、この僕が犯人なんだぜ。他に犯人なんかいないよ。犯人が自分で言っているんだから、これほど確かなことはないさ。そんなに心配するなよ」
けれども、私の心は千々に乱れていた。
間違いない。私は第十七章で、事件についての自白をした後で自殺をしている。自分がやったことは、きちんと記憶にある。殺人者は私に決まっている。そうさ……。
榊原が、脇から紫苑の肩を軽くこづいた。
「おい、シオン。くだらないことを考えるなよな。また、話が面倒になったらどうするんだ。俺はもう早く帰って寝たいんだ。すっかりくたびれたんだよ」
紫苑は怖がるような目で、コクコクと小刻みに頷いた。
「解ってるけどさ」
「大丈夫ですよ」と、胸を叩きながら請け合ったのは、木田だった。「これは、何かの間違いっすよ。編集さんが、著者に黙って勝手に差し込んだか、印刷の過程でどこかの他の原稿が挟まったんじゃないすか。そんなに心配することはないですよ」
ところが、誰もが怯えた表情のままだった。そして、互いに自分の胸中の不安を探っていた。
真梨央が意を決したように、
「みんな、少し冷静になってくれ。ダルマが言ったとおりかもしれないし、俺は、これは作者の間違いだと思う。今までこの作者は、自分の本の中に《読者への挑戦》を挿入したことはない。今回初めて、それができたので、ちょうと舞い上がってしまったんじゃないかな。過ちで、二つへの《読者への挑戦》を書き込んでしまったのさ」
しかし、榊原が眼鏡の奥で目を細め、
「いや、真梨央。それは違うな。俺には別の考えがある」
「何だ?」
「あれさ。さっきダルマも口にしたが、戦前、あの《白亜の館》を建築した龍門有香子というお姫様の死に関する謎がまったく解かれていない。すなわち、その謎を、俺たちや読者に解かせようとして、あんな回りくどい《続・読者への挑戦》などというものを置いたんじゃねえのか」
「でも」と、紫苑が訴えた。「風来坊さんは、事件を解決するためのデーターが足りないって言ってたよ。謎を解くなんて無理だよ」
「だが、それは風来坊が言ったことにすぎねえ。あいつが無能なだけのことだ」
「そんなあ!」
「ちょっと待て」と、真梨央が口を挟んだ。「もしかして、この後で、本当の名探偵が出てくるとしたら、どうだ。そして、その探偵が、謎をすっぱりと解き明かすんだ。今度こそ、あますことなくな」
榊原は皮肉な笑みを浮かべ、
「なるほどな。どんでん返しに継ぐどんでん返しって奴か。最近の推理小説の流行だしな」
木田が顔を突き出し、
「あれ、どうして、画伯さんが、そんなことを知っているんですか。画伯さんは、推理小説なんか読まない人だったじゃないですか」
「馬鹿。あれは物語の中の人格の話だ。実際の俺は、推理小説だってSFだって読むぜ。だいたいだな、今時の本と言ったら、書店に行ってみろ。半分近くがミステリーでもないくせにミステリーとか呼ばれているんだぞ。良識ある日本人として、無関心でいられるわけがない」
留美子が急に明るい顔をし、手を顔の前で組んでピョンピョンと跳ね上がった。
「ステキ! じゃあ、本当の名探偵って、誰が出てくるの? 誰? 誰? ピストルを撃っているみたいな名前の人とか、クイーン、バイシクルー、バイシクルーとか、馬に乗った白馬の王子様みたいな人とか、カマドウマが嫌いなあのお方のお友達かしらん!」
「やだな、ルミちゃんは」と、紫苑は冷ややかな目で自分の従姉を見た。「そんな人たちが出てきたら、出演料を別に取られるじゃないか。それに、著作権法違反だよ。この本の作者は二階堂黎人だって言っているじゃないか。そうしたら、出てくるのは、巻き毛の女名探偵に決まっているよ。もお。加々美さん、ルミちゃんに何とか言ってよ」
「あはは。巻き毛の人が出てきたらすごいね。豪華メンバー勢揃いだ。僕も見てみたいよ」
日野原が太い腕で腕組みし、真面目な提案した。
「とにかく、みんなで考えてみたらどうですか、あの謎を」
「いいよ」
と、紫苑。
「かまわないが」
と、真梨央。
「できるかな」
と、榊原。
「できるっすよ」
と、木田。
そして、友美が何か口にしようとした時だった。
「あらっ!」
と、彼女の顔色が変わり、続いて、
「キャッ」
と、可愛い悲鳴を上げたかと思うと、留美子が私にしがみついた。
「地震ですよ、先輩!」
と、日野原は言い、まわりをキョロキョロ見た。
舞台の上が小さく揺れている。確かに地震のようだった。その内に、その振動はますます強くなり、緞帳その他まで小刻みに揺れ始めた。
「地震じゃないぞ!」
と、驚くように言ったのは真梨央だった。そして、彼は、下手の方を指さした。
ズシン、ズシンという像が歩くような地響きが伝わってきた。足音はどんどん大きくなり、こちらに近づいた。
「何、あれ!? こわーい!」
と、留美子は悲鳴を上げ、私の胸に顔を埋めた。
「すごーい!」
と、紫苑が呆れた声を出した。
「人間じゃねえか」
と、榊原でさえ、口を半開きにして言った。
「本当に、人間なんですか!?」
と、木田は眼鏡の奥で目を凝らした。
床を震わせる足音と共に、喉をぜいぜい鳴らす音がし、さらに、
「ウオッホッホッ」と、ガラス窓が割れそうなほどの、老人の陽気な大声が聞こえた。「諸君。御機嫌はいかがかね。どうやら、ずいぶん、待たせたようじゃの! もう酒は飲んでおるか。男なら、酒を飲まねばならない。無論、ビールなら何パイントでもかまわん。おお、バッカスよ! ほほう、そちらの嬢ちゃんたち二人は、どうやら女じゃな。だったら、蜂蜜入りの紅茶が体に良いぞ!」
私たちは目を疑った。いまだかつて、こんな威風堂々とした風体の老人を見たことがない。まずびっくりしたのが、その体格だ。巨大なビア樽が歩いてきたかと思ったほどで、しかも、その重い体を支えるために、ステッキを片手に一本ずつ、二本も持っているではないか。体重は優に百二十キロ以上ありそうだ。苦しげに喉を鳴らしているのも無理はない。
まるまると太った顔を見ると、髪は白髪混じりの黒髪で、それを後ろへ軍旗のように揺らしている。顎は幾重にも脂肪でくびれており、顔は酒を飲んだばかりのように赤みを帯び、口元にかすかに皮肉っぽい笑みが浮かんでいる。
黒い立派な口髭があり、目は悪戯小僧のように生き生きと輝いている。学者然として、幅広の黒いリボンを付けた眼鏡をかけ、さらに、頭には黒のフェルト帽がのっている。黒いだぶだぶの服を着て、その上に、インパネスのような黒いマントを羽織っていた。
「何を、素っ頓狂な目をしておる!」と、その老人は我々の前まで来て立ち止まり、文字通り吠えた。「何か話をしていたのなら、わしにかまわず、議論を続けてかまわんぞ。わしが拝聴しておるからと言って、そんなに固くなる必要はない!」
真梨央は気を取りなし、
「あのう、失礼ですが、あなたはどなたですか」
と、おどおどしながら尋ねた。
老人の目が、眼鏡の奥で愉快そうに輝いた。
「わしか、わしの名は《増加博士》じゃ」
「増加博士?」
私たちは全員、それを奇妙な名前だと思った。私は一瞬、それは渾名なのだろうと考えた。
「そうだ。増加博士じゃ。老辞書編纂家と呼んでくれてもいいし、まあ、オホン、そのだな、警察の手伝いなどもしておるでのう、場合によっては、名探偵と呼んでもらっても、あながち間違いではないな」
「はあ」
「何を意気消沈しておる。若い者がそれではいかん。若い者は、血気盛んでなくてはつまらんぞ。フェンシングをしろ。剣を持ち出して、すぐに決闘を始めるくらい元気な若者がよろしい」
真梨央は襟を正して質問した。
「ええと、それでですね。増加博士は、ここへ何をしに来られたのですか」
「何をしに来たかじゃと!」
増加博士は気分を害したように怒鳴り、右手に持ったステッキを振り回した。
私たちはびっくりして頭をすくめた。
「何をしに来たかと、お主は尋ねるのか! これは驚いた。このわしを捕まえて、何をしに来たかと尋ねておる!」
「す、すみません」
さすがの真梨央も、長身を縮めてすくみ上がった。
「いや、謝ることなどない。まあ、よかろうて。わしは、あまり神経質な方じゃないからな」
「は、はい」
「わしは、お主らを助けに来たのじゃよ。お主らが困っていると聞いて、手助けに来たわけさ。わしは、いつでも若い者の見方なのじゃ」
「そうなんですか」
「うむ」と、増加博士。「それに、わしはビールが大好きじゃ。ウオッカでも、スコッチでもアルコールが入っている物なら何でもいい。ただし、女子供が飲むような甘ったるい名前のカクテルだけは、ごめんこうむる」
「すみません。ここにはお酒はないんです」
真梨央が言うと、増加博士ははっきりがっかりした顔をした。
「酒がないとな。おお、アテネのアルコンよ! じゃが、仕方がないな。ならば、さっさと事件を片づけて、家へ帰るだけさ。そんな惚けた顔をしていないで、早く話をしたらどうなんじゃ」
「え、あの、何の話をですか」
「決まっておるじゃないか、《奇跡島》で、数々の殺人を犯し、死体に不気味な装飾をして、皆を怖がらせた悪魔めの話じゃよ。お主らは、殺人犯の名前を聞きたくはないのか!」
私は唾を飲み込んでから、一歩前へ出た。
「失礼ですが、増加博士。あの事件でしたら、すでに片づいています。あの犯罪を犯したのは、この僕ですから。犯人は僕です」
すると、増加博士は不満気に下唇を突き出し、私の方に太い指を突きつけた。
「馬鹿を言っちゃいかん。この本は推理小説じゃぞ。それも、《新本格》を名乗る作者が書いた本じゃ。そんなありきたりの結末があるわけがない。大丈夫じゃ、わしがちゃんと、お主たちや読者の腰を抜かさせるような犯人の名前を突きつけてやる」
「解りません。いったいどういうことなんですか。僕の他にも、犯人がいると言うのですか」
「違う!」増加博士は大声を上げ、またステッキを上下に振った。「お主は間違っている。お主は犯人などではない。もちろん、そっちのリボンだらけのお嬢ちゃんも犯人ではない。真犯人は別にいるのじゃ。それも、たった一人の恐るべき真犯人じゃ!」
「え、じゃあ、僕は犯人ではなかったんですか!」
私は訳が解らなくなり、意識が朦朧とした。
増加博士は、体全体を揺すって笑った。
「その通りじゃ。だから、わしが今ここで、この《奇跡島の不思議》事件のすべての謎を解こうと言うのじゃよ!」
3
私たちの目は、この驚異的な話し方をする老人の大きな顔に釘付けになった。初めは、誰もが彼を怖がったが、それでもだんだんと、私たちにもこの老人の性格が解ってきた。一見、怪物のような話し方をするが、実は非常に優しい心根を持った人のようだ。
真梨央が代表して尋ねた。
「確か、ルミコや加々美以外に、実は本当の殺人者がいたというお話でしたね。孤島の殺人鬼は、まったく別の人間だったとおっしゃるのですか」
榊原と日野原が、私の方を疑わしげな目でチラリと見た。友美は、留美子の顔を横目で見ている。
「そのとおりだ」増加博士はそう言い、私と留美子の顔をステッキで順に指し示した。「あの人物に比べたら、この二人などは借りてきた猫のようなものだ。可愛いものじゃよ。だいたい、この細っこくて、神経も細いお嬢さんが、夜中に死人の首をノコギリでギコギコと切断したりできるものなのかな。わしには、ディキンズの『デイヴィッド・コパフィールド』に出てくるドーラという娘っ子ほどに、弱々しく思えるがのう」
「いやん!」
と、留美子は頬を赤らめた。
私は尋ねた。
「それでは、私とルミコは、実際には犯人ではなかったというのですか」
「あたし、自分が友美ちゃんを殴り殺したって、知っているんですけど……」
留美子も上目遣いで、おずおずと尋ねる。
「そうじゃ。お主たちは犯人ではない。作者から、都合の良い記憶を植え付けられているだけのことじゃよ」
真梨央は熱心に尋ねた。
「じゃあ、真犯人は誰なのですか。それは、男なのですか、女なのですか。このメンバーの中に、当然いるんですよね」
私たちは疑いを持って、互いに互いの顔を見た。
増加博士はニヤリと笑うと、
「まあ、待て。それも順序立てて話そう。ただし、これだけは明言しよう。真犯人はただ一人じゃ。全部の殺人を、この人物が単独で行なったのじゃよ」
「はい」
「いったい何故、このわしが、この若者とお嬢さんの他に、真の犯人がこの小説の中に隠れていると考えたか、その理由から話そう。わしが、その重要な秘密に気づいたのは、あまりに当然しごくな問題からじゃった。何かというと、殺人の動機じゃよ。作中で、この二人が殺人を犯した理由を、作者はあれこれ書いている。やれ愛憎がどうのとか、芸術創造の殺人的展開がどうのとか、形而上的で回りくどいことをじゃ。しかし、それがちっとも説得力を持っておらんのじゃ。嘘臭いとさえ言えよう」
「はあ。そう言ってしまうと、身も蓋もありませんが……」
「麻生君と言ったな、お主はどうじゃったかな。風来坊という名探偵氏の話を聞いて、あんな推理で、完全に納得できたのかな」
「え、ええ。それは、まあ……」真梨央は困った顔をして、曖昧に答えた。「その時には一応……」
「だとしても、それは雰囲気によるところが大きい。一時的なものにすぎない。こうして落ち着いて考えてみると、まったく曖昧な話じゃ。
いいかね。よく《本格推理》は殺人の動機をないがしろにしているなどという馬鹿げた批評をする奴がおるが、それこそまったく愚かな言動じゃ。何故なら、推理小説の骨格には《犯人捜し》という趣向がある。犯人をうまく物語中に隠すためには、犯人の犯罪動機をうまく隠し、しかも、その手がかりも文中に埋めておく必要がある。そして最後には、読者にとびっきりの犯人を提供して、納得がいく動機の説明までせねばならない。したがっておよそ《ミステリー》と呼ばれるものの中でも、動機の扱いに最も手を焼いているのが推理小説なのじゃよ!」
私は熱弁を奮う増加博士の意見を聞きながら、ちょっと反対意見があった。というのは、この本の作者の著書を読むと、犯人は、『殺したいから殺した』みたいないい加減な動機が多いからだ。つまり、推理小説作家の中には、動機に腐心する者とそうでない者など、いろいろいるのではないだろうか。
増加博士はぜいぜいと息を整え、私の方を見た。私は何か注意でもされるのかどどぎまぎした。
「加々美君。わしは今、何の話をしておったかな?」
「え、あ、あのう。ミステリーにおける動機の話です」
私は焦って答えた。
「ああ、そうじゃった。わしは物覚えが悪い。どうしても秘書が必要じゃ。たった一分前のことも思い出せない」
「……はい」
増加博士は、大きな体をもぞもぞと小さな椅子の上で動かすと、
「とにかく、殺人の動機というのは、一本筋が通っていて、明確でなければならん。それでないと、良い推理小説の解決とは言えんのだ。そして、ダルマ君だか風来坊君だかが言ったとおり、事件の動機を考える時には、誰が一番その犯罪によって利益を得るかを探ることが重要になる。そうすれば、大半の事件は光明が見えるものじゃ。そこでわしは、この《奇跡島》事件において、一連の殺人が犯されたお陰で、誰が最も利益に預かったかを考察した」
「でも、それは俺たちもやりましたけど」
「いやいや、お主たちはやり方を間違えている。それに着眼点がずれておる」
「と、言いますと?」
「たとえばだな。見立ての件がある。孤島という閉ざされた場所で殺人を犯すということは、かなりリスクのある行為だ。その上、見立て殺人となれば、これはもう殺人を周囲に宣伝して回っているようなものじゃ。そのような危険を犯しつつ、しかも、それによって利益を得られる人物など、普通はいない。となると逆に、これはもう特定の者が犯人として絞られるのは必然と言えよう」
「なるほど」
「わしは今、この人物を犯人として告発できる条件を並べてみる。そこから論理的に犯人を炙り出すのじゃ。ええと、こうなるぞ――」
1、殺人の舞台に、《奇跡島》という孤島を選ぶことで、地理的、空間的に利益があるもの。
2、日野原剛を含み、五人の人間を殺害して、一番利益を得られるもの。
3、見立て殺人をこれ見よがしに行なうことで、一番利益を得られるもの。
4、殺人を一番良い機会に実行できるよう、皆の行動を把握しているもの。
「――どうじゃな。これが犯人の条件じゃよ。これから考えれば、もう犯人の正体など一目瞭然じゃないか」
「解りません」
と、真梨央が情けなさそうな顔をして答えた。
榊原が、またあの陰険な細い目で、私たちの方を探っている。しかし、私や留美子が犯人ではない以上、怪しいのは彼の方だ。真犯人はいったい誰なのだろう。麻生真梨央、榊原忠久、日野原剛、木田純也、武田紫苑、加嶋友美……それとも、ここにはいないが、権堂謙作、竹山収蔵、竹山民江……もしかして、風来坊が犯人、つまり、名探偵が犯人だったというとびっきり意外な結末なのだろうか。
解らない!
いったい、誰が真犯人なんだ!?
私たちは全員が一心に、増加博士の次の発言に注目した。
「お願いします!」と、紫苑が大きな声で頼んだ。「早く、教えてください!」
増加博士は深く頷くと、私たちの顔を順繰りに見回して、そして、ようやく答えを出した。
「この《奇跡島》事件で連続殺人事件を起こし、一番利益を得る者。それはたった一人しかいない。そうたった一人じゃ。それはだな、誰かと言えば、この小説の作者の《二階堂黎人》という男じゃよ!」
4
「作者が犯人だったと言うのですか!」
私は大声で訊き返した。世界が一瞬にして破滅した以上の驚きを感じた。
増加博士はおかしそうに、大きな体を笑いで揺すった。
「どうだね、解ったかね。真犯人は二階堂黎人じゃったのだよ。何しろ彼は、この小説を書くことで印税という報酬を得られる。読者が喜んで買ってくれれば、懐が膨らむというわけじゃ。金銭的な欲望という一番はっきりした動機を、彼は持っておるじゃないか。
推理小説の歴史を見ても、作者が犯人だったというのは、今までにもあまり記憶がないな。それほど特別に意外な犯人を狙ったものなのじゃよ。あまりに当たり前すぎて、お主たちは誰も気がつかなかったようじゃがな」
「では、この長ったらしい推理小説は、作者がたったそれだけの趣向をやりたいがために、存在しているのですか」
「おお、わしの帽子よ! そうじゃよ。お主の言うとおりじゃ。馬鹿馬鹿しいようだが、それが現実というものじゃ!」
私は頭がクラクラした。そして、喉の奥から不満が噴き出てきた。
「……それは確かに、今まで書かれた推理小説の中には、《記述者即犯人》とか、《探偵即犯人》とか、《被害者即犯人》とか、《容疑者全員犯人》とか、《動物犯人とか》とか、様々に意外な犯人を狙ったものがありましたよ。しかし、《作者即犯人》なんて、そんなの、当たり前である以前に違反ですよ。そんなことを言ったら、小説が成り立たない。作者と読者という次元で考えても、小説中の人間を犯人とするのが、最低限の推理小説的なお約束事じゃないですか。そんな卑怯な手段がまかり通ったら、読者は推理の矛先をどこへ向けて良いかまったく解らなくなりますよ」
「だからこそ、作者の二階堂黎人は、あえて書いたんじゃないのかな。常識をくつがえすことこそが、現代ミステリーの最も追求しておるところじゃろうが」
「そんな!」と、紫苑。
「嘘だわん!」と、留美子。
「ひでえなあ」と、榊原。
「驚いたです」と、木田。
「何と言っていいか……」と、日野原。
「信じられません」と、友美。
「まさかと思っていましたが」と、真梨央。
とにかく、非難囂々である。
「あっはっはっ。驚いたかね」
と、増加博士は愉快そうな顔をして、喉の肉を震わせた。
「当然ですよ!」私は強く文句を付けた。「驚いたというより、噴飯ものです。誰だって怒りますよ」
「しかし、作者は別にアンフェアではないぞ。手がかりはしっかり提示してある。作者自身が犯人ではないとしたら、何で、ちゃんとした長い物語の前後に、こんなふざけたような楽屋落ちの章が二つもくっついておるんじゃね。わしら、小説中の人間が、現実界の人間を名乗って、作者や読者と対等の立場まで歩み寄っているのも、《作者即犯人》という突拍子もない趣向を作者が成立させたいが故の技法じゃ。それを受け入れてやらなくては、わしらがこう厚かましく出てきている価値がない。
君らが、実物大の存在として登場した章が本の冒頭に置かれた時点で、すでに小説という虚構と、読者が身を置いている現実世界の境界は取り払われたのじゃ。ということは、君ら登場人物も、読者も、そして作者さえも、等価値でこの世界に位置していることになる。となれば、物語そのものは、我々全員を繋ぐ媒体にすぎない。その内の誰が犯人であってもまったくおかしくはないのじゃよ」
「……それにしたって」
と、私が言うと、紫苑も口を尖らせ、
「そうだよ。増加博士。ボクは信じませんからね。これだったら、ルミちゃんや加々美さんが犯人だった方が、よっぽどいいよ!」
「だったら、最初の第〇章と、この最後の第十八章は読まなければいいじゃないか。そうすれば、お主が望んでいるような秩序だった世界のまっとうな推理小説が読めるぞ」
「もう遅いよ。だって、読んじゃったもん。それならそれで、最初に言ってほしいなあ」
「それもそうじゃな。今さら、忘れるわけにはいかんか」
「でも」と、友美が心配そうな顔をし、真梨央の腕にすがりながら言った。「増加博士。本当に、本当に、この本の作者の二階堂黎人さんが真犯人なのですか。あまりにいろいろな解決が出てきたので、私、もうぜんぜん何を信じていいのか解らなくなりました」
「ほほう。それももっともな意見じゃな。よろしい。それならば、お主たちや読者へ、決定的な証拠を見せよう」
増加博士は二本のステッキに頼りながら、苦労して椅子から立ち上がった。そして、
「お主たち。もしも犯人である二階堂黎人が、自分で自分が犯人であることを自供していたら、どうするかね。そうしたら、わしの言葉を信じることができるかね」
私は率先して頷いた。
「ええ。それなら、納得します」
「でも、どこで自供しているというのですか」
と、真梨央が尋ねた。
増加博士は、またあの悪戯っぽい光を瞳に浮かべると、
「それは、最初からお主たちの目の前にあった。お主たちは、二階堂黎人の自供をあからさまに目にしていたはずだ」
「そうなんですか」
驚いて、友美が訊き返した。
「そうさ。まだ、解らんのかね。血の巡りの悪い娘っ子じゃな」
すると、木田がワナワナと震えながら、
「じゃあ、あの、まさか――」
増加博士は全身で笑った。
「うわはははは。そのとおりじゃよ。目次を見てごらん。目次の小見出しを並べてみるのじゃ。《読者への挑戦》を抜かしてだ。そうすると、こうなるな――」
第0章 人間たちを紹介する
第1章 海岸から孤島へ出発する
第2章 意外な人物が登場する
第3章 ドアを開いて……
第4章 失われた過去と生命
第5章 煉獄と地獄の狭間で
第6章 異常なる芸術作品
第7章 投影された殺人の悲劇
第8章 愕然とした人々の顔
第9章 被害者第二号は?
第10章 特異な飾り物の謎
第11章 極彩色の殺人
第12章 ロートレックのある部屋
第13章 証拠の検討を始める
第14章 難解な芸術論の末に
第15章 逃れられぬ運命
第16章 誰が孤島の殺人鬼なのか
第17章 宵闇が訪れて……
第18章 仲間たちの饗宴
「――こうやって小見出しを並べてみれば、秘密でも何でもない。こんなのは、推理小説においては頻繁に出てくるお遊びじゃ。気づかない方が悪い。目次を見て、怪しげな文章や、内容にそぐわない小見出しが並んでいたら、一度は確認してみることじゃ。
いいかね。それぞれの小見出しの頭の一文字を取り、それを繋げてみるのじゃよ。そうすると、こういう文章になる。『に・か・い・ど・うれ・い・と・が・ひ・と・ご・ろ・し・な・の・だ・よ・な』とな。つまり、『二階堂黎人が人殺しなのだよな』となる。これこそ、犯人の明白な自供以外の何ものでもないじゃないか!」
私たちは唖然として、もう何も言葉が出てこなかった。こんな単純で、あからさまで、人を喰ったような証拠が、当初から突きつけられていたなんて。
しかし、私は義務感のようなものを感じて尋ねた。
「だけど、どうしてそこまでして、二階堂黎人は、自分がこの物語の唯一の犯人にならなくてはならないのですか」
「それはだな、非常に単純な理由なのじゃよ。ようするに、事件の犯人が二人も――つまり、お前さんと、そちらの少女趣味なお嬢ちゃんだが――存在していることに我慢ができなかったからだよ。すなわら作者は、普段、推理小説におけるそのような犯人設定をあまり好ましく思っておらんのだ。
事件は計画的であること。用意周到であり、偶然に頼らぬこと。犯人は単独犯であること。そういった読者の主張があるのを、時々聞かないかね。きっと作者も、本当はそれに賛成なのさ。ところが、今回の物語のプロットを立てたところ、どうしても犯人の正体を隠すために、お前さんたち二人に悪役になってもらわねばならなかった。
しかし、作者はそれが気に入らなかった。無論、リレー型の犯人というプロットを最初に推理小説に持ち込んだ作家は偉大じゃった。天才的な閃きだった。だが、それが二度、三度と反復されるとなると、その類い希な思いつきも腐って地に墜ちるリンゴに思えてしまう。だからこそ、物語の最初と最後に、お主たちやわしが特別出演する章を立てて、自ら単独の犯人となり、純粋無垢なプロットを貫き遠そうとしたわけじゃ。おお、バッカスよ! 何と高潔な推理小説作家魂じゃろう!」
増加博士はニコニコして、私たちの顔を見回した。
「ええ。たいしたものですね」
私は本心はともかく、いやがおうにも賛辞を述べなくてはならなかった。
増加博士は居住まいを正すと、最後にクスリと小さく笑った。
「さて、どうやら、わしの仕事は終わったようじゃな。もうこれ以上、ここにいても、文章の無駄遣いになるばかりじゃ。去ることにするよ。お主たちも元気でな――」
そして増加博士は、来た時と同様、工事現場のような地響きと共に舞台を退場していった。
その後、私たちは虚脱感に襲われてしまい、長い間黙っていた。私はもう、何も感じられなかった。
しばらくして、この会場の正面が少しずつ消され始めた。最初は観客席だった。それが全部消えると、今度はこの舞台の上となる。そして、本当のカーテン・コールとなるのだ。
「――ねえ」
と、紫苑が誰ともなく尋ねた。
私は帰り支度を始め――と言っても、何も持つ物などなかったが、
「何だい?」
「あのね、《増加博士》って、どういう名前なの。とってつけたような変な名前だけど、何か意味があるわけ」
「ああ」と、私は投げやりに答えた。「たぶんそれは、こういうことだよ。《増加》ってことは《ふえる》ってことだろう。だから、《ふえる博士》さ。《フェル博士》だよ」
紫苑は言葉を失った後、私の顔を穴のあくほど見つめ、
「それってさ、ジョン・ディクスン・カーのギデオン・フェル博士のこと?」
「そうさ。だって、風貌がそのままだったじゃないか」
「つまり、また作者の病気が出たってことだね!」
紫苑の言葉を残し、私たちミューズのメンバーは、この小説の舞台を去ることにする。私たちは舞台の袖に向かって歩きだした。友美が、真梨央に尋ねている。
「真梨央さん。増加博士は作者が犯人だと言いましたけれど、本当でしょうか。だって、増加博士は作者が一番利益を得るから犯人だと指摘されましたけど、そう考えれば、その本を買って読み、何時間か楽しんだ読者だって最大の利益受理者ですわ。私、思うんですけれど、私たち登場人物が、殺人鬼によって殺されるのを一番望んでいた人って、やっぱり読者なのではないでしょうか――」
しかし、それももうどうでもいいことだ。しょせん、話はここで終わる。私はもう何も考えたくない。他の小説の主人公たちが、これからは頭を悩ませればいいことだ。
私は、ただ最後に、読者の皆さんには、ここまでお付き合いしてくれたことに、作者に成り代わって最大の感謝を捧げておこう。そしてもう一つだけ、この長い物語から見出される教訓めいたものについて述べておこう。
小説家は、自分の小説を書いている時こそ、あらゆる世界の《神》になれる――ということだ。
《了》
