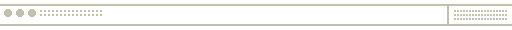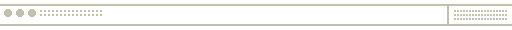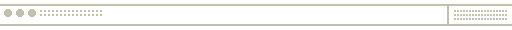
エッセイ
以下の作品は、個人で楽しむ他は、禁複製です。
エッセイ
【近況】
近況と言っては何だが、ここ三、四年ずっと捜しているものがある。一つは、紀田順一郎先生のある本の中で紹介されていた三笠書房刊行の『永遠のアンバー』という小説。ミッチェルの『風と共に去りぬ』に対抗して書かれた物語だという。偶然、テレビでこれを映画化したものは見たのだが、それがまた妙な所で尻切れトンボに終わっていたので、本当にあれが結末だったのか知りたくなり、ますます小説が読みたくなった。馴染みの古書店にも頼んであるのだが、なかなか見つからない。
もう一つの捜し物は、ニッキである。と言っても飴玉などではなく、子供の頃に駄菓子屋で売っていたニッキの小枝だ(根っこ?)。二、三センチの長さに無造作に切られたニッキの小枝が、小さな紙袋に数本入っていた。それを口の中に入れてかじると、ニッキ独特の辛みと清涼感の入り交じった味が少しずつ滲み出てきた。だんだんはがれてくる小枝の表皮を吐き出しながら、味がしなくなるまでかみ続けたものだ。あのちょっと刺激的で、清々しい味が忘れらず、もう一度でいいから食してみたいと願っている。
だが、世間の変わり様からすれば、こちらの方は一冊の古本以上に見つけにくそうである。だとすると、永遠に記憶の中の美化された味でしかない。
【尋ね物?】
前回、私は『風と共に去りぬ』に対抗した『永遠のアンバー』という本を捜していると書いた(まだ見つかっていない)。実は、「『風と共に去りぬ』をしのぐ」とか、「どこそこの『風と共に去りぬ』」という惹句(ちなみに「惹句」って広辞苑に出ていないので、誰かの造語かと思いました)に弱いのである。帯にそう書いてあると、必ず読んでしまう。もちろんそれは、『風と共に去りぬ』こそが人類史上最高の小説だと思っているからである。で、最近古本屋で発見したのが、ジャンヌ・モンテュペ著『紅い泉のほとり』三笠書房刊。惹句は「フランスの『風~』」。そう言えば、三笠書房は『人形の谷間』という「『風~』をしのぐ」作品も出していた(実体はまったくしのがない)ので、三笠書房はそういう広告がお得意のようだ。という訳で、今私が一番気になっている本は、最近集英社が刊行した『青い自転車』シリーズという奴。これも、帯には「フランスの『風~』」とある。はたして、面白いのか?
追記。この文章を書いて協会に送った二日後、久しく行っていなかった古本屋を覗いたら、『永遠のアンバー』三巻がセットで並んでいた。同時に、もう一冊、やはり捜していた『古代のアラン』もあるではないか。大ビンゴ!。で、手に入れてしまったからには、『永遠のアンバー』は書棚へ直行。もうたぶん読まないだろう。それが古書集めというものである。
【手塚治虫ファンクラブの頃】
一ヶ月ほど前に引っ越しをした。引っ越しをすると、普段はしないような整理整頓を行なうので、しばらく忘れていたような物をタンスや押入の奥から見つけ出すことが多い――というのは、以前の引っ越しの経験からしても解っていた。引っ越しの準備をしながら、埃を被った本やアルバムをつい開いてしまい、仕事もそっちのけで読みふけってしまうなどということもある。
今回、久しぶりに見つけて感動したのは、手塚治虫先生から頂いた何枚かのハガキであった。それが、子供の頃のがらくたを集めておいた段ボール箱の一番下から出てきたのである。実はそのハガキは、私が手塚先生へ出したファンレターへの返事だった。小学校五年生の時に手塚先生の本を集めようと思い立ち、収集を始めて、中学の終わりに至るまで、私は頻繁に手塚先生へファンレターを書いた。内容は、手に入れた単行本や、その時雑誌に連載されている作品を見た感想文である。それを便箋五枚くらいにびっしりと書き、各頁の左隅に、先生の絵を模写したキャラクター(アトムやレオ、ヒゲオヤジ、ヒョウタンツギ、火の鳥など)を描き加えるわけである。
私のファンレターに対して、嬉しいことに、何通かに一通、手塚先生からハガキや年賀状を頂戴した。「ボクのマンガに関する感想をどうもありがとう」といったお言葉から始まり、近々描かれるつもりの作品や、単行本の出版予定が記されていた。先生からのハガキが来る度に、私は大いに感激し、また新しい作品を読んで、せっせと感想文を送り続けた。
そうしたある日――確か中学二年の時だったが――手塚先生からのハガキに、「ボクのファンクラブがあります。森晴路という人がやっています。良かったら、連絡を取ってごらんなさい」とあり、横に住所も書かれていた。私はそんな素敵なものがあったのか!とびっくりするやら喜ぶやら、さっそく入会希望の手紙を、その森晴路という人に送った(ちなみに、森氏は現在手塚プロの資料室長である)。
それが、私が《手塚治虫ファンクラブ》に入ったきっかけだった。当時のファンクラブは、まだ市井の好事家の集まりに過ぎず、活動と言えば、月一回の会誌の発行(ただし、遅れ気味であった)と、月一回の集会――といっても、喫茶店で好きなマンガに関して延々と論じる(ダベる)だけ――であった。東京には森氏を中心とした《メトロポリス》という仲間がいて、いつも新宿で顔を合わせた。時折、そのメンバーは森氏の自宅に招かれ、珍しい本や高価な古本を見せてもらい、手塚先生に関する貴重な話を聞かせてもらった。また、皆で手塚プロへ遊びに行ったりもした。
そうして、私が大学へ入学した年、森氏が手塚プロへ入社して多忙になり、会誌を作ることが物理的にできなくなった。それで、白羽の矢が立ったのが私だった。大学生でしかも一年生、一番時間が自由になるだろうというのが、周囲の一致した意見だった。もちろん、私は承諾した。そして、森氏に原稿の書き方や写植の発注の仕方を教わりながら、慣れない手つきで、オフセット印刷の会誌を二冊作った。
最初の一冊は、私が日本テレビの《24時間テレビ》の制作アルバイトをしてまで関わった、手塚先生久々のアニメ『バンダーブック』の特集である。通常手に入らない手塚先生直筆の絵コンテを掲載するなど、見栄えはともかく、意欲的な内容だったと自負している。
そのすぐ後で、手塚プロが『火の鳥2772』という劇場用アニメを作り、これに合わせて正式に《手塚治虫ファンクラブ》を発足させる。それまでの会員は自動的にこの会に吸収され、私は名目的ではあるが、会長の役を務めることになったのだった――。
引っ越しで見つけた昔の手塚先生のハガキが、私の青春時代とも言えるそんな懐かしい頃のことを思い出させてくれた。
【犬好きのこと】
六年ほど前にパソコン通信を始めた頃から、《黒猫館主人》雅号をハンドル名に付加している。というのは、文字通り当時から黒猫を飼っているからで、綾辻行人氏が『黒猫館の殺人』を上梓した時には、わがことのような気がして、勝手に嬉しがっていた。しかし、実を言えば、私は大の犬好きである。猫は好きではないというより嫌いで、外を歩いていてドラ猫に遭遇したり、あるいは、自分の家の敷地によその猫が入ってくると、思わず石をぶつけたり、水をぶっかけたくなる。いや、時々その衝動を抑えきれず、実行に移してしまうこともしばしばなのだ。
では、何故、黒猫を飼いだしたかと言えば、その頃はマンション住まいであったため、犬を飼うのが物理的に無理だったという単純な理由。そして、黒猫を飼ってみて解ったのは、猫は猫なりに可愛いし、食べ物もトイレも手間はあまりかからないが、犬のように車に乗せて遊びに行くことはできないということである。現在は一戸建ての家に住むようになったので、いつか犬を飼おうと――犬嫌いの黒猫様には内緒で――家人と相談を始めている。
私の犬好きは、動物好きの両親がいつも犬を飼っていて身近にいたからであろう(他にもハトやカメや鯉も飼っていた)。最初はスピッツ、次ぎにコリーを二代、コッカスパニエル、マルチーズといった具合である。さらに、子供の頃にテレビで見た『名犬ラッシー』や『名犬ロンドン』、『名犬リン・チン・チン』等の影響も大きいと思う。テレビのみならず、名犬ものというジャンルが小説や映画にもあるが、名猫ものというのはついぞ聞いたことがない。その意味でも、やはり猫というのは、飼い主の個人的な精神的充足感以外には、一般的に役に立たない動物である。
ところで、先日、親しい作家・漫画家仲間で、飼い犬を持ち合い、どの犬が一番素敵か品評会を開こうということになった。もちろん、お犬様に名を借りたちょっとしたピクニックというのが実体だが、、こんな面白い企画には出席しない手はない。現在、飼い犬を持たない私は、品評会の審査員という特別な肩書きを頂戴して参加した。
開催場所は、東京都立川市にある昭和記念公園。ここは敷地が非常に広く、犬の散歩が許されているので、この手の話には絶好である。出席者は、小説家の桐野夏生さんと愛犬のカヌ嬢。漫画家の喜国雅彦夫妻と愛犬コタロウ君。小説家の津原泰水さん夫婦と愛犬ラジオ君である。
ウェルシュ・コーギーのカヌー嬢はまだ六ヶ月。シェルティに似たすっきりした顔立ち。やや胴長で、チョコチョコ動かす短い脚が愉快である。コタロウ君は雑種で、つぶらな瞳がチャームボイント。人間には純情だが、他の犬が嫌いという一匹狼的性格。ラジオ君は、黒みががった毛がふさふさと長いチベタンテリア。その姿は歩くモップといった感じ。賢く、飼い主の命令には実に従順である。
芝生の上にビニール・シートや弁当を広げ、全員でじゃれ合っていると、犬の個性も三者三様であることがよく解る。それが犬種によるものか、個犬的な資質であるのかまでは判断がつかなかったが、やはり犬は人間の最良の友だなあどと、私は一人で納得したりしている。
で、品評会の結果だが、これは以外な結末を迎えた。当日は休日のため、犬を連れて散歩に来ている人が多く、犬同士、犬の飼い主同士すぐに仲良くなってしまう。私たちの誰かが、近寄ってきた一匹の雑種を見て、『あの犬の名前は何だと思う?』と尋ねる。すさかず、誰かが、『雑種はシロとかポチに決まっているさ』と答えた。『すみません、その犬の名前は何ですか』と、飼い主の方に尋ねると、その人は満面の笑みを浮かべ、『コロです』と明瞭な返答。その平々凡々とした名前を聞いた途端、本日の品評会の第一位は、横から飛び入り参加したこのコロ君のものと決定したのである。
【イチゴ飴の紐は未来のどこに繋がっているか】
子供の頃、駄菓子屋は、必ず路地裏か町外れにあった。そこは子供たちの社交場であって、ハッカやふ菓子やカルメラやあんず飴やFXガムやスモモやラムネやバナナ菓子やイカの足やくだもの水なんて駄菓子の他にも、ロー石やようかい煙や紙ふうせんやメンコやビー玉やコマや凧やプラモデルなど、チープなオモチャが必ず置いてあった。狭い店内に入れば、乱雑にデコレーションされた物を何も見落とすまいと、みなが血眼になった。
最近は、駄菓子がけっこう市民権を得て、デパートなどに小さくこぎれいなテナントを見かける。時折、憧憬に誘われて覗いてみたりするが、記憶の中の駄菓子屋とはどこか違うような気がする。昔は、店構えも品物も、もっと怪しく、汚く、不潔だったし、お金を払う時など、必ず妙な後ろめたさを感じた。なにより、魔女のような雰囲気のおばちゃんがいなくなったのが一番異なる。
幼稚園の頃、駄菓子屋で一番気に入っていたのはイチゴ飴だった。というより、自分の小遣いではそれしか買えなかった。確か一個5円だった。小粒のイチゴと同じくらいの大きさで、表面に粗目の砂糖がまぶしてある。広口のガラス壜の中に、毒々しい多数の赤色の飴と小数の黄色い飴が入っている。それ自体くじなのだ。一個一個の飴に綿の細い紐が付いており、途中は紙帯で束ねられ、端は壜の外に垂れていた。お金を払い、紐の一本をゆっくりと引く。黄色の飴が取れると当たりで、何と気前がいいことか(とその頃は思った)、もう一回紐を引くことができた。興奮と期待に震えながら、推理力と超能力を駆使して、私は慎重に紐を選ぶ。無論、なかなか当たりは出なかった。
けれども、立て続けに六個の当たりを引いたことが一度だけある。夏休みに長野県松本市にある母の実家に遊びに行き、東京に帰るという時、私は近くの駄菓子屋へ急ぎ飛びこんだ。そして、イチゴ飴の紐を引いたら、驚天動地、次から次へと当たりが出たのだ!
店の外では、バス停にいる母が「バスが来たから、急いで!」と私を叫んでいる。だが、頭に血が昇った私はそれどころではなかった。東京へ帰れなくたって何だ! イチゴ飴の当たりの方がもっと大事じゃないか!
いくら何でも、もう外れるだろうと毎回自虐的に覚悟する。なのに、またもや当たり!というスリルとサスペンス。私の手は震え、喉は乾き、心臓は破裂しそうになった。最終的に掌の上にのった六つのイチゴ飴。あれほどの至福は、後にも先にも記憶がない。
もちろん、バスには乗り遅れた。
【コントラクト・ブリッジ初心者宣言】
トランプ(カード)・ゲームというと、日本では、一般的に子供のお遊びのように思われがちだが、西部劇に頻出するポーカーに代表されるように、欧米では、大人の社交遊戯として認知されている。数々あるカード・ゲームの中でも、常に私の感心を惹いていたのが、コントラクト・ブリッジだった。
映画『大脱走』の中で、捕虜収容所にいる兵隊たちが、二段ベッドの上下に寝そべり、ブリッジをやっていた。「ハートの2」「クラブの3」などと、カードを手にして、競りの宣言をしている。TVドラマの『奥様は魔女』でも、サマンサとダーリンが社長夫婦を
家に迎え、食後に、ブリッジをするためにテーブルを囲んでいた。
もちろん、アガサ・クリスティーなどの推理小説にも、ブリッジは何度となく重要な小道具として出演している。
子供の頃の僕にとって、コントラクト・ブリッジは、大人の匂いがする特別なゲームだった。日頃、自分が熱中している《ババ抜き》や《神経衰弱》等とは、格がまったく違うという印象があった。また、ルールがよく解らないということが、かえって、このゲームに対する憧れを肥大化させた要因だった。
いつかコントラクト・ブリッジをやってみたい。そして、自分の書く推理小説の中に、それを趣向として取り入れてみたい。そうずっと考えていた。だから、ブリッジの解説書を読んで、ルールだけは理解した。だが、このゲームは四人のメンバーを必要とする。周囲に同好の士がまったくいないという現実の元では、なかなかその願いはかなわなかった。
実際にコントラクト・ブリッジをすることができたのは、大学の最終学年の時だった。数学のゼミの教授がこのゲームのファンで、生徒にルールを教えてくれた。そして、何度か、課題授業の合間にブリッジをして遊ぶ時間を作ってくれたのである。
その当時、巷はカフェ・バー・ブームだった。六本木には、雨後の竹の子のごとく、その手の店が乱立した。その内の一軒がブリッジ用テーブルを設置してあると、私は若者向け情報誌で見て知った。ある夜、教授とゼミの仲間を誘い、カードを持って出かけてみた。
名前のよく解らない、赤や青や紫のカクテルを頼み、僕らは悠然とした態度でブリッジを始めた。周囲にいるたくさんの若い恋人たちが、こちらをチラチラ盗み見る。その羨ましそう視線が何とも言えない優越感を誘って、若い僕らの虚栄心を充分に満足させた。
けれども今になって考えてみれば、本当は、奇異な奴らと白い目で見られていたのかもしれない。
【華麗なる誘拐】
小説を読んでいて一番物語の中に引き込まれるのは、やはり何と言ってもヒロインの誘拐場面である。それもとびっきりの美女がいい。主人公の大切な恋人や妻が、悪者や怪人や怪物や宇宙人に誘拐され、それを主人公が救出しようと、必死になってどこまでも追いかける。はたして、愛する人を無事に救出できるのか――これほど興奮し、手に汗握り、感情移入のできる物語展開はない。と、実は今でもひそかにら思っている。
しかし、最近は、こういう事を正直に言えなくなった。下手をすると、当の女性たちから、セクハラだと訴えられるからだ。それに、現代の女性は非常に強くなった。おめおめと敵に捕まりはしないだろう。もしかすると、こちらが駆けつける前に、もう相手を木っ端微塵にノックアウトしているかもしれない。
でも男ってのは、いつも「君に何かあったら、僕の命にかけても助けに行くよ!」と、ターザンや『ダイ・ハード』の主人公ばりに格好つけたいものなんだよ。
【初めての品切れ】
今から二十年以上前のこと。小学校五年生の僕は、小学館の新書判『鉄腕アトム』全二十巻を毎月一冊ずつ買っていた。ところが、十五巻目が品切れで、どこの本屋でも手に入らない。その頃の僕には『品切れ』とか『絶版』の意味がよく解らず(それ以来、この二つの単語に悩まされ続けているわけでもあるが)、出版社まで直接行けば一冊くらいは残っているはずだと勝手に決めつけ、単身神保町まで乗り込んだ。本社の受付嬢は、
「ここには本は置いてありません。倉庫に行ってください」
倉庫に行くと、警備員が、
「ここでは本の販売はしていない」
と、つれない仕打ち。
絶望にうちひしがれて帰ろうとすると、その時、建物の中から眼鏡をかけた品の良いおじさんが出て来た。
「あ、課長」
と、警備員。
「どうしたんだね」
「カクカクシカジカ」
課長さんは僕の方を見て、
「ちょっと待っていたまえ」
と中へとって返し、しばらくすると、その本を持ってきてくれたのだ。感涙にむせぶ僕に、
「お金はけっこう。これからも、小学館の本をよろしくね」
あの時の紳士はきっと、小学館の社長さんになったことだろう。
【翻訳ミステリーと私】
以前、僕はあるマンガの解説で、自分が生まれて初めて読んだマンガを覚えていると書いた。それと同様に、最初に読んだ翻訳ミステリーが何であったかも覚えている。それはまた、最初に読んだ――国産、外国産を問わず――最初のミステリーということにもなる。
その本の名は、モーリス・ルブラン著『怪盗紳士ルパン』。発行元は偕成社。確か、少年少女名作何とかシリーズの一冊だった。読んだのは、小学校二年の時。風邪をひいて寝ていたところ、退屈だろうと、母方の祖母が近所の本屋で買ってきてくれたのだ。
実を言うと、彼女は私の祖父の後妻で、私とは血は繋がっていない。昔の農家の出なので、あまり読み書きができなかった。だから、今にして思うと、何故、彼女がこの本を選んできたのかが不思議である。彼女がルパンを知っていたとは思えないから、本屋の主人に、何か面白い本はないかと尋ねたのかもしれない。どちらにしても、僕はそのことを感謝している。あのような素晴らしい本に出会えたことが、今日、僕が推理小説作家になっている原因だからだ。
その『怪盗紳士ルパン』という本で、あまりに格好良い主人公に触れた僕は、病気が治ると、すぐに図書館へ飛んでいった。当時住んでいたのは、東京都の国立市。今は市立の立派な中央図書館があるが、三十年ほど前には駅前のロータリーの脇に、毎週土曜に開設される子供向けの簡易図書館しかなかった。そこに、南洋一郎訳のポプラ社版アルセール・ルパン・シリーズがずらりと並んでいたのだ。
並んでいたというのは、少し嘘がある。何故なら、ルパンは子供向けの本の中でも、江戸川乱歩の少年探偵団シリーズと共にすごい人気があったからだ。したがって、いつでもシリーズ中の一冊か二冊しか棚には残っていなかった。
もちろん、僕はそれを毎週わくわくしながら借り、むさぼるように読んだ。『奇巌城』『813の謎』『水晶の栓』『虎の牙』『三十棺桶島』などなど。たまに図書館に一冊もなかった時などは、泣きたいほどがっかりした。
アルセーヌ・ルパンは、小学校時代の僕の英雄だった。山中峰太郎訳のシャーロック・ホームズも読んだが、僕にとってホームズは、ルパンの恋人レイモンドを殺した悪人だったので、あまり好きになれなかった。世の中にはホームズ派、ルパン派というのがあり、僕は文句なくルパン派である。
その後、大人になるにしたがって、僕は日本文芸社の保篠龍緒訳ルパン全集や、創元推理文庫、新潮文庫、偕成社版全集などの完訳ルパンを繰り返し読んだ。しかし、南洋一郎訳を読んでいた時が、やはり一番胸が躍り、興奮した時期だった。
【芦辺拓なる偉大な作家といかにして遭遇したか】
一九九一年の秋だったかと思うが、第一回鮎川哲也賞に『吸血の家』という推理小説で応募した。翌年の春、東京創元社の戸川安宣編集長から電話をいただいた。『吸血の家』が最終候補作に残ったという知らせだった。正直に言うと、この時、私は受賞を確信した。私がこの作品の応募に関して心配していたことはただ一つ、応募規定枚数の上限を原稿が越えていたことだけだった。つまり、規定違反で失格になることを恐れたのであって、内容についてはかなり自信があった(しかし、後にそれは、恥を知らない非常な思い上がりであると思い知らされた。特に、まったく原稿の書き方がなっていなかった)。
その一ヵ月後、また戸川編集長から電話があり、『吸血の家』が佳作入選したことが告げられた。そして、当選作は、芦辺拓氏の『殺人喜劇の13人』であることも。
この時の奇妙な気持ちを、私は今でも明確に覚えている。自分の作品が入選しなくてがっかりしたということがまったく無かった。それよりも、『吸血の家』を越える作品が世の中にあったということで、一人の推理小説ファンとして、非常な喜びと興奮を覚えたものである。私は意気込んで、芦辺拓氏の作品の内容がどんなであるか戸川編集長に尋ねた。だが、戸川編集長は例の飄々とした感じで、「なかなか良い作品ですよ」というだけに笑って留めた。おかげで、秋の鮎川賞パーティーで『殺人喜劇の13人』の現物を手にするまで、私のこの作品に対する期待は否が応でも増すばかりであった。
そして、ついに手に入れたあのやや厚めのずしりと重い本。
私は一刻も早くその作品を読みたかった。したがって、帰りの電車の中でページを急ぎ読み始め、その夜の内に、すべてを読み終えた。
私の期待はまったく裏切られなかった。戯作的な独特の文体、完成された文章、惜しみなくちりばめられたトリック、緻密なプロット、何も取っても、そしてそれらが総合した上での豊饒な味わいに関しても、まさに傑作と呼んで相応しい作品だった。鮎川先生をはじめとする選考委員三人型の慧眼に、狂いはなかったのだ。鮎川賞と『殺人喜劇の13人』は、日本の推理小説史に輝かしい一頁を記したのである。
さて、話が前後したが、肝心の芦辺拓氏と最初に会ったのは、夏も真っ盛りの頃であった。芦辺氏が鎌倉の鮎川先生の所へ挨拶に行くので、あなたもどうかと、戸川編集長が誘ってくださったのである。
飯田橋の東京創元社ビルの一室で芦辺氏を紹介された途端、私は彼の存在の大きさに胸を撃たれた。何故なら、彼はもう文豪の顔をしていたからである。それと、会った途端に、彼が私と同じ人種であることも直感的に悟った。つまり、純粋推理小説愛好人種とでも呼ぶべきものであることを。その巨大な感動は、以前、書店で平積みにされていた綾辻行人氏の『十角館の殺人』を見た時と同じだった。
私と芦辺氏は、互いの一言目から、もう旧知の友人のように仲良くなれた。無論そのはずである。我々の魂の中には、センス・オブ・ミステリーとも言うべき、まったく同一の根元が存在したのだから。
以来私は、彼の作品が出てくるのを毎回非常に楽しみに待っている。だが、彼はなかなか意地悪な人間で、新作を矢継ぎ早に刊行するような真似はしてくれない。それだけがたいへん残念である。
ところで、『殺人喜劇の13人』の一番大きなトリックに、《陰獣トリック》が使われていることは容易に指摘できる。読者は(特に芦辺拓という人物を知っていればいるほど)、最初に出て十沼京一を芦辺拓というキャラクターとだぶらせてこの小説を読むことになる。したがって、作品紹介の際に、『のちに被害者の一人となった十沼京一の手記にもとづいた森江のものうい推理がたのしめる』などと言ってはいけないのである。
なお、最後に芦辺氏と私の推理小説作法上の合い言葉をここに紹介しよう。
『ロジックよりもトリックを!』
【どんな鍵だって……】
密室殺人が出てくる推理小説ばかり書いているものだから、鍵だとか錠前だとかに強い興味がある。古今東西の文献を漁ったり、古い錠前が飾ってある資料館へ足を運んだり、実際に自分でも幾つかの錠前を分解したり、組み立てたりもする。普通の家にあるようなイエール錠やシリンダー錠なら、針金などを使って簡単に開けられるようになった。これは私の特技であろう。
この前は、先輩作家の折原一さんに、元防犯課の警察官の講演会に連れて行ってもらっいた。空き巣犯の家宅侵入の手口だとか、防犯に錠前をどう役だ立てるかという話があった。現実の世界では、小説のような密室殺人はなく、合い鍵が用意されているそうな。
一昨日、ある地方都市へでかけた時のこと。堀の中を色様々な緋鯉が泳ぎ戯れている町である。そこに有名な美術館があり、絵画鑑賞を決め込んだ。二階に上がると、土蔵造りの窓に、飾り金具式のいかしたクレッセント錠が付いていた。この鍵をどうやったら外から開けたり、あるいは閉めたりできるだろうかと、私は夢中になった。窓枠の大きさを測ろうと思い、ふと脇を見ると、額縁のない五号の油絵が掛かっている。五号キャンバスは、長手の寸法が三四八ミリ。これを物差し代わりにあてがえばいい。
私はそれを壁から取りはずした。途端に、部屋中に非常ベルが鳴り響き、足音も高らかに走ってきた警備員が、私を羽交い締めにしたのだった。
私は弁明する機会も与えられず、事務室に連れ込まれ、そして……今、こうして最寄りの警察署の独房に押し込められた。
だが、取材の好きな私は、この絶好の機会を逃さない。独房の鉄棒には、普通なら見ることのできない魅力的な錠前が下りている。厳重な施錠と、警官たちによる警備とを破って、《不可能犯罪作家》と呼ばれる私の名前にかけても、見事に脱獄してみせよう。
【世界最高の推理小説】
《新本格推理》と呼ばれるミステリーが大人気である――と言ったら手前味噌すぎるとしても、けっこう人気はあるみたいだ。《新本格》ファンの中には、従来からのミステリー・マニアの他に、島田荘司氏の『占星術殺人事件』や綾辻行人氏の『館』シリーズを読み、初めてミステリーの洗礼を浴びたという人も多い。そんな新しいミステリー・ファンから、最近よく訊かれる質問がある。
「新本格の次に読んだらいい推理小説は何ですか」
この答えは簡単である。
「古典的な名作を読みなさい」
本格推理はその性質上、生まれながらにしてメタ・ミステリ(先例を乗り越えていく衝動と様式)の傾向が顕著である。故に、前例を踏まえてトリックやプロットを案出することが多々ある。つまり、古典的な名作を解読することは、《新本格推理》をいっそう深く理解することに役立つわけだ。
今回は、推理小説の数多い古典の中から、芸術品とも言える名作中の名作を紹介したい。
で、最初はヴァン・ダインの『僧正殺人事件(1929)』。これは彼のシリーズ第四作で、第三作の『グリーン家殺人事件』と並ぶ代表作。内容は人並み外れて博識、ディレッタントな探偵が、奇怪な童謡殺人事件を独自の美学や心理的推理法で解決するという究極の物語。何よりも、マザーグースに則った見立て殺人が、諧謔と残虐を対比させ、摩訶不思議な犯罪劇を演出する。しかも、犯人の超人思想に基づく犯行動機は、推理小説史上初めて完璧な観念論として提示される。その形而上学的な解決は、後世の推理作家に思想・宗教性の面で多大な影響を与えた。
次はエラリー・クイーンの『Xの悲劇(1932)』。こちらも『Yの悲劇』という次作と共に、恐ろしいほどの傑作である。満員電に乗る人物が、突如ニコチンを塗った刺だらけの球で毒殺されるという怪事件が起こる。謎の不可解性は強烈で、そこから導き出される真相と犯人の意外性も秀逸。探偵も魅力的、手掛かりの提示も巧妙、題名にかかわる《X》のダイイング・メッセージも見事である。解決に到る論理性は元よりクイーンの専売特許だから、数学の方程式の解法以上に整然として美しい。
最後がジョン・ディクスン・カーの『三つの棺(1935)』。カーは密室殺人を中心に不可能犯罪ものに熱意を注いだ作家である。
この作品は、死んだと思われた男が地獄から蘇ってきて、自分を陥れた男たちに復讐をするという怪奇譚である。一つ目の殺人では密室から犯人が消失し、二番目の殺人では雪の降った道路に足跡一つ残さず殺人を犯す。最後に明かされる犯人は他に類を見ないものだし、事件の真相は、読者のそれまでの認識を百八十度引っ繰り返すほど予想外だ。また、文中での《密室講義》という有名なトリックの分類が、江戸川乱歩ら多くのミステリー研究者を刺激した。
以上三作品。いずれも百五十年以上に及ぶ推理小説の歴史で、華麗なる頂点を究めた宝物である。
【私のケンカ歴/半生の争い】
私は今、某週刊誌とケンカをしている。ミステリーのベスト10選びのアンケート方法がでたらめ極まるので抗議したことから派生した問題だが、正義はこちらにあり、勝利は目に見えているから、今回はそれを書かない。
では、他にどんなケンカを体験してきたかと言えば、それは父親との骨肉の争いである。私が大学生の時に死んだ父親とは二十何年かのつき合いだったわけだけど、そのほとんどの時期をケンカしながら過ごしてきた。
父親とは、とにかく肌が合わなかった。気質、性質、信条、意見、進路、その他、ありとあらゆる点で妥協が見いだせなかった。私はこのように小説家になっているぐらいなので生来の文系人間なのだが、父親は高校野球の選手だったり応援団長をしていたから、根っからの体育会系人間だった。まさに、明治時代の権力志向の強い日本の父親といった感じの暴君である。彼は家にいると、箸一つ取るにも母親をこき使っていた。『巨人の星』に出てくる星一徹にそっくりで、気に入らないと激情に走り、ちゃぶ台を投げ出したりするようなことも平気でした。
子供の頃には、父親が頻繁に怒る原因がよく解らず、ただ漠然と、何かちゃんとした理由があるのだろうと恐れていた。が、高校生ぐらいになってこちらの理解力が出てくると、それは嘘だと見切った。ただ単に、その時々の自分の体調や気分で、彼は家族に当たり散らしていただけのことなのである。
私は子供の頃から運動が大嫌いだった。それなのに、野球やサッカー、マラソンなどを無理矢理やらされ、剣道を習わされたこともある。冬の雪が降った寒い朝に、心身の鍛練だとか言われて、一時間以上も剣道着姿で雪の上に裸足で立たされたりした。現在の私は、原因不明の体の故障を抱えているけれども、それは、子供の頃のこうした無理が祟ったせいだと考えている。
そんな彼の横暴の中でも、今でも思い出す度に頭にくる出来事がある。それは、小学校一年だか二年だかの時の運動会の日に、父がいきなり真っ白なタビを出して、それを履いていけと私に命令するのである(これなど、星飛雄馬にボロ・スパイクを履かせた星一徹を思い出させるエピソードではないか)。年輩の方には、タビを履いて運動をした記憶のある方もいるかもしれないが、昭和三十四年生まれの私たちの世代で、そんな経験をした子供は誰一人としていないはずだ。
いつも頭ごなしに命令を押しつけられていた私だったが、この時だけは全身全霊を使って泣き叫び、激しく抗議した。一時間以上も、畳の上を転がって反抗し続けた。結局は、普通の運動靴を履いて出かけることを許されたが、小学校時代に父親の無理強いに逆らい得たのは、とうとうその一回だけだった。
したがって、父親が急死した時、周囲の人々は気の毒がってくれたけれど、私は心中で、彼から自由になれたことを喜んでいた。
【ホタルの魔術】
夜、ホタルの光舞う姿を美しいと最初に意識したのはいつのことだったか。それは解らない。私は生まれた時から東京の住宅地に住んでおり、時代はいわゆる高度成長期のまっただ中だったから、東京でホタルを見たはずがない。では、どこで見たかと言うと、たぶん、長野県の松本市でであろう。
一つは、小学校の三年くらいの時の夏、長野県松本市の母の実家に遊びに行った時のこと。叔父二人が浅間温泉の近くにある小沼に連れていってくれたのだが、日が沈んだ途端、小沼と小沼を囲むススキの藪中にホタルが乱舞し始めた。付近に何の照明もない真っ黒な場所で、まるで夜空の星がいっせいに動き始めたかのような神秘的な光景であった。
私はずっと東京都の国立市に住んでいた。ここの南の端、多摩川沿いに、清華園という場所がある。ゴミ焼却場と市営プールが一緒になっていて、私は小学校中の夏休みになると、このプールにバスで泳ぎにいくのを常としていた。その清華園で、市がホタルの養殖をしたことがあると知ったのは、小学校の二年の時だった。三歳上の遊び仲間がいて、彼の家にあった古い学研の〈学習〉誌にそのことが載っていたのである。私はびっくりした。まさか、こんな身近な場所で、ホタルが見られるかもして、母にその記事が本当かどうか尋ねてみたが、残念ながら、市長が変わってこの計画は取りやめになっていることが解った。
二つ目は、小学校の五年だと思うが、国語ドリルの中に、谷崎潤一郎の『細雪』の一節が出てきた。田舎での蛍狩りの部分なのだが、その美しく精緻な筆致に触れ、私はすぐさま『細雪』自体を無性に読みなった。おかげで、『細雪』は私が日本の小説で一番好きな物語となったが、今度はホタルを見たくなった。
その機会はすぐに訪れた。その頃、金沢に父方の伯母がいて、母と二人で避暑に出かけた。義伯父は競馬の獣医で、蹄鉄打ちでもあった。家の前は一面田圃で、緑緑した稲穂が盛大で埋まっていた。その夜、私は伯母に呼ばれて外へ出た。そして、アッと驚いた。何と、田圃中にホタルが乱舞しているのである。数などとうてい数え切れない。雪が降るみたいに田圃中を覆っているのである。私は飽きることなく、その美しい光景に見入った。
翌朝、私は海へ行くことになっていたので早起きした。外へ出ると、田圃では農家の人が農薬を巻いていた。背中にタンクのような物を背負い、手に持った鉄パイプのようなもので、農薬を噴霧しているのである。
その夜も、私はホタルを見ようと楽しみにしていた。夕食をすませ、外へ息せき切って飛び出た。そして、昨日よりもさらに私は驚くことになる。何故なら、一匹のホタルも飛んでいなかったからだ。私は愕然とした。自分の見ているものが信じられなかった。私は田圃へ近づくと、目を凝らして稲の間を詳細に調べていった。しかし、やはりたった一つのホタルの光も見つからないのである。
そうなのだった。朝、田圃に巻かれた農薬のせいだったのだ。そのせいで、ホタルが死滅してしまったのである。そのことを悟った時の驚き。私はあの時の恐怖を今でも覚えている。悲しみと憤りが私の心を満たしたが、その気持ちをどこへぶつけて良いか解らなかった。
【ミステリーの謎が解ける時】
まだ作家になる前の一介のミステリー読者にすぎなかった頃、私にはよく解らないことがあった。それは、島田荘司先生が何故、あれほど熱心に新人を世に出すための推薦を行なっているのだろうかということだった。自己のミステリー論を開陳しつつ、綾辻行人氏をはじめ、歌野晶午氏、法月綸太郎氏、我孫子武丸氏、麻耶雄嵩氏らのデビュー作に熱いエールを送り続けたあの言動は、今も非常に興味深い問題として思い出される。無論、大乱歩の時代から、有名作家が、新人の本の推薦に名を貸すという行為はあった。しかし、それは所詮名を貸すだけであって、あのような積極的で主導的な働きかけではなかった。
しかも、それが推薦者にとってたいへんなリスクを伴うことは、作家でない私にも推測できた。表面的でなく作品の内容にまで深く関わるということは、応援する作家の面倒を一生見るほどの覚悟が必要だし、作品が読者に受け入れられなかった場合、その不人気の責任まで負わねばならないこともある。事実、島田先生は、あれらの革新的な作品を理解できなかった一部の読者から感情的な罵詈雑言を投げつけられ、また、銀座あたりでただ酒にありつくためだけに徒党を組んでいるような連中からも、「島田荘司はボスになるために手下を集めている」などと、己の下劣さを掩蔽する目的での誹謗中傷を浴びせられた。そのような逆風が吹いているにもかかわらず、島田先生はどうしてこんなに懸命になって本格ミステリーの復活を願うのだろうかと、私は考えていた。
今、私がこうして作家になっているのは、東京創元社の鮎川哲也賞で『吸血の家』という作品が佳作をいただいたからだ。当然、私は、同社からデビューするものだと思い込んでいた。だから、島田問題は単に興味深い一つの謎でしかなく、そのため、戸川編集長(現社長)に、「島田先生はどうしてあんなに熱心に新人の推薦文を書かれているのでしょう?」などと呑気に尋ねたこともあった。
ところがである。私は、諸般の事情により、講談社から『地獄の奇術師』という作品で世に出ることになった。しかも、担当編集者のU山氏は、島田荘司先生に原稿を読んでもらい、できれば推薦を頼むと言うではないか。まったくの他人事だと思っていたことが、突然、自分自身の出来事になったのである。私は運命の不思議さに、心の底から驚いた。
打ち合わせのため、私は担当編集者と一緒に何度か島田先生とお会いした。そして、作品内容に関する提言を受けたり、実際に推薦文をいただいた。そうして、御本人と直接お話をする機会を得てひしひしと感じたのは、島田先生が本当にミステリーを愛しているということと、ミステリーの将来のあり方に関して深く思いを馳せていること、ただこの二つの純粋な気持ちだった。何のことはない。謎は、一番簡単な答によってあっさりと解けてしまったのである。
【大好きな作家クレイグ・ライス】
人生における男と女の出会いと同様、ミステリーにおける読者と作品との出会いにも、一目惚れというものが存在する。私がクレイグ・ライスの作品を好きになった瞬間もそれだった。初めて出会った〝彼女〟の名前は『大はずれ殺人事件』。ライスの作品の中でも『スイート・ホーム殺人事件』、『素晴らしき犯罪』と並んで上位に位置する傑作である。
ライスの多くの作品では、〝爆笑トリオ〟とか〝酩酊三人組〟と呼ばれるジェイクとヘレン・ジャスタス夫婦に、弁護士のジョン・J・マローンが活躍する。特に私のハートをノックアウトしたのが、ヘレン。金持ちの娘にして、完璧な美貌と姿態を誇る絶世の金髪美人。しかし、彼女はとりすましただけのつまらない女性ではない。偽証や軽犯罪はなんのその。恐ろしいスピード狂で車をカーチェイスばりに乗り回し、拘留された警察署で警察官たちとトランプやサイコロ賭博をし、犯人や手がかりを追って、パジャマの上に豪華なミンクを着たまま夜中の街を奔走する。とにかくあらゆる面で〝飛んでいる女〟だったのである。
元新聞記者のジェイクは、そんなヘレンを心から愛する典型的なアメリカの好青年。一方、マローン弁護士は、彼ら二人を暖かい目で見つめる保護者然とした人物。背が低く、小太りで、髪が薄くなりかけている。酒とポーカーと美女をこよなく愛し、家賃が払えないほどいつも素寒貧。徹夜明けで、よれよれのシャツにネクタイは耳の方へ曲がり、靴紐は解けている。けれども、弁護の腕だけは一流だ。
ライスの作品の特徴は三つある。一つは、たぐいまれなユーモアに満ちて、コメディ・ミステリーとして一流なこと。そして、それと相反するシニカルな悲哀感を物語の根底に含んでいること。彼女の作品は〝都会的な〟と形容されることが多いが、それは人生のやるせなさや悲しみなどを、一見、明るいジョークにくるんでさりげなく表現しているせいであろう。
ライスの生い立ちはあまり幸せではなかった。小さい時に両親に捨てられ、ほとんど孤児同然に育っている。成人してからも、結婚と離婚を何度か繰り返し、『タイム』誌の表紙を飾るほどミステリー作家として成功しておきながら、最後はアルコール中毒になって死んでいる。そうした彼女の悲劇的な私生活面が、執筆作業に何も影響を及ぼさないわけがない。
三つ目の特徴は、小説の構成が巻き込まれ型のサスペンスであること。ジャイク、ヘレン、マローンの爆笑トリオも、自分から好んで事件に関わるわけではなく、いつも否が応もなく犯罪に引き込まれる。また、彼らは実によく酒を飲む。そしていったん事件にかかわると、ほとんど寝ない。不眠不休で事件の起こった街を駆けづり回り、ラムやジンやビールを気付け薬にして、ヘトヘトになりながら、最後まで頑張り抜くのだ。
話は少しそれるが、私はブルース・ウィルス主演の『ダイ・ハード』を見た時、これはライスの爆笑トリオものじゃないかと思った。『ダイ・ハード』でも、主人公の警察官は愛する妻をテロリストに拉致され、彼女を救うために孤軍奮闘する。彼は傷ついても傷ついても立ち上がり、敵に立ち向かっていく。その無謀ぶりと頑固さが、ライスの作品と如実にダブって見えたわけだ。もちろん、ブルース・ウィルスが従来型のマッチョマン的ヒーロー(スタローンやシュワルツネッガー等)でなかったことも、そう思えた理由だ。ちょっと崩れかけた外見に、ひ弱そうな顔、どうみても、真っ先に撃ち殺されるような脇役タイプ。そうしたさえない外見も含めて、全編を貫くやせ我慢と辛抱ぶりが、まさに、我れらがジョン・J・マローンにそっくりだと感じたのである。
今回表題作として選んだ『マローン殺し』は、そんなマローン弁護士を主人公としたライスの待望の短編集だ。待望のというのは、今まで数々のミステリー雑誌に分載され、今回初めて一冊にまとめられたものが出版されたからだ。もちろん、新たな読者にとり、そんなことは重要ではない。大事なのは、この本でたっぷりとマローンの奮闘ぶりを味わうことができるということだ。そして、この短編集を読めば、誰でもマローンを愛するようになり、クレイグ・ライスの他の長編をすぐにでも捜したくなるだろう。
【カレーの王道】
子供の頃からカレーが好きだ。
十年ぐらい前、大学生の頃に、友人二人で東京中のカレー屋を食べ歩いた。最初は、いわゆるカレー・ライスを探求して住んでいた町のあたりを歩いていたが、辛さや香辛料に惹かれるようになり、最後は足を伸ばして、都内にある本格的なインド料理店に行き着いた。
吉祥寺のまめ蔵を皮切りに、高田馬場のボルツで辛さ二十倍のカレーに挑戦し、新宿・タカノのワールド・レストラン、中村屋、ボンベイ、銀座のナイル・レストラン、アショカ、デリー、九段下のアジャンタ(今は二番町のみ)、渋谷のサムラート、
六本木のトップス&サクソン、神保町の共栄堂、ボンディ、秋葉原ベンガル、赤坂のモティ、原宿のBEE、神田のガヴィアル……などなど、百軒以上の店で舌鼓を打った覚えがある。
そして、いろいろ食べ歩いた結論は、一軒では自分の味覚を満足できないということだった。つまり、店によってメチューの中に得意な物とそうでない物があるという発見だった。ある店は肉系のカレーが美味しいが、ある店は野菜系の方が美味しい。ナンが美味しい店もあれば、サモサが美味しい店もある。ブリアニが美味しい店もあれば、サフラン・ライスが美味しい店もある。タンドリー・チキンが美味しい店もあれば、シシカバブーが美味しい店もある――といったように、味もボリュームも値段も接待も雰囲気も、当然ながら千差万別であった。
したがって、ここ一店がお勧めという究極で至高のカレー屋はない。私自身、その日の気分や好みによって、食べ分けている。最近は、東京にタイやスリランカ料理などの東南アジアの料理店も増えた。したがって、カレーのバリエーションも増えて、たいへん嬉しく思っている。
過去二回の海外旅行が、タイとマレーシアだったというのも、カレー料理が好きだから、と言ってしまえる。
作家になり、自由な時間が取れるようになったのを機会に、またカレーの食べ歩きをしようかとも思う。今度は日本国中のカレー店が相手だ。函館の五島軒、横浜元町のタージ・マハール、鎌倉の珊瑚礁、名古屋のMORI、京都のスジャータ、森繁、インデアン、大阪のオリムピック、ルーデリー、タージ……みんなみんな、味を磨いて待ってろよ!、
【マイロングセラー(1)】
マイケル・ボンド作の有名な『くまのパディントン』・シリーズ(松岡享子訳)を最初に読んだのは小学三年生の頃だったと記憶するから、もう三十年以上前になる。同時期に、東京都が多摩地区にモノレールを造ると発表を行なったが、それが実現するのにもほぼ同じ年月がかかっている。
この小説の内容は、ペルーから船でやってきた一匹の子供のくまが、イギリス人の善良な家族に拾われ、無邪気さ故に様々な騒動を巻き起こすというユーモアものである。小学生の私は、主人公の傍若無人な活躍に喝采を送り、たちまちこの小説の虜になった(大人になった私は、主人公の無責任さや無軌道な行動に眉をひそめざるを得ない)
パディントンの本は、福音館という児童書系出版社から出ていて、他に、『パディントンのクリスマス』や『パディントンの一周年記念』など四冊があった。その後、かなり間をあけつつ『パディントン妙技公開』まで七冊が刊行された。しかし、紹介はそこで途切れ、待てど暮らせど後が出ない。私の知っている限り、このシリーズの原書は十二冊あり(実は、高校生の時に、洋書屋で原書を取り寄せたのだ)、それが何故、最後まで翻訳されないのか不思議でたまらない。福音館の本は今でも現役のロング・セラーであり、パディントンはお菓子や絵本、衣服のキャラクターにもなっている大変な人気者だ。あとたった五冊なのだから、ぜひとも訳出してほしい。
【マイロングセラー(2)】
アメリカのSF作家エドガー・ライス・バローズの書いた原作の小説を読んだことがない人でも、密林の王者ターザンの名前を知らない者はいないだろう。年輩者なら映画やTV番組で、若者なら、最近公開されたディズニーのアニメで、鬱蒼と生い茂るアフリカのジャングルを、野生の動物たちと共に縦横無尽に駆け巡り、飛び回る、筋骨たくましいこの超人の勇姿を一度は見たことがあるはずだ。
しかし、映像化されたターザンは、原作におけるターザンの魅力のほんの一部を表現しているに過ぎない。映像版ターザンは怪力無双であっても、「俺、ターザン。お前、ジェーン」流に人間の言葉を片言しかしゃべれない。それに対して、本物のターザンは、運動能力抜群の上に知能指数も非常に高く、数カ国語を話すのだ(動物語も)。
とにかく、ターザンの小説を一読した者は、この世の中にこんな面白い物語があったのかと、絶対に驚嘆賛嘆し、強い感動を覚えるに決まっている。嘘だと思ったら、第一作『ターザン』と第二作『ターザンの帰還』が、創元推理文庫から新訳で出ているので、ぜひ読んでみてほしい。
ターザンの小説は全部で二十六作あり、早川文庫から《ターザン・ブックス》と銘打って、すべての翻訳が出るはずだった。残念ながら、訳出は二十三作までで頓挫しており、爾来十年以上、残り三作の紹介がなされていない。まったく不可解な話である。
【マイロングセラー(3)】
子供の頃から運動音痴で運動嫌いの私だったが、一つだけ見るのもするのも大好きだったスポーツがある。バレーボールだ。ミュンヘン・オリンピックで男子チームが金メダルを取った時に小学六年生だった私は、今の青少年がサッカーに熱中するように、バレーボールに夢中になった。
当時、日本中のバレーボール・ブームをより過熱させたものに、浦野千賀子の『アタック№1』と、望月あきら・神保史郎の『サインはV!』という二つのバレーボール漫画の人気があった。スポ根漫画の代表であり、私も、この二作は何度も読み返した。どちらの作品にも様々な必殺技が出てきて、ことに『サインはV!』の、魔の変化球サーブいなずまおとしとX攻撃には痺れに痺れた。恐ろしく派手な攻撃だったからだ。
『サインはV!』は、何度も単行本化され、岡田可愛主演でテレビ・ドラマにもなったので、物語は人口に膾炙している。X攻撃は、主人公の浅丘ユミと混血児のジュン・サンダースとが息を合わせて行なうスパイクだが、ジュンは病気で早世してしまう。そして、チームは優勝し、ユミを含むチームは、日本代表として海外遠征の徒に着くのだ。テレビ・ドラマも漫画の単行本も、みんなこの場面で終わっている。
ところが、雑誌連載時には、この後に《ブラックスター編》というのがあった。アメリカ遠征で惨敗した日本チームを鍛えるため、恩師の牧コーチがあえて悪役に回るのだ。この名作漫画の完全版の刊行を望むのは、ファンとして当然のことであろう。