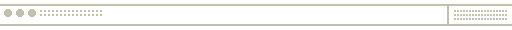
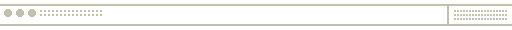
�ȉ��̍�i�́A�l�Ŋy���ޑ��́A�֕����ł��B
�w��Փ��̕s�v�c�x�ɂ���
�u��Փ��̕s�v�c�v�́A�������߂Ė{�i�I�Ɂs�Ɛl���āt�Ɏ��g���������ł���B�]������W�J���Ă��閼�T��E��K�����q�V���[�Y�̏ꍇ�ɂ́A���p������l��\�ʑ��̂悤�ɁA�P�ʑΈ��ʂƂ����}���̖`�������v�f���܂�ł��邽�߁A�Ɛl�͂���قljB����Ă��Ȃ��B�ނ���A��Έ���`�����߂ɁA���l�͈��l�炵���s�����A�o�ꂷ��B����͂���ł��܂�Ȃ��̂����A�������A�ӊO�ȔƐl�����҂�������ɂ̓J�^���V�X�����Ȃ��Ƃ����ᔻ�����R���݂���B�����ŁA���̍�i�������ɓ������ẮA�O���O���A�_���I�Ō����ȔƐl�T��������Ă݂悤�ƍl�����B
�@����͔��ɒP���ŁA��w���̔��p�ƃO���[�v������ړI�������āA�s��Փ��t�Ƃ��������m�̊C���ɕ����ԌǓ��֑D�œn��B�����ɂ́s�����̊فt�Ƃ�����قȐ��m�ق�����A�؍݂��n�߂��ނ�̊ԂŘA���E�l���N�����āA���|�̉Q���ɓ������܂��Ƃ������̂��B�܂�A�s�Ǔ��t�{�s�فt�{�s�N���[�Y�h�E�T�[�N���t�{�s�E�l�S�t�Ƃ����A�܂��ɖ{�i���������̒�Ԃ̂悤�ȍ�i�ł���B
�@�o�ꂷ��N�j�����A���Ȃ�{�i�����ɂ��肪���ȃL�����N�^�[�ƂȂ��Ă���B�c�_�D���Ō����₷���A�܂����������B�ݒ��A�~�X�e���[�}�j�A�Ƃ����̂͂ł��邾���r�������A����ł��A�����͂��邽�߂̍ŏ������]�~�͔�I�����B
�s�Ǔ��̘A���E�l�t�Ƃ����e�[�}�́A���������̐��E�ł͔��Ƀ|�s�����[�ȃe�[�}�ł���B�N���X�e�B�[�́w�����ĒN�����Ȃ��Ȃ����x��M���ɁA�ߔN�ł͓��ɁA���ҍs�l�w�\�p�ق̎E�l�x�A�L����L���w�Ǔ��p�Y���x�A����Y���w�ĂƓ~�̑t�ȁx�Ƃ���������̎��n������B�������A�m���Ă���قǂɂ͍�i���͏��Ȃ��B����́A������Ŕ��ɓ�����������邩�炾�B
�@����͌Ǔ��ł��邩��A�L��A���͉͂ʂĂ����������C���B�E�l�Ƃ������|���N���N���錻��́A�L�`�̖�����Ԃɂ���A�N�ɂ�������͂Ȃ��B����Ԃ̒��ŁA�e�^�҂͂��̂�������肳��A�e�^�҂��Ɛl���T������A���Ԃ̓��ɐ���ł���B����̓W�J��Ɛl�̈ӊO���ɂ����R�Ƙg���͂߂��Ă��܂��i�ނ��A���ꂪ�t�ɕs�v�c�ƃT�X�y���X�������o���_�ł�����j�B���̋����̈�̒��łǂꂾ������ȓ��������ďo���邱�Ƃ��ł�����̂��A�@���ɐ�����Ƃ̘r�O��������邱�ƂɂȂ�B
�@���������āA���̃e�[�}�Ɏ����߂邱�Ƃ́A�����Ƃ����d�ȍs�ׂȂ̂��B���������ƁA�������鐄�������̓ǎ҂̑O�ɖ��S�Ȏr���N�����˂Ȃ��B�����A����́A���ꂪ���̃~�X�e���[�������������̂������ł���B���̂��߁A�s�{�i�t�ł��邱�Ƃ������W�Ԃ��A����̖ʂł������I�Ȃ��𑵂̂��āA�����ās�Ǔ����́t�ɒ��킵�Ă݂��B
�@���c���i�搶���w�{�i�~�X�e���[�錾�T�E�U�x���Ă���A��ʓI�ɂ��A�{�i�����ɂ�����s�R�[�h�t�Ƃ��s��t�Ƃ��s���u�t�Ƃ����ϓ_�ɂ��Ȃ蒍�ڂ�������悤�ɂȂ����B���l�́A�{�i�������N���V�b�N���y��n�[�h���b�N�Ɠ����l�����Ƃ��ĂƂ炦�Ă���̂ŁA�����̗v�f���A�P�Ɏ��M�f�ނ̈ꕔ�ɂ������A�{�i�����̒��ɖ{�i�̃R�[�h�����p�����͓̂��R���ƍl���Ă���B������A���q�V���[�Y���������ɂ́A���܂肻����ӎ��������Ƃ͂Ȃ������B
�@���c�搶�̘_�ł́A�R�[�h�̑��p�͍�Ƃ���A�{�i�����̐��ނɂ��q����댯������Ɗ뜜����B�������A���͂����Ɗy�ϓI�ł���B���̂Ȃ�A����ł́\�\�Q���ׂ����Ƃ����A�s�R�[�h�t��s��t�Ƃ�������������@��̓�������S�Ɏg�����Ȃ����H�▼�������Ȃ����炾�B���������āA�{�i���������s�����莩�������N�����قǁA���̋Z�@���~�����Ă�����A�`�[�����Ă���Ƃ͍��̂Ƃ���܂��v���Ȃ��B
�@���c�搶�́s�E�l�t�́s�|�p�Ɓt�ł͂Ȃ��Ƃ����ӌ��ł��邪�A����ɂ��Ă����͈ӌ����Ⴆ�Ă���B�r�̗ǂ��E�l���������Ă���̒��ł́A�s�E�l�t�ł��邱�Ƃ��ꎩ�̂��s�|�p�Ɓt�Ƃ��Ă̎��i�Ă��邱�ƂƓ������ƍl�����邩�炾�B
�@�������A�������܂������������l�̈�ɒB���Ă���Ƃ͎v��Ȃ��B�܂��A�{�i�R�[�h�Ɋւ���g�����Ȃ��̖ʂł̊J�́A�������������߂Ă���B�����炱�����́A�����A���E�ō��̐������������������Ƃ�����]�������������Ă���̂ł���B
�w���T�㐅�T�ѓm�ڂ̑�`���x�̂��Ƃ���
�@�D���Ƃ̂��߂̃m�[�g
�@���T��E���T�T�g�������鏉�߂Ă̒Z�ҏW�ł���B�ƌ����Ă��A�ނ�����{�́A�����_�ł͂܂����ɓ�������Ȃ��B�u�y���}�W�b�N�v���ԏ��X���Ɓu��Փ��̕s�v�c�v�p�쏑�X���ł���B�O�҂̎����́A���̒Z�ҏW�Ɠ������A���s�㗝�X�ɋ߂�T�g���Ɣ����R�������R���r��g�݁A�߂����ɁA�u�z�K�}�W�b�N�v�Ƃ����V�삪�������\��ł���B��҂́A��w������̃T�g����`�������̂ŁA������u�F���_�̕s�v�c�v�Ƃ����V��\�ł���Ǝv���B
�@�M�҂͍���A�T�g���̕�����A����҂Ƒ�w���҂̓�ɕ����ď��������Ă��������Ɗ�]���Ă���B���̏ꍇ�A����҂͔����R�����삪�A��w���҂͕��c�����N�����_�ƂȂ�ł��낤�B
�@�Ȃ��A���̒Z�ҏW�Ɏ��߂�ꂽ��i�́A����������n��I�ɂ́u�y���}�W�b�N�v���瑱�����̂ƂȂ��Ă���B
�w�r�[���̉Ƃ̖`���x
�@�薼����z���ł����������邩�Ǝv�����A���̒Z�҂́A���V�ەF���̒��ҁu�����̉Ƃ̖`���v�̖{�Ǝ��ł���B�R�Ԃ̐l�����ꂽ�ꏊ�Ɉꌬ�Ƃ�����A���̉Ƃ̒����r�[�����炯�ł������Ƃ������͓I�Ȑݒ�́A���V�����q�̂����B�u�����̉Ƃ̖`���v�̒��ɁA�r�[���Ɋւ��邱�Ƃň�_�����s��������A���̕s������������ړI�Ŏ��M���ꂽ��i�ł���B
�w�w���}�t���f�B�g�X�x
�@���L�Ɋւ���g���b�N�́A�^��Ƃ̖^���쒷�҂�ǂ�ł��鎞�Ɏv�������B�ƌ������A���̂悤�ɍ��o���ēǂ�Łi�������āj���܂����̂��B�ŁA�^���͂����������̂���������A�����Ȃ������̍�i�Ɏg�����킯�ł���B
�w�u�{�w�E�l�����v�̎E�l�x
�@�ǂ�ł��炦�Ή���Ƃ���A���a���j���̌���u�{�w�E�l�����v�ɋ^����������_����h���������e�ł���B���@�Ɋւ���s���͍]�ː에�������q�ׂĂ��邪�A�܂����������������B�����Ɋւ���^����쒆�ɏ������Ƃ��肢�낢�날��A�܂��A���Ԃ��Ƃ̊O�ǂɐ݂����Ă���_��A�J�˂���ɖʂ��ĉE�i�g�C���̂������j�ɂ���_�Ȃǁi�����̘L���̊p�ɂ���ׂ��j�A�Ɖ��̍\������ς��Ǝv���Ă���B
�w�痈��������x
�@���c���i����z�~�X�e���[�̃p���f�B�A�Ƃ��������A���c�~�X�e���[��͕킵�ď����ꂽ��i�Q�𝈝�����ړI�ŏ������B�u���X�����X�Ɍ������v�Ƃ������_�͒����I�ł���A��㈓I�Ș_�����d������{�i�����̗��ꂩ�猾�����܂�D�܂������̂ł͂Ȃ��B�u���Ɍ����邩�v�͌l�I�Ȏ��_�ɗ��r������̂ŁA�������Ė��l��[������������̂ł͂Ȃ��B���̂悤�ȍ�i���������Ƃ��������̂́A�����E���c���i��������l�ł���B
�w�������{�x�̂�����̌㏑��
�@���{���甲���o�ā\�\
�w�������{�x�Ƃ����Z�ҏW�ɂ́A���T��E��K�����q������O�̍�i�\�\�u���V�A�ق̓�v�A�u�����̃����v�A�u����v�����߂��Ă��邪�A���e�I�ɂ͔��Ƀo���G�e�B�ɕx���̂ɂȂ����B
�u���V�A�ق̓�v�́A�V�x���A�̐ጴ���ނ���Α��̊ق������������Ԃ̓��Ɋ��S��������Ƃ����_�C�i�~�b�N�Șb�ŁA�g���b�N�ƃv���b�g�ƃX�g�[���[�������ɉ�����������i�Ǝ������Ă���B����̒Z�҂̒�������I�ׂƌ�����A�S�O�Ȃ���������B�����Е��ɂ̈���N��搶�ҏW�́w�{�i�����P�x�ɁA�u�Ԏ����̎E�l�v�Ƃ����f�B�N�X���E�J�[����삵���Z�҂����^���Ă������������A���́u���V�A�ق̓�v�́A�����V���[�Y�ɏK�����薼�ǂ���A���Ƃ��Ƃ̓G�����[�E�N�C�[������l���ł������B������A�������[�́w��z�̕����x�Ƃ����������낵�A���\���W�[�̂��߂ɁA��K�����q���̂ɏ������߂��̂������B
�@���������A�����̃��V�A��́A���ׂĈ���搶�̍Z�{���Ă���B���̂��ƌ����A�����Q�l�ɂ����{���A���ׂĉp�ꌗ�ŏo�ł��ꂽ���̂��������炾�B���͖{�̒��ɏo�Ă��錾�t�����V�A�ꂾ�Ƃ���v���Ĉ��p�����̂����A����̓��V�A��̉p��ǂ݂ɂ����Ȃ������̂ł���B�悭�l���݂�A�\�A����O�ɁA���V�A�̓�������Ɋւ���{���\�A�̒�����o��͂����Ȃ��B���R�A���{�œǂ߂郍�V�A�̗��j�����A�����ŏ����ꂽ���̂��肾�����킯���B
�u�����̃����v�́A�����n���Ђ́w�\�~�ʓ�\���̓�x�Ƃ����A���\���W�[�̈�҂ɐG������ď������B���̍�i�ł͏�����Ƃ������ŎE����Ă���̂����A�g���b�N���̂��̂͏�����Ă��Ȃ��B�ł���Ȃ�A����𑱂��Ƃ��Ď����������Ǝv�����B�����q�ׂ�A�����̏����~�X�e���[��Ƃ̃��f�����N�ł��邩�͎����ł��낤�B
�@�Ƃ���ŁA�ʔ������ƂɁA���̒��ɂ́A�u���V�A�ق̓�v�̃��C���E�g���b�N��"����"�Ɗ�����l��"�n�����Ă���"�Ɗ�����l�̓��ނ����݂���B���������Ӗ��ł́A����̓~�X�e���[�ɑ���ǂݎ�̊������������g�}�X�������ƂȂ肤��B�������A�O�҂͖{�i�����D���ł���A��҂͔ƍߏ����D���Ƃ������ƂɂȂ�B���l�ɁA�u����v�̂悤�ȃN�C�[�������W�b�N�����őS�҂��܂Ƃߏグ����i���A���ƍD���������͂����肷��X���ɂ���B
�w���A�E�X���C���@�̎S���x�̂�����̌㏑��
�@�f�r���[��Q��
�@����u���A�E�X���C���@�̎S���v�ɉ�����ɓ������ēǂݕԂ��A�u������āA���T��E��K�����q�������_�[�ƃX�J���[�̓�l��������Ă���A�܂�Łw�w�|�t�@�C���x�����v�Ƃ��v�����B
�@����͂��Ă����A��N����IN�POKET�ŁA�u�n���̊�p�t�v�Ɋւ��Ă̎v���o�����������A���ɂ́A�u�n���̊�p�t�v�Ɓu�z���̉Ɓv�̓��i�̃f�r���[�삪���݂��邱�Ƃ��q�ׂ��B��������ƁA���̑�O�Ԗڂ̒��ҁu���A�E�X���C���@�̎S���v�́A�f�r���[����ɊY�����邱�ƂɂȂ�B��ʓI�Ɍ����i���ƂɃ~�X�e���[��Ƃ̏ꍇ�j�A����ڂ̍�i�͎����ƂȂ�A���̍�Ƃ̗͗ʂ�����ꍇ�������B���ۂ̘b�A�ǎ҂Ƃ��Ă̎����A�f�r���[���삪�������낭�Ȃ�������A�͂������Ă�����Ƃ̏����́A���̌゠�܂�ǂނ��Ƃ��Ȃ��B
�@�ł́A���������ϓ_����]���������A�u���A�E�X���C���@�̎S���v�͂ǂ����������B�����Ō����̂��������A���Ȃ�ǂ��d���������̂ł͂Ȃ����Ǝ������Ă���B��w����ɗ��q�V���[�Y�̒��Ŕ�䍂��Ȃ���l���Ă������A���̌����̂Ђ�߂������ɂ́A�܂��ɋ��에���̏�ԂɂȂ����B���M���ɂ������̎艞�������������A�������̓䇁�������グ�����̊����Ə[�����͍����Y��邱�Ƃ��ł��Ȃ��B
�@���́A��������������ɂ�������̈�Ƃ��āA���̂悤�Ȃ��̂�z�肵�Ă���B���Ȃ킿�A�쒆�̓�Ƃ��ꂩ�瓱���������́A����̓o��l�����������Ɠ����ɁA�ǎ҂������ʈȏ�ɋ������Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B���̈Ӗ��ł́A���̌����́A�����̓ǎ҂𑊓��̃J�^���V�X�֓��������̗͂����邾�낤�ƁA��]�I�ϑ����������Ă���B
�@���q�ׂ��_���܂߂āA�u���A�E�X���C���@�̎S���v�́A���낢��ȓ_�Ŏ��Ɏ��Ȗ�����^���Ă�����i�ł���B���̒��ł��ł�����̂��A��i�̍\���o�߂ɂ���B���̕���̏o���_�́A�����P�Ɂs����̖�������̓]�����t�Ƃ������z�ɂ������B���́A��̖����g���b�N�����邱�Ƃ��o���_�Ƃ��A���̎��͂ɕ���Ə�ݒu���A�l�Ԃ�z���A�l�X�Ȏ�����W�J�����āA���X�ɕ����c��܂��Ă������̂��B
�@���������܂��������肫�Ƃ����������́A���l�ȏ����W�������̒��ł��A�قƂ�ǐ����������L�̂��̂ł���B�t�Ɍ����A���ꂪ�s�{�i�t�̏ł���A�M�͂ł����낤�B
�w�n���̊�p�t�x������̍�
�@�ǂ�Ȑ���������Ƃ�������������Ȃ����A�����A�������g�œǂ݂������̂��������Ǝv�����̂��A���́w�n���̊�p�t�x��w�z���̉Ɓx���M�������������ł���B
�@��̓I�Ɍ����A���Ԃ𑛂����厖���A粘f�I�Ȕ閧�A�l�������ꂽ�\�z�A��ȃg���b�N�A�_���I�ȓ�����A�A�N���o�`�b�N�Ȍ����A�����̂悤�Ȕƍ߁\�\����ȗv�f�ɖ���������ŁA�������A��Ȗ��T�オ����A�Ȃ��D�܂����B
�@���I�s�l���̏o���ȍ~�A���X�A�o�ł����~�X�e���[�̓��e�������ԑ��l���������A�����ẮA�ƍߕ������̂�g���x�����̂��肪�X���ɕ��сA�l�I�ɂ͔߂����������B�����Ă��Ȃ���A�����ŏ��������Ȃ��A����Ȑؔ������C�������������B
�@�����āA�����グ����i�́A�����̒ʑ��`���ɁA�{�i�����̐D���Ȏ肪����荞�V�@�����ƁA��̎��������Ă��B
�@�Ƃ͌����A�{�i�������W�T����_�����ƁA�T�㏬�����W�T����`�����́A�ӊO�Ƒ����������B�G�����[��N�C�[���̂��Ƃ��A�����ʼn��ܓI���������X�ƓW�J����ƁA����̌y���ȗ���𒆒f���邱�ƂɂȂ�B����A������f�B�N�X���E�J�[�̂悤�ȉ���`�����̂̏ꍇ�A�T��́A���I�؋��̗L���ɂ�����炸�A�����I�ɐ�������炴��Ȃ��B���Ⴉ����������������A�T�オ���^���^�����������Ă�����A�s���I�ȓG���Ɛl�ɂ������Ɠ������Ă��܂��̂��B�@���������āA���q���̂̎��M�ɂ������ẮA���̓w�����ǂ����������邩�ŁA���͂����y������J�����Ă���B
�@�Ƃ���ŁA�w�n���̊�p�t�x�Ɓw�z���̉Ɓx�A�ǂ��炪���ɂƂ��Ă̏�����ƌĂׂ���̂Ȃ̂��B�ꉞ�̕��͂ɂȂ�A��ƂɂȂ�@���^���Ă��ꂽ�̂́w�z���̉Ɓx�����A�����I�ɖ{�Ƃ����`�ɂȂ��Đ��̒��֏o���̂́A�w�n���̊�p�t�x���悾�B�킴�킴����ȍ����Ȃ��Ƃ��C�ɂ���̂́A�ǂ�����������ƐS�̒��ʼn��߂��Ă�������Ȃ̂ŁA�i�ʂ̈��������邩�炾�B
�@�ǎ҂̐����炵�āA�w�n���̊�p�t�x�𐄂����̂�����A�w�z���̉Ɓx�𐄂����̂�����A�l�C�̖ʂł��������t���Ȃ��B�O�҂ł͓��c���i�搶�ɢ�E����A��҂ł͈���N��搶�ɢ��ࣂՂ����B������A���ɂ͏����삪�������̂��ƍl����Ȃ�A����قǍK���ȃf�r���[�������҂͑��ɂ͂��Ȃ����낤�B
�w�z���̉Ɓx���`������́c�c
�@���w�Z5�N���̏H�̂��Ƃ����A����̃h���������K���Ă���ƁA��蕶�Ƃ��āA�J�菁��Y�́w�א�x�̈�߂��o�Ă����B������4�Ƃ������́A��q��Ẩx�q�炪�c�ɂŌu���������ʂł���B�����̕��͂̈ꕔ�ɂ́A�����I�ȕ��͋C���o�����߂ɋZ�I�I�Ȏ�@���p�����Ă���A�n�̕��Ɖ�b���ӑR��̂ƂȂ������ς�肳���������B�o��̕��́A�u����͉����Ӗ����܂����v�Ƃ��A�u��҂͉����l���Ă��܂����v�Ƃ��A�����ɂ������ȓI�ʼn���Ȃ����e����������ǂ��A��蕶�ɂ͂��������������B���͂����������́w�א�x�Ȃ鏬����{���ŒT���Ă���ƁA���䖲���ɂȂ��ēǂݒ^�����B���ꂪ�J�蕶�w�Ƃ̍ŏ��̏o��ł���A�w�א�x�́A���́s���U�̖{�t��1���ɑ����ɉ�������B
�@���������ƁA���̏����O�̉ċx�݂ɁA���͐ΐ쌧�̋���ɏZ�ޔ���̉Ƃ֗V�тɍs���A�c�ނ̏�ɗ������閳���̌u���������肾�����i�����A�����A�_�v���c�ނɔ_����T�����Ƃ���A���S�Ȃ��ƂɁA���̖邩��u��1�C�����Ȃ��Ȃ����c�c�j�B�u��������̔��������i���]���ɂ������������A�ŏ��́A�w�א�x�̊Y���ӏ��ɂ�����Ƃ���A�u�c�c�ł��u���Ɖ]�ӂ��̂́A��ɂȂ��Ă���̎v�Џo�̕����Ȃ������₤�ȁv�Ƃ����C���ł��̏����Ɏ䂩�ꂽ�̂ł���B�������A�Ō�܂œǂݒʂ��Ă݂�ƁA�����P���ɁA�������o���̕���Ƃ�����{�ݒ�ɐ[����������Ă��鎩���������B
�@���́A����قǎ����w�א�x�Ɉ������o�������ƌ����A���Ԃ�A�����ɏ����̌Z��i�o���j�����Ȃ������������낤�B�������A���͒��j�������̂ŁA������������o���~���������̂��B��̐g�ł��鎄���D�����o�ɉ�������\�\����ȏ�ʂɓ���Ă����B������A�S�̒��ŁA�N��̏�����o�Ƃ������̂������Ԃ�Ɣ������Ă����Ǝv���B���̔������ꂽ�S�ە��i�����̏����̒��ɑ��݂��A�ʎ��I�ɕ`����Ă���悤�ɍ��o�����킯���B���ɁA��q�▭�q�Ƃ������Ⴂ�o���ɂ́A�g�߂Ȏo�̎��݂������������悤�Ɏv���B
�@���̂悤�Ȗ���A�������������ƂɂȂꂽ��A�����ƁA���e�̎o�����̂��������ƐS�ɐ����Ă����B���R����́A�₩�ŁA�D���ŁA�R���悤�ȕ��w��i�ƂȂ�͂��������B�Ȃ̂ɁA�����グ���w�z���̉Ɓx�Ƃ�����i�́A�|���A�X���A���낵���E�l����ɂȂ��Ă��܂����B����͎����A�q�������l�ɂȂ���ɁA���R�ƁA�����̖{���̉����邩��m���Ă��܂���������������Ȃ��B
�w�z���̉Ɓx�Ƃ�����i�́A�܂����`�I�ɁA�f�B�N�X���E�J�[�́w�e�j�X�R�[�g�̓�x�ɏo�Ă��鑫�Ճg���b�N�ɒ��킵���{�i���������ł���B����͊ԈႢ�Ȃ��B����ǁA���̂��ǂ남�ǂ낵���b�̒��ɂ́A���a���j���w�{�w�E�l�����x��w���哇�x�ȂǂŔ@���ɕ`�o������̑O�́s���{�l�I�Ȃ��́t�����X�Ɨ���Ă���B�ƌn�ɂ܂��h���ƁA���Ƃ̕���Ƃ����^�����c�c�B
 �߂� |
 �\�� |
